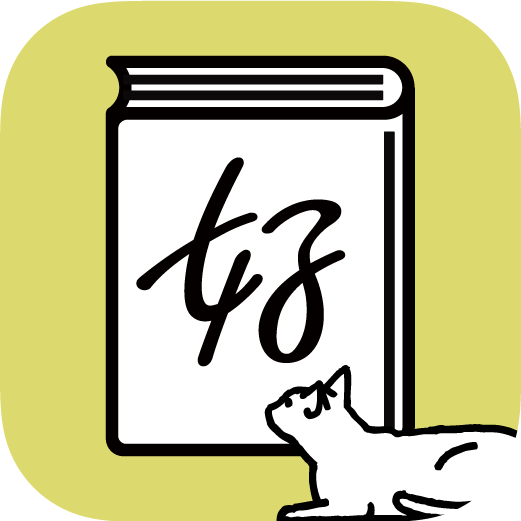ISBN: 9784560093986
発売⽇: 2024/02/29
サイズ: 19.4×3.9cm/496p
「グローバリスト」 [著]クィン・スロボディアン
新自由主義は、アメリカの思想だとされることが多い。規制緩和や民営化を推進するイメージもある。これに対し、本書は中欧から見た新自由主義の歴史を描く。主役は、ミーゼスやハイエクのジュネーヴ学派。その思想は、国民国家と民主主義を制限してでも自由貿易を目指す「戦闘的グローバリズム」だ。
物語は、第一次世界大戦後のオーストリア=ハンガリー帝国の崩壊で始まる。大戦前、帝国内では多民族が共存し、経済は統合されていた。だが、戦後の民族自決で生まれた各国は保護貿易に走った。それを批判したのがウィーンを拠点とするミーゼスらのグループだった。やがて国際連盟のあるジュネーヴに移った彼らは、当初はデータの収集を重視したが、世界恐慌の時代に統計が計画経済の道具になると方針を転換する。市場はデータでは把握できないほど複雑であり、だからこそ国家は市場に介入すべきではない。この論理に従い、数字による説得ではなく市場を守る法の定立が目標となった。
第二次世界大戦後に脱植民地化が進む中で、ジュネーヴ学派は国際機関に期待をかける。その狙いは、途上国の保護貿易を法的に封じることだった。1970年代に途上国が国際舞台での発言力の強化を試みると、それに対抗してハイエクの信奉者たちはGATTの改革を提唱し、WTO創設への道を開く。
本書の分析の中でも、日本の読者としてはジュネーヴ学派とキリスト教神学の類似性が特に興味深い。人知を超えた存在である市場は神に相当し、人はただその価格シグナルに従って行為する。日本人は市場競争への拒否感が強いと言われることもあるが、むしろ新自由主義の方が宗教的な信念に支えられてきたのだ。そんな議論がキリスト教圏の外で説得力を持たないのは不思議ではない。市場競争は本当に望ましい帰結を生むのか。必要なのはデータに基づく政策論争だろう。
◇
Quinn Slobodian 1978年生まれ、カナダ出身。歴史学者。ボストン大学教授。専門はドイツ史、国際関係史。