川本三郎「いまも、君を想う」書評 妻への追慕、端然とせつせつと
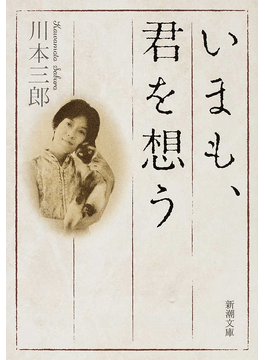
ISBN: 9784101271613
発売⽇:
サイズ: 16cm/199p
いまも、君を想う [著]川本三郎
慎みぶかい追想記である。
追慕の情とともに、ひそやかであること、ささやかなることをみずからの筆致に求める気配がある。そこにわたしは先立たれた身としての慎みのありようを感じ、せつせつとした想いにしずかに触れた。
七歳年下の妻、川本恵子さんが逝ったのは二〇〇八年の紫陽花(あじさい)の季節。癌(がん)と知らされてから足掛け三年間の闘病生活ののち、五十七歳の若さだった。
端然とした文章が胸に響く。ひとりになって二年、しきりになつかしいのは手料理の味、ファッション評論家だった妻のおしゃれ、飼った代々の猫、そして他愛(たわい)のない会話の数々。
「だから言ったでしょう、アロハは三枚目のほうが似合うって」「そのまずいそば食べたい!」「団の面目丸つぶれだわ」
ふとしたとき、在りし日の妻の声がよみがえる。なんということのない日常の言葉のはしばしに、おたがいの理解、愛情の交歓があった。家計も家事もまかせきり、旅行の算段にいたるまで三十余年の結婚生活はことごとく妻の存在に拠(よ)っていたと噛(か)みしめる。
「家内あっての自分だった」
この単刀直入な独白に、二年の歳月が与えた喪失の重みがある。しかし、白旗を掲げたわけではない。介護から離別まで、つまり死という別れをわがものとして受け容(い)れた苦悩のすえの恬淡(てんたん)でもあるだろう。
「六月に亡くなりました」と伝えた、豆腐屋の軒先でのこと。
「おかみさんは、頭にかぶっていた手拭(ぬぐ)いをとって深々と頭を下げてくれた。私の知らなかった家内がいる。近所の人に親しく記憶されている。そのことがうれしかった」
とっさの所作に、死に相対するときの日本人の礼節が宿っていた——こうして綴(つづ)ることで想いは掘り下げられ、岩清水が湧(わ)くようにあらたな命脈が保たれて、みずからを励ます。
亡くなる半年前「ツー・ストライク、ノー・ボール」と歌った妻のあかるい声がよみがえる。毎朝ひとり、川本さんは土鍋でごはんを炊くようになった。うまく炊けるとほっとする。
評・平松洋子(エッセイスト)
*
新潮社・1260円/かわもと・さぶろう 44年生まれ。評論家。『林芙美子の昭和』『郊外の文学誌』。












