諏訪哲史「領土」書評 小説なのか?可能性に挑む
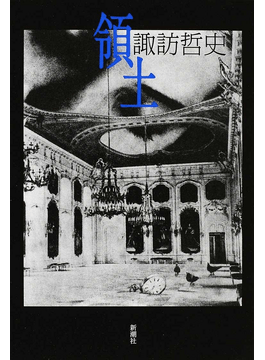
ISBN: 9784103313816
発売⽇:
サイズ: 20cm/333p
領土 [著]諏訪哲史
文学の世界に静かに殴り込みをかける、意欲的な短編集だ。
「幻視」や「残影」に貫かれた一冊。徹底して一人称の語り手によって語られる本書の世界は、短編ごとに舞台を変えながら、迷宮の相貌(そうぼう)を強めていく。ある場所を探索する話が多いのだけれど、出口のわからない迷路のなかをさまよっている感じで、読者は語り手とともにその場所の謎と闇のなかに閉じ込められていく。「なんなんだ、この世界は」と眩暈(めまい)を覚えると同時に、子どもに戻って醒(さ)めない夢のなかを歩んでいるような、妙な既視感と懐かしさも覚えてしまった。
建物の描き方が興味深い。ホテル、学校、デパート、地下街など、閉じているように見えて、どこかに綻(ほころ)びのある空間が、静かに口を開ける。時刻はたいてい夜。女性の同伴者(妻、恋人、母)がいることはあっても、語り手は基本的にひとりぼっちで、存在の不安と闘っているように見える。一人で彷徨(ほうこう)し、自らのドッペルゲンガーに邂逅(かいこう)する予感にしばしば胸を締めつけられる(鏡を覗〈のぞ〉くような、無限に反復される世界!)が、小説のなかでその瞬間は無限に先延ばしされていく。
いま「小説」と書いたが、「小説狂」を自称する本書の著者の、「小説」というジャンルへのこだわりと愛情は並大抵ではない。いまは故人となった劇作家ハイナー・ミュラーが1970年代の終わりに「ハムレットマシーン」というテクストを発表したときにドイツの演劇界に走った、「これは戯曲なのか?」という衝撃を思い起こさせられた。「これは小説なのか?」と読者を驚かせる試みも世界中で行われているが(たとえば昨年邦訳の出たサルバドール・プラセンシア)、本書によって日本語小説の可能性も確実に拡(ひろ)げられたのではないだろうか。虚構のなかに生み出される現実と「作者性」を意識させる仕掛けも刺激的だ。
◇
新潮社・2415円/すわ・てつし 69年生まれ。作家。「アサッテの人」で芥川賞。『りすん』など。












