「魂にふれる―大震災と、生きている死者」書評 「生ける死者」と共生するとは?
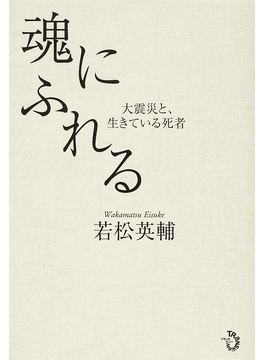
ISBN: 9784798701233
発売⽇:
サイズ: 20cm/225p
魂にふれる―大震災と、生きている死者 [著]若松英輔
この拙文は本書に誘発された筆者の考えと思っていただきたい。
あの忌々(いまいま)しい津波にさらわれた死者の魂の行方を案じていた頃、本書と出会った。そして常に関心事であった「生ける死者」と真正面から対峙(たいじ)する著者の真摯(しんし)な眼差(まなざ)しに共感した。「今日は悲しい」と海に向かってつぶやく初老の男性をテレビカメラが捉える。その言葉を導入として著者の「死者論」が展開される。著者は哲学者池田晶子や万葉歌人の言葉を引用しながら、悲しみは「死者を傍らに感じている合図」と解し、この想(おも)いは著者の中で執拗(しつよう)に反復され、常に読者に寄り添い続ける。
3・11に肉親を失った「君」に悲しみについて語りかける著者はその前年に妻を亡くしており、「君」こそが相対化された著者に他ならず、彼は愛する死者(妻)と共生することで愛を育成させ、「悲愛」と共存しながら今を生きようとする。人は一般的に鎮魂という言葉にすでに死者の魂を想定していることから、著者は死者を「亡き存在」とせず、著名な哲学者、作家、思想家、宗教家の言葉を引用しながら、死者の存在を立証する。その内の一人、歴史家上原専禄は、死者との共存は「歴史と社会の理念」というよりも、彼の妻の死という私的経験によるとして、著者も想いを同じくする。
著者は悲しみから逃れようとしない。なぜなら死者は「呼びかけ」を行う主体だからだ。ここで僕はあるテレビ番組を思い起こした。両親と妹を津波に呑(の)まれて孤児になった幼い姉の夢枕に、両親とともに立った妹の霊が、「お姉ちゃんは津波に勝ったんだから」と生きのびた勇気にエールを送る。姉の悲しみを癒やす妹の言葉に触れた時、感涙と共に自分が救済されたような気持ちになった。
この画面からは著者のいう死者の側からの悲しみを伴った「呼びかけ」というよりも、祖父の家に引き取られて笑顔ではにかむ幼い姉が心の奥で感じたものは、むしろ悲しみからの自立ではなかったかと僕は思うのである。それに対して妻に先立たれた著者の「悲愛」を手放さない魂に触れる時、なぜか切ないものがこみ上げてならなかった。
いったん肉体から分離した魂は物質的世界から離脱して非物質的存在となり、本来の自分自身になろうと努め、肉体の支配下にあった人間的意識にとらわれない限り魂の自由を獲得し、離別した現世の地上的磁場からも解放され、生きる死者として死の彼方(かなた)で自立するのではないか。従って著者の言う「悲しみ」の主体は死者の接近によるというより、むしろ生者の側の「悲愛」が作り上げるイリュージョンではないかと思うのだが、如何(いかが)であろうか。
◇
トランスビュー・1890円/わかまつ・えいすけ 68年生まれ。批評家。「越知保夫とその時代」で三田文学新人賞。著書に『井筒俊彦 叡知(えいち)の哲学』『神秘の夜の旅』など。












