「仏独共同通史―第一次世界大戦」書評 対立の錯誤を明かす実験の書
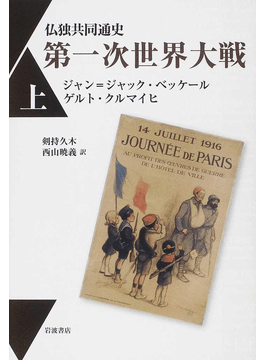
ISBN: 9784000237963
発売⽇:
サイズ: 20cm/200,20p
仏独共同通史―第一次世界大戦 [著]J・J・ベッケール、G・クルマイヒ
第一次世界大戦の分析には多様な論点がある。20世紀の科学技術による悲惨な戦争、帝国解体に至るナショナリズムの勃興、各国間の領土をめぐる対立、米国の台頭、共産主義体制の登場、どの視点からでも論は成りたつ。
本書はこの大戦を仏独2大強国の戦争と捉え、両国の世代の異なる歴史家が共同執筆を試みた実験の書といえる。自分たちが重要な史実と理解しても相手側は異なる見方をしているとの差異に興味がもたれる。冒頭でも指摘されるが、普仏戦争以来、「復讐(ふくしゅう)心に満ちた」仏との見方がされてきたのは、双方の歴史観の歪(ゆが)みでもある。この誤断と現実政治の乖離(かいり)を見るのが本書を貫く軸にもなっていて、第一次大戦前からの両国の対立には歴史的な側面と人為的に煽(あお)られる感情とによる錯誤の増幅が窺(うかが)える。
仏独の関係は20世紀に入るとモロッコ問題などをめぐって危機が昂(こう)じていき、1911年以降はきわめて険悪になった。独には露と英、露と仏の接近により包囲されているとの感情が強まるし、仏もまた独の軍事的奇襲を恐れて兵役の延長などを進める。しかし著者たちは、両国民の「大部分が戦争を望んでいないと答えたであろう」と分析したうえで、仏は「神聖なる団結」、独は「城内平和」という語に象徴されるように国内の団結を固めつつ、本心は戦争は避けたいとの意思を読みとっている。
にもかかわらずひとたび戦争が始まってしまうと、両国は軍事力の総力を挙げて4年3カ月も戦い続ける。その間のヴェルダンやマルヌの戦い、さらには毒ガス使用、残虐行為、戦争文化などを論じながら、仏は独を、独は仏を「敵」としてどう見ていたかを解説する。戦時下では秘密にされたが、仏では毎日平均885人が死んでいたという。2人の歴史家の筆がこの戦争に苦しんだ「時代」を悼んでいることに気づかされる。
◇
剣持久木・西山暁義訳、岩波書店・各3360円/Jean−Jacques Becker 28年生。Gerd Krumeich 45年生。












