神林長平「ぼくらは都市を愛していた」書評 「言語」を通して現実を問う物語
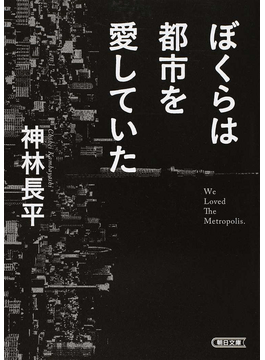
ISBN: 9784022647627
発売⽇:
サイズ: 15cm/366p
ぼくらは都市を愛していた [著]神林長平
デジタルデータのみを破壊する原因不明の「情報震」。それにより世界が混乱に陥り、人類滅亡の危機に瀕(ひん)する悪夢的近未来と、今と大きく変わらない東京、二つの舞台で物語が進行する。
語り手の一人である双子の姉ミウは、日本情報軍観測部隊長であり、「情報震」で無人化した東京に入り込む。そこで、記憶に異常をきたし(人間の脳の働きも突き詰めればデジタルだ)、部下とも接触を失い孤立する。
一見平穏なもう一つの世界で、弟のカイムは、勤務する公安警察上層部の意向で腹部に人工神経網を植え付けられ、疑似的なテレパシー能力を与えられる。仲間同士「腹を読める」だけでなく電脳ネットワークとも接触できるちょっとした超能力だ。ある殺人事件に際し、自分が犯人で同僚女性が被害者だと確信するのだが、自分にはアリバイがあり、同僚も目の前で生きているという不条理に晒(さら)される。
姉弟それぞれの現実は、都市全体が形作る「意識の流れ」と、そこから表出する機械知性の存在が明らかになった時点で転換点を迎える……。
神林の描く物語には常に「何が現実を現実たらしめるか」「きみはどの現実を生きるか」問う部分がある。中心にあるのは「言語」か。本作でも、カイムは「人間にとっての現実とは言語情報であり、言葉、そのもの」と語り、ミウは都市の機能停止を「都市は言葉を失った」と表現する。
評者が繰り返し想起するのは「山月記」で知られる中島敦の小品「文字禍(もじか)」だ。文字が人間の精神活動をトラップして鋳込(いこ)むことを描いたと読める作品だが、神林作品はこれを現代的に深めた所から始まり、今もさらに深め続けている。情報震という着想に現実の震災を結びつけるよりも、むしろ、読者に「現実震」をもたらすテーマの掘り下げに骨太な心意気を感じた。
◇
朝日新聞出版・1890円/かんばやし・ちょうへい 53年生まれ。『敵は海賊』『戦闘妖精・雪風』シリーズなど。












