ジェイ・ルービン「日々の光」書評 肌の色や宗教を越えた“母と子”
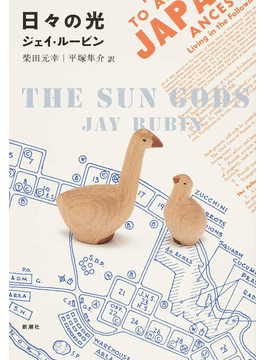
ISBN: 9784105053727
発売⽇: 2015/07/31
サイズ: 20cm/461p
日々の光 [著]ジェイ・ルービン
書き方のスタイルはオーソドックスだし、「母探し」というテーマも新しいものではないが、母と子に血のつながりがなく、しかも肌の色が異なるとなれば話はちがう。
戦前に北米に移住した野村という日系人一家、なかでも気丈さと愛情深さを併せ持った光子という女性が話の中心だ。彼女は移住先で子連れのアメリカ人男性と短い結婚をするが、戦争が勃発して独りで日本に帰国。父の元にもどされたビリー少年は、幼くてその女性がだれかも判断できないまま、彼女への強い思慕の念だけを体の奥に秘めて成長し、大人になって光子を訪ねる旅をする。
強制収容所の箇所が印象深い。光子は夫から預かった幼いビリーとともにミニドカの収容所に移る。この不条理な処遇のことは知識では知っていたが、リアリティーがあったとは言えない。人里離れたへき地に建てられた簡易住宅に1万人もの日系人が詰め込まれたのだ。そこに金髪の少年が交じっている奇妙さ。いじめにあう彼を必死にかばう光子。彼女の経験を追ううちに収容所の細部が体に染み込み感情移入していた。これぞ小説の力である。
後半は留学生として来日したビリーの目で、1959年から東京オリンピック前年までの日本が描かれる。光子を探す九州の旅、そこで探り当てた事柄が未知の事実を明らかにし、ビリーに新しい出会いをもたらすエンディングは光子の戦後にようやく光が射(さ)し込むようで感動を呼ぶ。
北米では光子はクリスチャンで結婚相手は牧師だった。帰国して宗教を離れ、戦禍に苦しむ母国の人々と「怒りに包まれてたがいに愛しあう」道を選ぶ。「ザ・サン・ゴッズ(太陽神)」という原題にもうかがえるように、唯一神信仰への強い疑念が示されている。夏目漱石や村上春樹などの翻訳者として深く日本文化と関わってきた著者の、ひとつの主張がここにある。
◇
柴田元幸・平塚隼介訳、新潮社・3132円/Jay Rubin 41年生まれ。ハーバード大学名誉教授、翻訳家。












