リチャード・パワーズ「オルフェオ」書評 遺伝子の描く音楽の本質
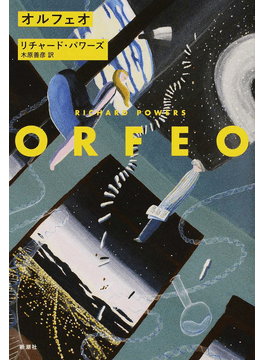
ISBN: 9784105058753
発売⽇: 2015/07/31
サイズ: 20cm/428p
オルフェオ [著]リチャード・パワーズ
主人公ピーター・エルズは七十歳で独り身。オンラインで注文したDNAで自宅でゲノム改変を試みる、日曜遺伝子工学者だ。一方で彼は作曲家でもある。一見無縁に思える二つがエルズのなかでどう結びついたのか。七十年の人生と現代音楽史をより合わせながら明らかにしていく着想は、さすが分子生物学と音楽の両方に通じたパワーズだ。
人間がいなくともこの世に音は存在する。それに秩序と意味を与える形式が音楽ならば、彼の求める音楽は別物だ。「音楽は“何か”そのものであって、何かを“意味”しているのではない」のだから。
若い頃の観念先行は次第に後退するが、調性音楽には向かわない。妻子を捨て、得かかった名声を放棄しても音楽の極北へと突き進み、最後には遺伝子の描く「美の譜面」こそに音楽の本質があるという考えに到達する。
ケージやライヒなど現代音楽家の活躍を同時代に体験した影響は小さくないが、それだけではこの生き方の説明はつかないだろう。結局こうしか生きられなかった人間なのであり、名を残す作曲家の下には彼のような前衛性と奇矯さを併せ持った無名の生が埋まっているのを感じさせる。
孤独な人生である。だが、その姿は昔とは異なっている。かつては大自然の中や孤立した室内で求心的に癒やされたが、現代ではデジタルの編み目で外と繋(つな)がり、自己の発信するものが無限に増殖される。家宅捜索されてバイオテロの容疑で指名手配された彼が、追いつめられた意識を電子の海のなかで解放するのはその意味で象徴的だ。
一つのセンテンスに歴史認識と理念が濃縮され噛(か)み応え十分だが、詩的なシーンも少なくない。ライヒの『プロヴァーブ』が流れるカフェで、この曲に気をとめる女性客とエルズが一瞬のやりとりをするシーンは美しく、音楽とは何かと問う著者の声が聞こえたような気がした。
◇
木原善彦訳、新潮社・3132円/Richard Powers 57年生まれ。作家。『エコー・メイカー』で全米図書賞。












