「空き地」からの問い、世界を見通す視座に 人文書院・浦田千紘 (第8回)
記事:じんぶん堂企画室
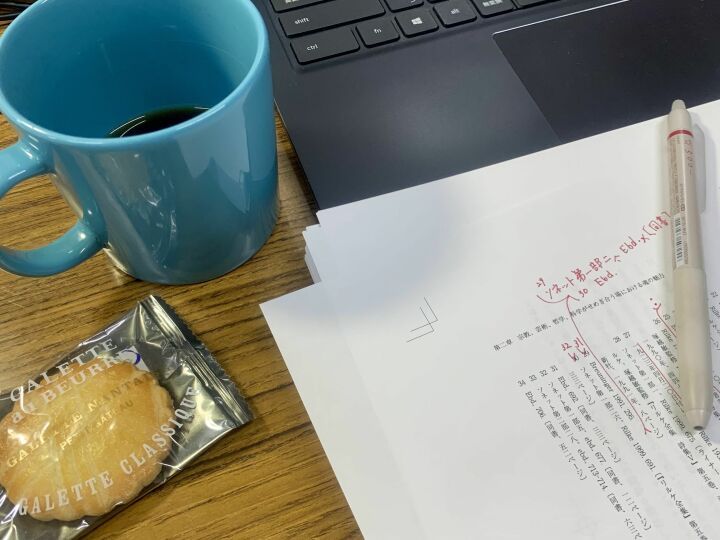
記事:じんぶん堂企画室
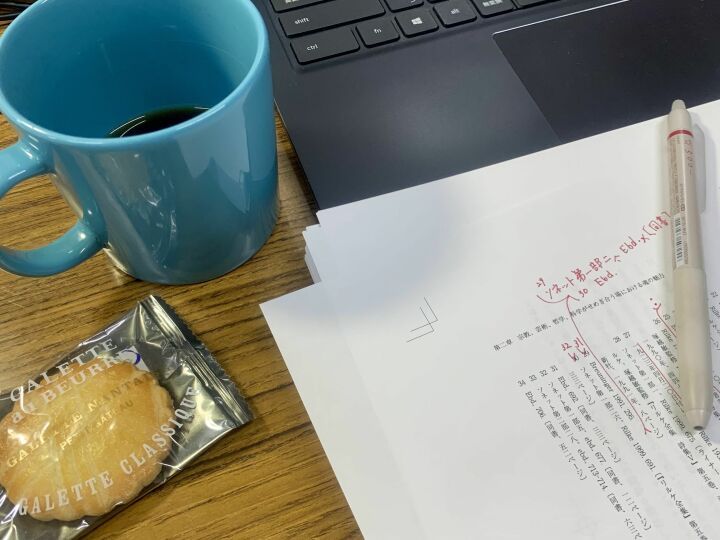
ほかの方と同じく人文書の定義はこころもとないものの、そうも言っていられない。なぜならわたしが働く出版社は、「人文書院」だからだ。
哲学者の鷲田清一がいうには、『夜と霧』(みすず書房)の作者V・E・フランクルは強制収容所のささいな日々の問題を考える果てに、思考の「空き地」に出たという(鷲田清一『「待つ」ということ』角川選書)。「人生から何をわれわれはまだ期待できるかが問題なのではなくて、むしろ人生が何をわれわれから期待しているかが問題なのである」という、「思考の方向転換」をもって。フランクルの経験は人類史上でもひときわ壮絶な部類だが、人生で岐路に立たされることはどんな人にでもあるだろう。他者の「思考の方向転換」の軌跡を知れる方法の一つが、書物だと思う。
「空き地」が問いを立て直す場所だとすれば、多かれ少なかれ、人文書は問いが大好きだ。「世界はそうなっているから考えても無駄だ」「もともとそうだからしかたない」といった考えに抗って、人は人文書の周りで「なぜ」と立ち止まる。編集者のわたしは、著者の問いにしばし併走させてもらう、そんな意識で企画を上げている。いただいたこの機会に、「人文書の魅力」が見えてきたらという思いで企画の方法を振り返ってみたい。

2019年、営業部から編集部に移ってはじめて企画した本が『99%のためのフェミニズム宣言』(シンジア・アルッザ他、惠愛由訳)だった。なにを企画すればよいか迷って母校の先生に助けを求め、訳すべきだと指南してもらった一冊だ。正直なところ、学生時代にフェミニズムはピンときていなかった。けれど会社に勤めるようになり、なんだか男性社員と扱いが違う、なぜ働きながら恋愛や結婚も同じ熱度をもって意識せざるを得ないんだろうと、日々思うことが増えた(後者は誰でも同じかもしれない)。わたしが人文書院に入社した2017年、『男も女もみんなフェミニストでなきゃ』(チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ、くぼたのぞみ訳、河出書房新社)が大ヒットしたのも思い出しながら、この機会にフェミニズムを学び直したいという不純な動機から出発した本書に、なぜ社会にフェミニズムの視点が必要なのか、教えてもらうことになる。
歴史的にフェミニズムはいくつかの分派があると言われるが、『99%』はリーマン・ショック以降の経済状況悪化を受け、性差別と人種主義が組み込まれた社会の再編をめざし、ますます個人を一企業のようにしていく資本主義に対抗すべく編まれた宣言文だ。差別はともかく、資本主義のどこが悪いのかと思う人も多いかもしれない。もちろん現代社会の問題は資本主義のせいだけではないけれど、個人の価値が賃金やバズの多さだけで測られる世界は息苦しく、資本主義は差別をフル活用して社会を回すことに長けている、というのがこの本の主旨だ。
つい先日見たテレビ番組で、声優で作家の池澤春菜さんが「本は本と結婚して本を生む」と言っていて、編集企画もちかいと思った。本書を真っ先に絶賛してくださったのが、ライターでアナーカ・フェミニストの高島鈴さんだった。『99%』は理想的な社会の方向性をぽんと差し出してはくれるけれども、社会の理想像は描かず、具体的な代替案もはっきりと示していない。根本的な問題はわかった、でも結局どうすれば……という疑問が少なからず残る。ポップ文面に高島さんのSNSから抜粋させてもらい、高島さんのウェブ記事を夢中で読み漁った。会った当初はエッセイなら別の出版社のほうがと遠慮していたが、何度かやりとりするうちに無事に企画が通り、結実したのがアナーカ・フェミニズムをキーワードにした『布団の中から蜂起せよ』である。
すでに書かれていたweb記事や書評をジャンルごとにまとめ直し、高島さんのパソコンに眠っていた文章やブックリストも付け足してもらった。わたしは翻訳以外ではじめての書籍、高島さんは初単著と、はじめてのことばかり。カバーをイラストレーターに描き起こしてもらうのもはじめてで、ディレクションはデザイナーの宮越里子さんの助けを借りた。絶対に入れようと言い合っていた原稿をゲラにし忘れ、高島さんに指摘をもらって冷や汗をかいたことを覚えている。いま思い出してもぞわっとするが、布団から起き上がれない人でも読み続けられるような軽い本を、それでいて書店でも一目をひくような本をと、みなで願いながらつくった時間は幸福でもあった。
生きていることが苦しいか? この世を憎んでいるか? この世の変化を望みながら、その兆しすら見えない現状に失望しているか? 布団の上で動けないまま、特に見たくもないSNSだの天井だの布団の裏側だのをえんえんと眺め、自分でも正体のわからない不安をやり過ごしているか?
あなたにもしそのような経験があるなら、この本はあなたのためにある。あなたがこの本を必要としなかったとしても、この本はあなたのためにできている。(高島鈴『布団の中から蜂起せよ』冒頭より)
そもそも世界はフラットで個々人の自由な競争がおこなわれる場なのか、それともあらかじめ格差や不平等が組み込まれているかで世界観は大きく変わる。後者の代表である人種主義や植民地主義は、中村隆之『環大西洋政治詩学』やバタチャーリャ『レイシャル・キャピタリズムを再考する』(稲垣健志訳)などのメインテーマだ。激化した資本主義がより具体的なアメリカ政治でどのように機能しているのか知りたくなり、これまた『99%』の縁でつながった河野真太郎先生にウェンディ・ブラウンの『新自由主義の廃墟で』の訳もお願いできた。
どの本よりも著者の熱量に相乗りさせてもらったと感じたのは、高島さんに紹介してもらった赤井浩太さんと松田樹さんによる『批評の歩き方』だ。多彩な執筆陣を巻き込みながらできた本は、けっして批評の未来は明るくないものの、これから歴史を編んでいこうとする若手の気概が込もったように思う。
「批評とは、好きな対象を語りたいと思ったときに出てくる言葉のこと」。「空き地」に出れば、おのずとほかの作品との比較や過去の問いの洗い直しが必要になってくる、そしてそんな文脈のなかでこそ現代的な問いが浮かび上がってくるのだと、執筆者たちに学んだ。
すべての本に共通の問題意識が通底しているわけではないものの、本を編んでいるとき、いつも思い出す言葉がある。「社会や国家は少数者の視点から見ないと、ほんとうの姿を現さない」。学部時代、現代政治学の先生から聞いた印象深い言葉だ。冒頭の例で言えば、第2次世界大戦期のナチ・ドイツがどのような国家だったか、国民からの視点では限界がある。映画『関心領域』で描かれるように、収容所の悲鳴が聞こえていてもそれまで通りの生活ができる人たちはいたのだ。少数者の視点をただ借り受けるだけではなく、そこから社会を国家を、そして世界を見通す視座が開ければ、借り受けたことの返礼ができるのではないか。そんな問いのかたちを、人文書と呼びたい。

書物の森が水源だとしたら、そこから賢く、自分にほんとうに必要なだけの、水をもらうことにしよう。ゆきつく先が海だとしたら、そこにささやかな、ありあわせの素材で作った小舟を浮かべてみよう。驚くべきことに、ぼくらはこの小舟に乗って、はてしなく広がる大洋へと出発することができるのだ。そして大洋にはたくさんの本の島が点在し、島にさしかかるたび、古いともだちや知らない島人たちが、海岸から手を振ってくれる。
その希望に支えられて、ぼくらはこの土地で、この都市で、生きている、生きてゆく。
(菅啓次郎『本は読めないものだから心配するな』左右社)
本が出るまでにはさまざまな人がかかわっている。その本を紹介してくれた人、翻訳なら訳してくれる人と原著者、日本語の本ならなによりその著者、印刷所で組版・印刷をしてくれる人、装丁のデザイナー、カバーを飾る絵画や写真の作家など、さらには販売に携わる営業部や書店の人びと、そして手に取ってくれた読者。文フリなど出版社を介さない市場が広がりを見せるなか、出版社が差し出せる対価はなんだろう。不十分ではあるもののささやかな答えとしては、問いのかたちにうまく輪郭が沿うように一つの物に仕立てることだろう。しかし本は一冊では成り立たないものだとも思う。隣に並ぶ本と合わせて読んだりすることで、一冊の背景や文脈をも読み解くことができたりする。それらが連なって、「本を読む」ことの楽しさにつながればうれしい。
書店員だった営業部長によると、「他の棚にうまくはまらなかった本が人文書棚に流れてくる」らしい。前回の藤枝さんの「何でも受け止める大きな器」ともちかい。実は「人文」というジャンルは海外にはなく、いろいろなものが流れつく島国特有の分野かもしれないと思うと、それもなんだか「空き地」っぽい。編集に携わった本が書物の森の一部となり、誰かの「必要なもの」になることを、僭越ながらも祈っている。
このエッセイのバトンを回してくれた藤枝さんは、同い年ながらも先陣をいく先輩だと思っており、時折電話やLINEで助けを求めている(ありがとう)。つくられる書籍にはどれも考え抜かれた熱がこもっていて、いつも姿勢が正される。
次のバトンを渡す編集者は、何人もお顔が浮かんだができるだけ遠くへと思い、みすず書房の鈴木英果さんに。直接お会いしたことのない大先輩(と言うのもおこがましいほど)だが、岡野八代『フェミニズムの政治学』やカロリン・エムケ『憎しみに抗って』(浅井晶子訳)、上野千鶴子『アンチ・アンチエイジングの思想』などを次々に編集されており、かねてからぜひお話をおうかがいしたいと思っていた。