「責任を引き受ける」とは、どういうことか――小さな哲学的考察(前編)
記事:春秋社
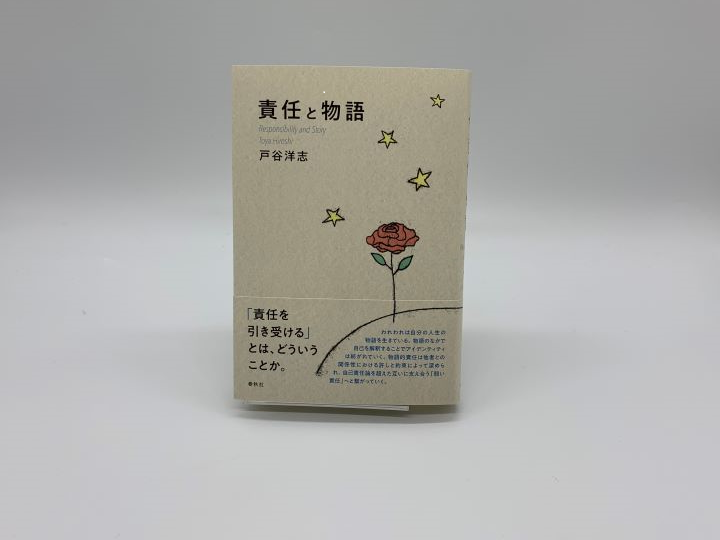
記事:春秋社
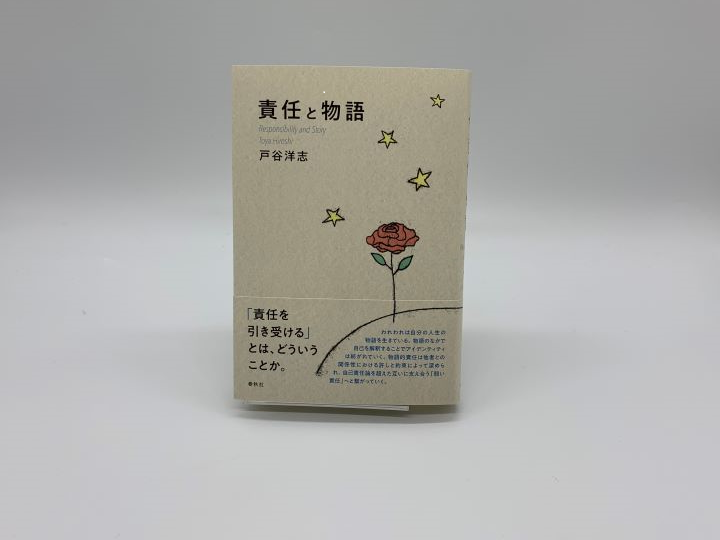
何気ない一言が他者を傷つけることはどんな人にでもある。他者と関わることで、誰も傷つけないでいることなど、不可能だ。それは誰にも避けられないことである。しかし、そうした出来事を「引き受ける」か否かは、自分で選択できる。「私」の何気ない一言が他者を傷つけたとき、「私の発言が他者を不当に傷つけた」と認めるのか、それとも、「私は本当のことを言ったのであって、それは不当ではない」とか「他者は私を誤解しているのであって、私は他者を傷つけていない」などと理由を立て、その出来事が自分の行為の帰結であることを認めないかは、「私」の意志にかかっている。それでは、この意味において責任を引き受けることは、どのようにして可能になるのだろうか。そうした問題について、近現代の哲学者の思索とともに、考えてみたい。
人間はどのようにして責任を引き受けるのだろうか。それは、見方を変えるなら、自分の行為をどのように理解するのか、自分が何をしたと見なすのか、という行為論の問題である。伝統的な哲学の議論において、「私」の行為の意味を決定づけるうえで重要だとされるのは、自由意志という概念である。そしてそのもっとも典型的な発想を提示しているのは、紛れもなく、近代の哲学者ルネ・デカルトである。
デカルトは次のように考えた。「私」が自由に行為をしていると言えるのは、どのようなときだろうか。それは、「私」にその行為をしないこともできたにもかかわらず、あえて、その行為を選択したときだ。たとえば「私」が他者を殴ったとしよう。その行為が自由な意志に基づいていると言えるのは、「私」が実際に他者を殴る前に、殴らないこともできるときである。その場合に「私」は、相手を殴るか殴らないかの選択肢を想定し、そのうちの一つを選択して、相手を殴ったことになる。このとき「私」は何かに強制されて他者を殴っているわけではない。「私」が他者を殴っている原因は、「私」がそう意志したという事実以外にない。だからその行為は自由意志に基づいている。
こうしたデカルトの発想は、現代では、自由意志の他行為可能性モデルと呼ばれている。つまり、ある行為が自由意志に基づいたものであるための根拠は、「私」にその他の行為の可能性が開かれているときである、という考え方だ。この発想に従うなら、「私が他者を殴った」ということは、それが「私」の自由意志に基づいている限り、受け入れざるをえないものになる。現代においても、日常的には十分に説得力のある考え方である。
しかし、他行為可能性ではうまく説明ができない問題もある。たとえば「私」が、自分とは肌の色が違う人に対して、「君はずいぶん色が黒いんだね」と言ったとする。それに対して、相手がショックを受け、「私」から差別を受けたと感じ、傷つく。このとき「私」は、自分の行為をどのように理解するべきだろうか。「私は他者を不当に傷つけた」と考えるべきだろうか。それとも、「私は本当のことを言っただけであって、それは不当ではない」とか、「他者は私を誤解しているのであって、私は他者を傷つけていない」などと考えてもよいのだろうか。
自由意志の他行為可能性モデルは、この問題に対して有益な解決策を提示してくれない。なぜなら、「私」が「君はずいぶん色が黒いんだね」と言うことが、どんな行為として理解されるべきかは、その発言が自由意志に基づいていたか否か、ということからは、導き出すことはできないからだ。このとき「私」は、自分の行為を理解するための指針を、別のところに求めなければならなくなる。
ではその指針とはいったい何だろうか。結論から言えば、そうした確固たる指針は存在しない。なぜなら、ある行為がどのような意味を持つものとして理解されるのかは、その行為が置かれた文脈によって、まったく違ったものになるからだ。
こうした問題を考えるときに、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの言語哲学は一つの手がかりになる。彼は、言語を何らかの対象を指示するものとしてではなく、その言語が語られる文脈に依存するとして捉えた。同じ言葉であっても、それがどのような文脈で語られるかによって、その意味はまったく違ったものになりうる。それはあたかも、同じようにボールを蹴るという行為が、サッカーとバスケットボールとではまったく違った意味を持つことになる、ということと同じだ。彼はこうした言語の営みを、言語ゲームと呼んだ。
言語ゲーム論に基づいて考えるなら、「私」が自分の行為をどう理解するのか、ということは、結局のところ自分がその行為をどのような観点から眺めるのか、ということによって左右される。そして、そのうえ、どのような観点から眺めるべきか、ということを義務付ける規範などは存在しない。そうであるとしたら、私たちはどんなに他者を傷つけたとしても、その行為を引き受けることから逃れ、いくらでも自己を正当化することができてしまう。
こうした無責任な居直りに抵抗するのは、どのような道があるのだろうか。