「Xジェンダー」や「ノンバイナリー」はどのように用いられてきたのか?――武内今日子『非二元的な性を生きる』
記事:明石書店
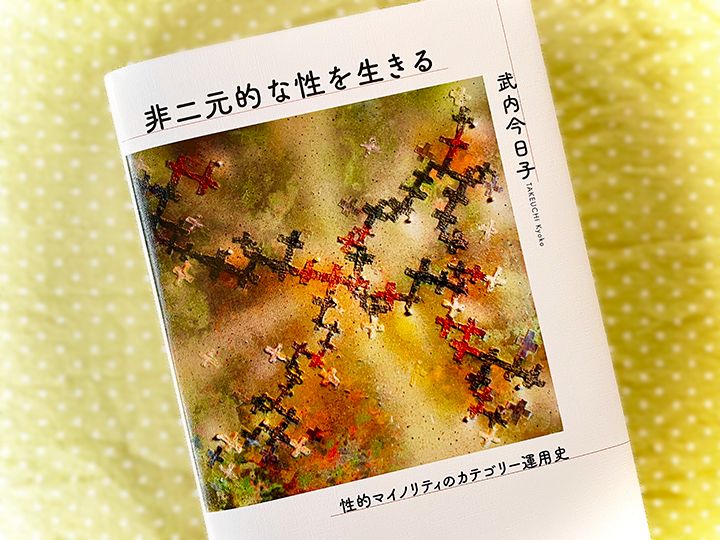
記事:明石書店
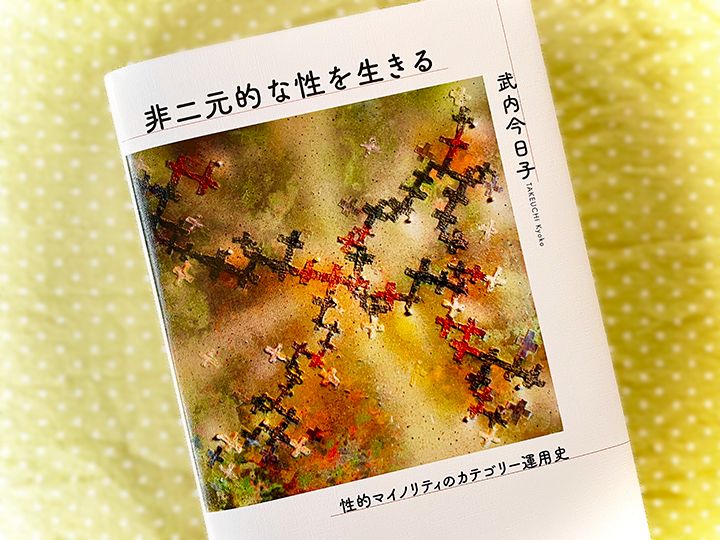
本書は、「男」「女」に当てはまらない非二元的な性を表すカテゴリーが、いかにして用いられ、性の理解や自己知をめぐるいかなる実践を人びとに可能にしてきたのかを明らかにするものである。そのために、1990年代以降の日本において非二元的な性のカテゴリーがいかに用いられてきたのか、そして現在自明視されている諸カテゴリーが人びとにいかなる可能性や限界をもたらしてきたのかを描き出すことをめざす。
「LGBTQ」が大衆メディアで大きく取り上げられる近年、「トランスジェンダー」、「Xジェンダー」、「ノンバイナリー」など、ジェンダー・モダリティ(出生時に割り当てられた性と性自認との関係のありようを表す概念)や性自認が非規範的である人びとを表すさまざまなカテゴリーが可視化されている。さらに、トランスジェンダーやXジェンダー、ノンバイナリーの人びとに関する解説書が出され、非二元的な性のアイデンティティをもつ人びとの生きづらさの所在やその乗り越えの方途を探ろうとする研究も蓄積されてきた。
こうした人びとの経験において、十分に描かれてこなかったが重要な側面として、「トランスジェンダー」や「Xジェンダー」、「ノンバイナリー」といった性のあり方を表すカテゴリーが人びとに何を可能にしてきたかという問いがある。これらのカテゴリーは現在、メディア等を通じて社会に浸透しつつあり、カテゴリーのもとでようやく自らの性のあり方をうまく表せるようになったという語りがある一方で、カテゴリーが個々人の性を表しきれないという語り、カテゴリーに自己を位置づけられないという語りも多くみられる。それでも、さまざまなカテゴリーが多くの人びとの実践が関わり合って生み出され、用いられてきたことは、当たり前のことではない。I. ハッキングが述べるように、新たなカテゴリーを知ることは新たな経験解釈の可能性をもたらし、時に人びとがさらに別のカテゴリーをつくり出していくことにつながってきた。
そこで本書は、「トランスジェンダーの人びと」「Xジェンダーの人びと」といったカテゴリー集団を自明視せずに、性のカテゴリーが人びとに用いられている仕方、すなわちカテゴリーの運用を考察の対象としている。とりわけ本書が焦点を当てるのは、「オーバージェンダー」や「Xジェンダー」、「ノンバイナリー」といった男女のいずれかには当てはまらない非二元的な性のカテゴリーである。これには、先行研究において二元的な性自認をもつトランスジェンダーの人びとについて主に検討されてきたという理由もある。ただそれだけでなく、非二元的な性のカテゴリー運用をめぐるさまざまな実践を見ていくことは、翻って「トランスジェンダー」や「性同一性障害」など、日本社会に先行して浸透していった諸カテゴリーがどのような影響を人びとにもたらしたのかを映し出すことにつながると考えている。こうした他のカテゴリーとの関係のもとで、さまざまな非二元的な性のカテゴリーが特定の時期や場においていかに意味づけられ、何を人びとに可能にしてきたのかを、本書を通じて明らかにしていきたい。
本書が依拠するのは、29人におこなったインタビュー・データや、ミニコミ誌等の文献の分析である。振り返ると、私が「Xジェンダー」を知ったのは2014年、学部2年生の頃だった。非二元的な性のカテゴリーの存在は、二元的な性の観念から距離をとり、自分の人生を別の仕方で振り返り、これからの生き方の新たな可能性を朧げにとらえるような経験をもたらした。その後多くの非二元的な性を生きる人びとに話を聞くうちに、時期や属していた場によって異なるXジェンダー観があること、「Xジェンダー」以外にも「オーバージェンダー」や「インタージェンダー」など非二元的な性を表すさまざまなカテゴリーが用いられてきたことを知り、さらに調査を進めていくようになった。本書の調査を支えたのは、自己を位置づける性のカテゴリーが揺らぎ続けてきた自分の経験を多少なりとも言語化し、先人たちの足どりをたどっていきたいという私自身の、そして自らの活動や人生の軌跡を遺そうとする調査協力者たちの、抜き差しならない想いでもある。
加えて、性の非二元的なカテゴリーの運用の変遷や、それにかかわる個々人やグループの活動、オフライン/オンラインでのネットワーキング、性的/恋愛的惹かれ、「性同一性障害」医療との距離感、性別欄などの制度への働きかけといった多様な要素を描き出すことは、現在に至るまで生じている、非二元的な性を生きる人びとの生が軽視される傾向に抗することも意味する。男女の二つの性別しかないという性別二元論が自明とされる社会において、非二元的な性を生きる人びとは数多くの障壁に直面し、信頼できる情報も得にくく、とかく生きづらい。「ノンバイナリー」が可視化されている現在も、非二元的な性は、しばしば一時的なブームや一過性のアイデンティティ、二元的なジェンダー役割からの「逃げ」として否定的にとらえられることがある。こうした状況においてこそ、非二元的な性を生きようとしてきた先人たちの入り組んだ足どりをつぶさにたどることが必要とされている。
(『非二元的な性を生きる――性的マイノリティのカテゴリー運用史』まえがきを一部変更のうえ掲載)