シリーズ30周年を迎える世界的人気映画の新たな魅力と隠されたテーマに迫る! ~『トイ・ストーリー講義』より~
記事:平凡社
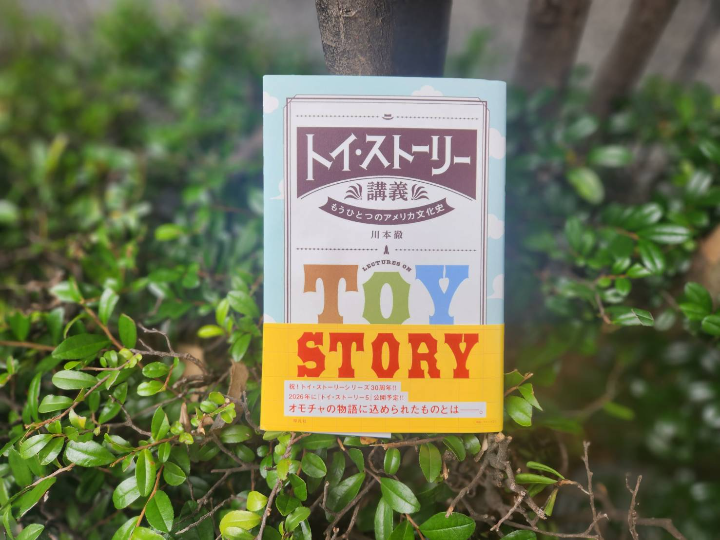
記事:平凡社
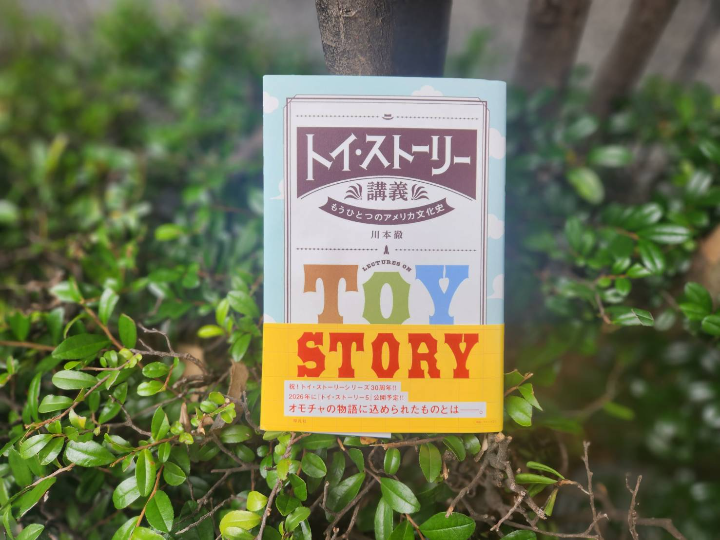
なぜ「トイ・ストーリー」の主人公は人間ではなく、オモチャなのでしょうか。キーワードは、CGアニメーションです。意外と知らない方もいますが、第1作『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーションです。現在では、多くの長編CGアニメーションが、世界中のスクリーンを賑わせています。そのすべての歴史のはじまりにあるのが、『トイ・ストーリー』です。
CGアニメーションは、いまでは実写顔負けのリアルな映像を表現できます。しかし、『トイ・ストーリー』の時点では、多くの限界を抱えていました。とくに、人間の髪や皮膚を描くことはたいへん苦手でした。ピクサーは『トイ・ストーリー』のまえに、「ティン・トイ」(1988)という短編を作っていますが、ここには人間の赤ん坊が登場します。しかし、この赤ん坊は、当時のCGアニメーションの限界ゆえに、不気味なことで知られています。紙オムツをはいているのですが、それもプラスチックに見えます。逆に言えば、当時のCGアニメーションはプラスチックを描くことは得意でした。そこで、おもにプラスチックでできたオモチャが主人公に選ばれたのでした。シリーズの第1作で、アンディのママの髪型がポニーテールなのも、そのほうが描くのが楽だからです。
その後、シリーズが作品を重ねるうちに、CGアニメーションは飛躍的に発展しました。
「トイ・ストーリー」の歴史をたどることは、CGアニメーションの歴史をたどることでもあります。
「トイ・ストーリー」には、アメリカについて、映画やアニメーションについて、さらには人生について考えるヒントがたくさんつまっています。ここで例として、主人公のウッディとバズのペアを考えてみましょう。ふたりはそれぞれ、カウボーイとスペース・レンジャー(宇宙警備隊)のオモチャです。なぜこのふたりがペアなのでしょうか。その背景はアメリカ史にあります。キーワードは、フロンティアです。19世紀、アメリカは大陸西部のフロンティア(未開の地)を開拓しました。この動きは19世紀末に終わります。しかし、20世紀以降、アメリカは空や宇宙を新たなフロンティアと見なし、開拓しました。宇宙はスペース・フロンティアとも呼ばれます。つまり、アメリカ人のなかで、西部開拓の歴史と、宇宙開発の歴史はつながっているのです。ウッディとバズは、一見違うタイプに見えて、ふたりともフロンティアのヒーローなのです。
ウッディとバズの持ち主はアンディという少年です。映画にはアンディの父が登場しないのですが、これはなぜでしょうか。劇中では理由は語られませんが、ひとつ言えるのは、父のかわりに、オモチャがアンディを見守っているということです。オモチャは子どもの「親」でもあるのです。シリーズでウッディの声を担当しているトム・ハンクスは、『トイ・ストーリー2』のあるシーンを見たときに、子どもとオモチャの物語に、自分の子どもの姿を重ねたと述べています。シリーズの生みの親であるジョン・ラセターは、『トイ・ストーリー3』の物語の根幹には、大学に行く息子を見送った自身の経験があると述べています。「トイ・ストーリー」は親としての大人の物語でもあります。
これにかぎらず、「トイ・ストーリー」は意外なほど大人の視点から作られています。
そしてそこには人生の大切なレッスンがあります。自分の平凡さを受け入れるとはどういうことか。いまこのときを生きるとはどういうことか。大切な誰かと別れるとはどういうことか。誰かのために生きるとはどういうことか。オモチャの物語に、こうした問いがあると聞くと、意外に思われるかもしれません。しかし、それこそが「トイ・ストーリー」の大きな魅力なのです。
ピクサーが手掛けた長編作品は「トイ・ストーリー」だけではありません。現時点での最新作は、アニメーションの歴代興行収入ランキングを塗り替えた『インサイド・ヘッド2』(2024)。ピクサーの長編としては、28番目の作品です。どの作品も詳しく論じるに値します(世界トップクラスのクリエイターたちが、毎回3年から6年をかけて作っているのがピクサー映画です)。本書では、各作品のあらましと「トイ・ストーリー」とのつながりを中心に論じることにしました。巷には、ピクサー映画の世界はすべてひとつの時間軸でつながっている、という説があります。その真偽のほどはさておき、ピクサーはその歴史のなかで、過去の作品のテーマや技法を少しずつ発展させてきました。各作品のつながりはたしかに強く、そこがわかると見方が大きく深まります。

その中心にあるのが「トイ・ストーリー」です。ピクサーがその歴史の節目節目に、このシリーズの続編を発表してきたことは、注目に値します。たとえて言えば、ディズニーがその歴史の節目節目に、『白雪姫』(1937年公開のディズニーの長編第1作)の続編を発表してきたようなものです。「トイ・ストーリー」を軸にすえて見なおすと、ピクサーの長編の歩みがとてもクリアになります。
(構成=平凡社編集部)
第Ⅰ部 最初の3部作
第1章 『トイ・ストーリー』—— 飛べないオモチャもすぐれたオモチャ
第2章 『トイ・ストーリー2』——ウッディの「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
第3章 ピクサーの軌跡①——『バグズ・ライフ』から『カールじいさんの空飛ぶ家』まで
第4章 『トイ・ストーリー3』——シリーズ最高のエンディングの理由
第Ⅱ部 その後の「トイ・ストーリー」とピクサー
第5章 ピクサーの軌跡②——『カーズ2』から『インクレディブル・ファミリー』まで
第6章 『トイ・ストーリー4』——過去作との別れと新たなる出発
第7章 ピクサーの軌跡③——『2分の1の魔法』から『インサイド・ヘッド2』まで
コラム
ディズニー? ピクサー?
「トイ・ストーリー」の英語
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の
エド・キャットマルと宇宙
ピクサーは照明がすごい
ラセター事件とその余波
「トイ・ストーリー」の短編
「トイ・ストーリー」から「バービー」へ