ヨーガはどこから来て、どこへ行くのか?(後編)
記事:春秋社
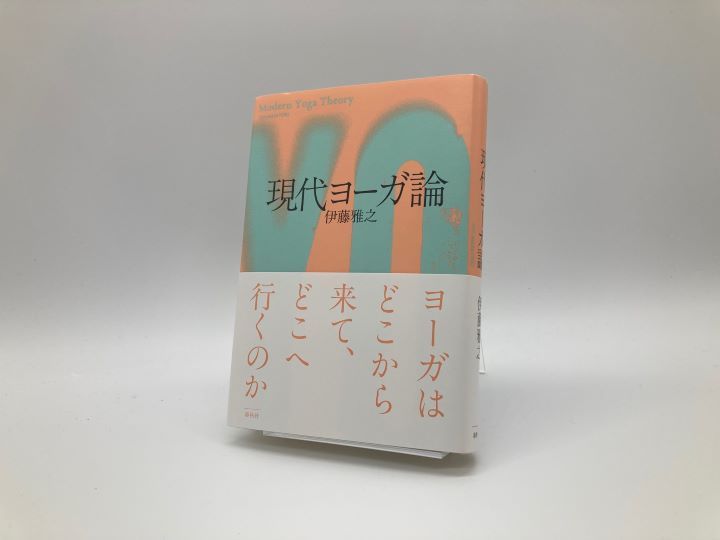
記事:春秋社
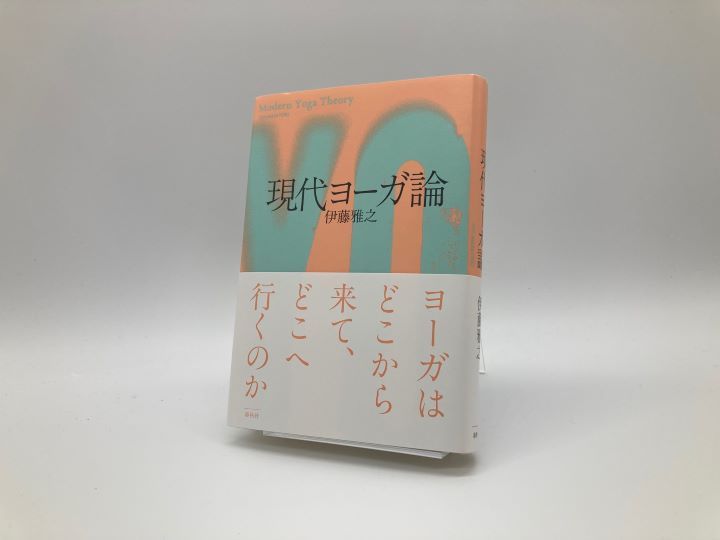
近現代に成立したヨーガ思想は、インド発の純粋な文化的産物ではない。むしろ、西洋の精神潮流や宗教運動との相互作用のなかで形成されたものである。たとえば19世紀末、ヴィヴェーカーナンダは、ヒンドゥー教復興運動の一環でヨーガを再定義した。彼は、従来の身体エネルギーの活性化に特化したハタ・ヨーガを排除しながら、欧米の知識人に親しまれていた神智学や超絶主義といった「スピリチュアルな自己探求」を重視するアメリカの思想とヨーガ哲学を重ね合わせ、新たな伝統を創造した。また20世紀初頭には、アメリカ人作家ヨーギ・ラマチャラカ(本名ウィリアム・アトキンソン)は、ポジティブ思考と精神の力による癒しを説くアメリカの思想運動であるニューソートの影響のもと、それを「ヨーガ」として紹介し、その普及に貢献した。こうして19~20世紀を通じ、インドの改革者と欧米の思想家たちが交流するなかで、ヨーガは国境を越えて発展し、さまざまな宗教・哲学的潮流を取り込みながら独自の形を築いていった。
現代ヨーガでは、精神面だけでなく、身体面でも西洋から多大な影響を受けている。20世紀初頭の国際的な身体文化運動(スウェーデン体操や武術、ダンス、ボディビルディングなど)が組み合わさり、現代ヨーガの身体技法が形成された。たとえば、スウェーデン体操はヨーロッパでオリエンタル・ダンス(当時、西洋で東洋的な神秘性や異国情緒を表現する身体芸術として再構築された舞踊)へと発展し、それがやがて古来インドのヨーガ的身体実践として再解釈された。このような身体動作は、『バガヴァッド・ギーター』や『ヨーガ・スートラ』といった伝統経典の文脈に再配置されることで、スポーツや武術とは異なる独自の体系として定着していった。
20世紀後半から現代にかけて、ヨーガはフィットネスや健康志向と結びついて大衆化した。実践者の動機には身体的健康の向上だけでなく、ストレス軽減など心の健康維持、さらにはスピリチュアルな成長も含まれている。たとえば1970~80年代のフィットネスブームを背景に、90年代以降に急速に広まったアシュタンガ・ヴィンヤサ・ヨーガでは、アーサナ(ヨーガのポーズ)がそのままスピリチュアルな鍛錬と見なされた。こうした変遷を経て、現代ヨーガは心身の健康維持と精神的・スピリチュアルな探求とを一体化する包括的な実践体系へと変容していく。
現代ヨーガは、自己責任と自由市場を重視する新自由主義社会と深く結びついている。とりわけセルフケア産業の主要な商品として位置づけられるヨーガは、「健康とは自己管理である」という理念を強化する。その結果、社会的な不平等や貧困といった構造的問題が、自己責任に還元される危険がある。こうした傾向は、ヨーガの個人化と市場化を象徴するものである。
しかしながら、そのような消費社会の枠内にあっても、ヨーガ実践者たちは必ずしも新自由主義的な価値観に追随しているわけではない。むしろ代替医療やエコロジカルなライフスタイルの実践を通じて、支配的なイデオロギーに対する批判的な姿勢を示している側面もある。つまり、現代ヨーガは一方では個人主義と商品経済に取り込まれながらも、他方ではオルタナティブな価値観や実践の空間として機能している。
このような動向に拍車をかけたのが、2017年以降に世界的に広がった #MeToo 運動である。ヨーガ界においてもこの運動は大きな反響を呼び、たとえばパタビ・ジョイスやビクラム・チョードリーといったカリスマ的指導者による長年の性的虐待が次々と告発された。従来、ヨーガの世界ではグル(師)への無条件の服従を前提とする「系譜ヨーガ」が重視されてきたが、#MeToo運動を契機にその権威構造自体が問い直されるようになったのである。
宗教学者ワイルドクロフトは、この動向を「ポスト系譜ヨーガ」と呼び、古典的テキストやグルに対する権威主義的な依存を脱構築し、対話や多様性を基盤とした新たなヨーガ文化の台頭として位置づけている。このポスト系譜的な実践では、グル中心主義だけでなく、商業主義に対する批判も展開されており、身体・ジェンダー・エコロジーを横断する包括的なアプローチがとられている。
本書では、アメリカ、イギリス、インドを中心に、過去150年にわたる現代ヨーガの展開を考察してきた。ヨーガは一貫した教義体系をもつわけではなく、各時代・地域の社会文化的文脈に応じて、その姿や意味を柔軟に変化させてきた。ヨーガとは、時代や文脈によって意味を変える「柔軟な容器」であり、内実も常に変化し続けている。
19世紀末から20世紀前半にかけてのインドでは、植民地支配のもとで進められた近代化や国民形成の一環として、ヨーガが身体訓練法として再構成されていった。同時に、ヴィヴェーカーナンダに象徴されるような精神的・宗教的な探求としてのヨーガが、西洋へと伝播していった。この点も、現代ヨーガの成立において不可欠な要素である。その後、20世紀後半から21世紀にかけては、新自由主義的な個人主義や自己責任の論理のなかで、ヨーガはマインドフルネスと並んで心身のセルフケア手段として広く受容され、世界的な広がりを見せた。
しかしながら、こうした実践の普及に対しては、研究者や実践者のあいだで常に批判的な視点が提示されてきた。健康や幸福が個人の努力や選択の結果とされることで、社会的不平等や制度的格差といった構造的課題が見えにくくなるという懸念からである。
ヨーガという柔軟性に富んだ「容器」は、これからも社会の変化に応じて形を変えながら、新たな意味や価値を担っていくことだろう。時には既存の規範や制度に異議を唱え、時には個人の癒しや連帯の実践として、多様な物語を紡ぎ出していく可能性を秘めている。今後、ヨーガがどのような方向へと展開していくのか、引き続き注視していくことにしたい。
(前編はこちら)