大学生活に「焦り」を感じたら ──濱中淳子著『大学でどう学ぶか』書評(評者:葛城浩一)
記事:筑摩書房
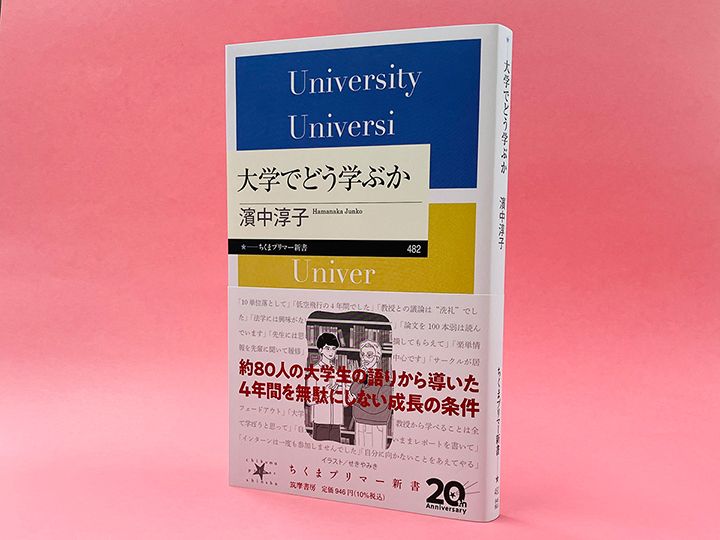
記事:筑摩書房
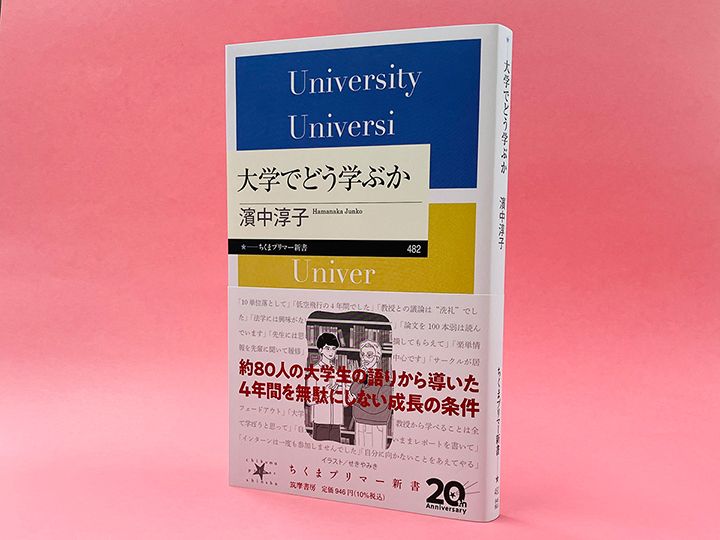
本書は、『大学でどう学ぶか』というタイトルからもわかるように、大学での学び方の指南書である。類書はこれまでもたびたび出版されており、たとえば、評者も学生時分に読んだ記憶のある、加藤諦三の『大学で何を学ぶか』(1979年、光文社)は、帯文に「不朽の名著」と銘打たれ2009年にベスト新書で再刊行されているし、新しいところでは、2020年に刊行された、上田紀行編『新・大学でなにを学ぶか』(岩波ジュニア新書)がある。このように、類書が多くあるという点では、本書は「既視感ありあり」のようにみえてしまうことから、本書を実際に手に取るか否かは、書店あるいは検索サイトでの「偶発的な出会い」に依るところが大きいかも知れない。しかし、本書を「偶発的な出会い」に委ねてしまうのはあまりにもったいない。本書には類書と決定的に異なる点があり、その点にこそ類書とは異なる大きな魅力があるので、この書評ではその魅力を二点に絞って紹介してみたい。
まず、第一の魅力は、著者が「大学教育」を専門とする研究者であるという点である。類書の著者がこのテーマで書籍を刊行できるのは、各専門分野で名を馳せた研究者だからであるが(すなわち、大学教育のことはよくご存じでも、それを専門としているわけではない)、本書の著者は、「大学教育」を専門とし活躍を続ける、まさに今、脂が乗っている中堅の高等教育研究者の一人である。著者はプロローグで、「シンプルでありながら本質を外していない、そして適宜学術的な理論や概念を用いながら明快なストーリーを提示する」(17頁)ことを、「かなり難易度の高い目標」(同上)ではあるが、と遠慮がちに掲げているが、本書では高等教育研究者の矜持をも感じさせる、類書とは大きく異なる「ストーリー」が見事に展開されており、その目標は文句なしに達成されているといってもよいだろう。
また、第二の魅力は、その「ストーリー」展開の核をなしているのが学生の語りであるという点である。類書では、教育を与える側の立場から論が展開されがちであるが、本書では、教育を受ける側の立場、すなわち学生の実態をふまえたうえで丁寧に論が展開されている。本書では、80人を超える学生へのインタビューより抽出された6人の学生の語りから、かれらがキャンパスで何を考え、どう過ごしているのかをリアルに感じ取ることができる。読み手のメインターゲットであろう大学進学を考えている中高生は、そうした語りを手がかりに、自身の大学での学びを具体的にイメージすることができ、だからこそ、著者が提示する、大学時代の学びを変える二つの「処方箋」(アウェイの世界に飛び込むこと、教員を活用すること)を実感をもって受け取ることができるように思われる。
このように、本書は類書にはない魅力を有しており、一読に値するものである。著者は、読み手のメインターゲットとして、大学進学を考えている中高生やその関係者を想定しており、すでに大学に通っている学生はそこまで想定していないように見受けられるが、個人的には、すでに大学に通っている、特に低学年次の学生にもぜひ読んでもらいたい。私が学生時分に感じていた「大学時代を有意義に過ごしたいがどうしたらよいかわからない」という焦りにも似た感覚をもつ学生は今も決して少なくないだろうが、その感覚は時間の経過とともに色褪せていく。その感覚が色褪せる前にぜひ本書を読み、奮起してもらいたいものである。
最後に、本書は「大学でどう学ぶか」という学生目線での問題関心に基づくものであるが、その問題関心に大学目線(「大学での学びはどうあるべきか」)で迫ったのが、著者を筆頭編者として昨年末に刊行されたばかりの『〈学ぶ学生〉の実像 ―― 大学教育の条件は何か』(勁草書房)である。本書ではエリート大学生の語りを中心に構成されているが、こちらは中堅大学生やノンエリート大学生、放送大学生など、多様な学生の語りで構成されている。本書を一読された後は、ぜひこちらにも手を伸ばしていただきたい。

プロローグ
第1章 6人の物語――それぞれの4年間
第2章 6人の物語を整理する
第3章 アウェイの世界に飛び込む――成長の条件【その一】
第4章 教員を活用する――成長の条件【その二】
第5章 学(校)歴の効果をどう読むか
エピローグ