「無知の時代」を生き抜くために
記事:明石書店
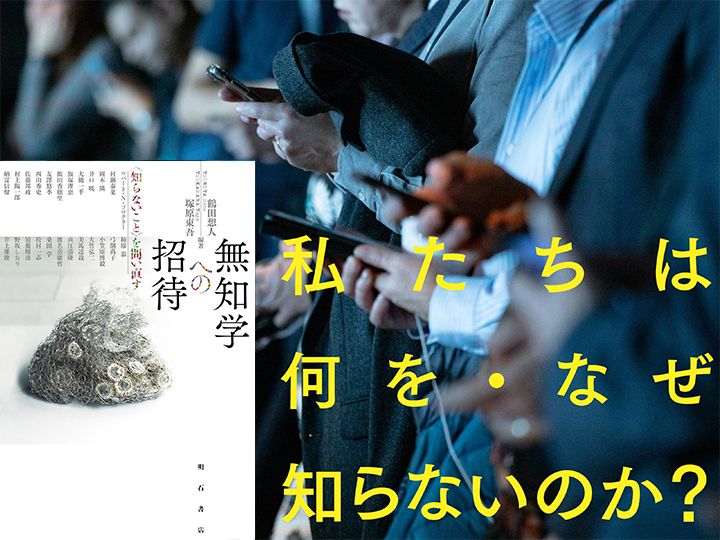
記事:明石書店
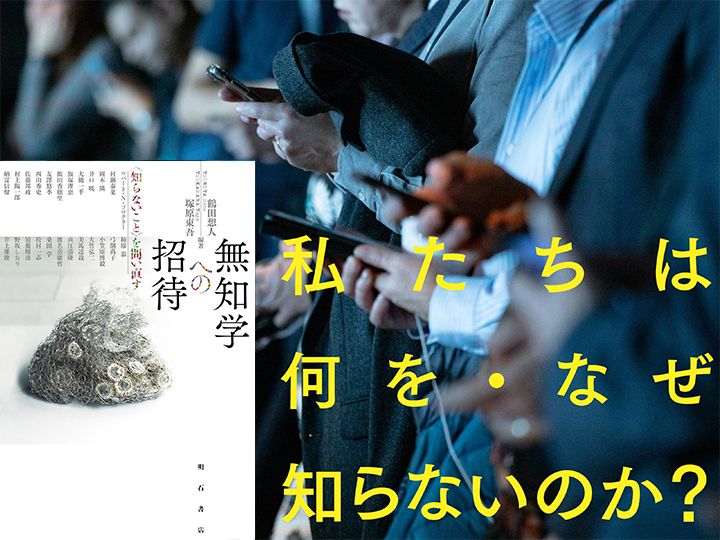
私たちはどのような時代を生きているのだろうか。戦争、気候変動、原発事故、パンデミック、フェイクニュースなど、私たちの時代を特徴づける事象はさまざまにある。しかしそれらの背後には、一つの巨大な力が蠢(うごめ)いているように思える。その力とは「無知」である。
例えばイスラエルは、パレスチナのガザ地区を物理的に攻撃しているだけではない。その攻撃を正当化するために、「無知」を積極的に利用してもいる。例えば岡真理によると、イスラエルは自国の行為が非難されると、それに対する「偽の対抗情報」を発信する(そこにはAIで生成されたフェイク画像も含まれる)。さらに、ガザの電力供給やインターネットを遮断することで、現地の惨状を発信できない状況を作り出す。こうして、私たちは何が真実かを知り得ないまま、イスラエルによるガザ侵攻の傍観者に仕立て上げられるのだ(『ガザとは何か』)。
しかし、この「情報戦」はイスラエルだけによるものではないと、岡は強調する。私たち自身の国のメディアも、さまざまな仕方でそれに加担しているのだ。沈黙(報道しないこと)による加担はもちろん、報道したとしても歴史的文脈を捨象することで、この問題の根源を見えにくくしている。「暴力の連鎖」、「憎しみの連鎖」といった言葉に回収したり、ハマースを単なる「テロ組織」として報じたりすることで、「どっちもどっち」の印象を作り出すことに手を貸している、と。それらは必ずしも悪意によるものではないだろう。しかし、そうして作られた私たちの「無知」や「無関心」、そして歴史の「忘却」こそが、このジェノサイドとその継続を可能にしているのだ。同じことは、ロシアとウクライナをめぐっても起きている。
現代は「ポストトゥルース」の時代と言われる。客観的事実よりも個人的な信念や好みの方が重視され、世論の形成にも力をもつ「真実以後」の時代である。この言葉は2016年のアメリカやイギリスの政治状況(トランプ氏の大統領選挙当選やイギリスのEU離脱)と結びついて登場し、瞬く間に時代を象徴するキーワードの一つとなった。ポストトゥルースはポピュリズムと相性がよい。SNSやAIの発達と普及により、フェイクニュースやフェイク画像などの生成と拡散がますます容易になり、それらが政治的に利用されて選挙や投票の結果を左右するまでになった。さらに気候変動否定論やワクチン懐疑論など、科学的合意(コンセンサス)を否定するような言説も拡散され、力をもつに至っている。いまや真実は、権力や人々の感情によって都合よく書き換えられるようなものになったのだ。
私たちは、近代科学の誕生あるいは啓蒙主義の時代以来、知識の時代を生きてきたと信じている。近代は「知は力なり」というベーコンの高らかな宣言とともに幕を開け、私たちの身の回りを科学技術の勝利の証で満たしているようにも見える。しかしいまや、ジョージ・オーウェルの描いた「1984年」のディストピア世界のように、無知こそが力を誇示している。私たちに知識をではなく無知を植え付けるために、情報が生産され、拡散され、操作されている。まさに無知が世界を回しているといっても過言ではないのだ。「私たちは無知の時代に生きている。どうしてこうなったのか、なぜそうなったのかを理解することは重要だ」(Proctor & Schiebinger, Agnotology, vii)。
本書はそのような「無知」について、学術的に探究する分野である無知学(アグノトロジー)の本邦初の入門書である。無知学は2008年にスタンフォード大学の科学史家ロバート・N・プロクターとロンダ・シービンガーの編著『無知学』によって提唱され、いまや学際的な研究領域に発展してきている。
『無知学』はプロクターらが当時所属していたペンシルヴェニア州立大学で2003年、次いでスタンフォード大学で2005年に開かれたワークショップに基づいており、「無知学」という語自体は早くも1992年にプロクターと言語学者イアン・ボウルによって考案されていた(当初はagnatologyと綴られていた)。さらにこの論文集以前にも、プロクターの1995年の著作『がんをつくる社会』やシービンガーの2004年の著作『植物と帝国』の中で、無知学の視点はすでに取り入れられていた。つまり無知学は、20世紀から21世紀への変わり目に登場してきた学問分野なのだと言える。
ここで本書のキーワードである「無知」について、あらかじめ補足しておきたい。無知学において「無知」とは、さまざまな状態を意味しうるアンブレラタームという性格が強い。それはまだ知らないこと(未知)や忘れてしまった状態、さらに疑念や不確実性なども含みうる。しかもそれらは必ずしも「悪い」ものとして指弾されるわけではない。本書の執筆者のあいだでも、「無知」はさまざまな意味で用いられている(さらに一人の著者が複数の意味でこの語を用いている場合や、「非知」や「不知」などの別の語を用いている場合もある)。本書では、それらをあえて統一することはしなかった。こうした定義のあいまいさは、無知学の課題でもある一方で、(当分のところは)強みでもありうると思われるからだ。どんな種類の無知があるかを探究することも無知学の目的の一つである以上、あらかじめ厳密に無知を定義することは、その探査の幅を狭めてしまうことにもなりうる。この点に関しては、今後哲学などの分野でより精緻な議論がなされることを期待したい。
無知を研究する人文・社会科学の分野は(狭義の)無知学以外にもある。無知学とほぼ並行して哲学や認識論の分野から現れたのが「無知の認識論」であった。2007年に人種とフェミニズムの哲学者シャノン・サリヴァンとナンシー・トゥアナの編著『人種と無知の認識論』が上梓され、この分野の輪郭が形作られた。また、無知の社会学あるいは「非知社会学」と呼ばれる潮流もある。ドイツ語圏でペーター・ヴェーリングら、英語圏ではリンジー・マゴイらによって率いられている分野である。
本書は『無知学への招待』と題されているが、狭義の無知学に限定せずに、無知の認識論や非知社会学を含む、無知研究の幅広い領域をカバーすることを企図している(それゆえ「無知研究への招待」と題してもよかったかもしれない)。とはいえ編者らの専門が科学史・科学論である以上、話題が狭義の無知学に偏ることは避けられなかった。今後、無知の認識論や非知社会学についても、日本へのより本格的な紹介が望まれる。
本書は欧米の無知学をある程度体系的に紹介するとともに、その日本への応用事例と、それにとどまらない無知という概念の広がりを示すことで、読者を無知学へと誘(いざな)うことを目的としている。無知学が読者の幅広い関心と結びつき、思わぬところから芽を出し、花を咲かせることを願っている。本書がその一助になれば幸いである。
(本書「はじめに」より抜粋、一部を修正)