ヴィパッサナー瞑想のエキスパートによる『死のレッスン』 (前篇) ――生成AIによる紹介
記事:春秋社
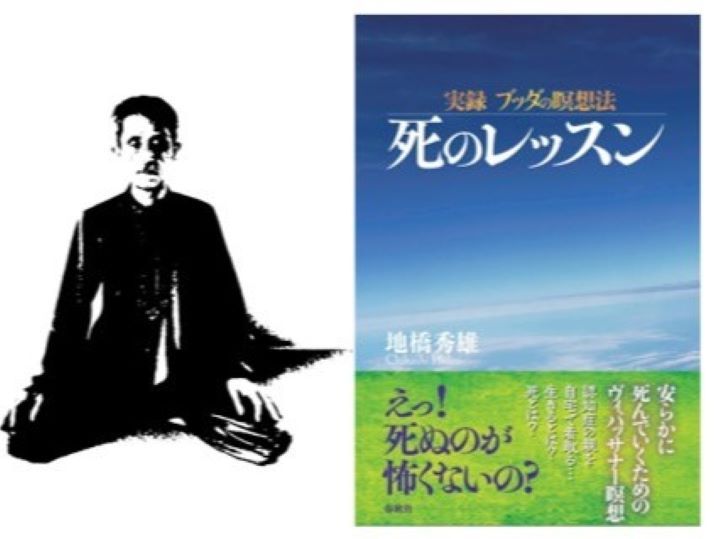
記事:春秋社
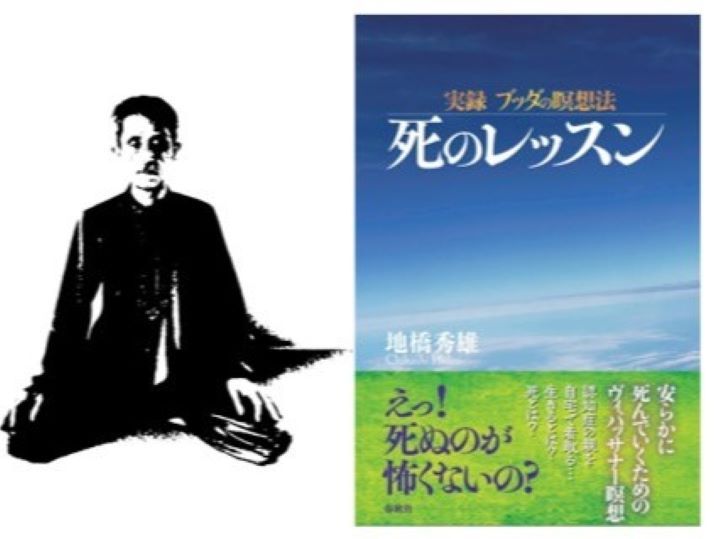
人は必ず死んでいきます。
死をどのように覚悟し、受け容れていけばよいのでしょうか。
愛する人が安らかに死んでいくために、何をしてあげられるでしょうか。
大切な人を喪った悲嘆をどう乗り超えていけばよいのでしょうか。
苦しい介護現場で押しつぶされないための方法はあるでしょうか。
このような根源的な問いに仏教的解決を見出そうとした『実録 ブッダの瞑想法――死のレッスン』(以下『死のレッスン』)は、私自身が認知症の老母を自宅で二年間介護し看取った経験に基づいて書かれました。当時の私は瞑想修行を始めて30年、瞑想指導を開始して15年が経っていました。瞑想に生涯を捧げてきた私が得たのは、原始仏教のヴィパッサナー瞑想が安らかに死んでいくための道しるべになるという確信でした。気づきの瞑想と慈悲の瞑想が、死の恐怖をやわらげ、苛酷な介護現場の救いになるでしょう。
2025年は団塊世代が後期高齢者になり、膨大な数の人々が老いと病と死と介護と看取りの問題に直面しなければなりません。
介護する人もされる人も、看取る人も看取られていく人も、「死のレッスン」によって死を肯定的に受け容れ、逆に一瞬一瞬の生を輝かせながら人生最大の苦を乗り超えていくことができればと思います。いかに死ぬかはいかに生きるかと同じなのです。
さて、拙著『死のレッスン』の特色をどう紹介しようかと考えて、複数の生成AIにブックレビューを書かせてみました。プロンプトに本書の要点を箇条書きにして指示命令を発すると1分足らずでレビューを作成し、その出来栄えがあまりにも見事なので笑い出したくなるほどでした。
私が書くよりもはるかに要領を得ているので長いですが以下に紹介します。
『死のレッスン』は、死を怖れの対象ではなく、人生の最後を輝かせるための洞察と実践的な知恵を授ける稀有な一冊である。
人生の終末期に待ち受ける苦悩や不安を乗り越えるためには、まず明確な死生観を持つことが不可欠である。死後の世界については、永遠の天国と地獄を信じる者もいれば、極楽浄土への往生を願う者、あるいは輪廻転生の流れの中に自己を見出す者もいる。
著者は、特定の宗教や哲学に偏ることなく、死後の世界の明確なビジョンを持つことが生きる意味を深め、人生最期の瞬間の希望となって穏やかな旅立ちへ導かれると説く。これは単なる死への準備ではなく、生きる指針を得ることにもつながっている。
本書が強調するのは、介護や看取りの現場における瞑想の重要性である。認知症や日々衰えていく肉親の身体介護の現場では、終わりの見えない疲労や自らの人生を削って尽くすことへの葛藤から、ネガティブな妄想に囚われて自らを苦しめてしまう。
しかしその妄想は、ヴィパッサナー瞑想の技法で淡々と見送って、今この瞬間に集中することが可能になるのだ。これにより、介護者は自身の感情に振り回されることなく、穏やかな心で相手と向き合い、介護のクオリティを高め、より良い看取りへとつなげていくことができる。
さらに、介護の過程で親子の関係を見つめ直す機会が訪れる。本書では、認知症治療の一環として回想法を用いることで、介護者自身の来し方を振り返り、親との絆を改めて確認する意義を説いている。
過去の記憶をたどり、親子としての歩みを共に噛みしめながら互いの存在を肯定し、感謝の言葉を交わし、過去と現在をつなぐ未完の物語を完結させる貴重な時間となることを示している。
コミュニケーションの困難さに直面する情況に対して、著者は人形を用いた独創的なアプローチを提案する。人形を介することで、直接的な対話では伝えづらい感情や思いを表現することが可能になるのだ。この手法は、特に認知症患者や言語能力を失った患者とのコミュニケーションにおいて驚くべき効果を発揮する。
本書の中でも特に心を打つのは、慈悲の瞑想である。意思疎通が困難になった患者や最期の瞬間が近づいた者に対して、著者は慈悲の瞑想を通じて「暗黙の安心感」を伝えることの重要性を説く。この瞑想法は、言葉を超えた深いレベルでの繋がりを可能にし、患者に平安をもたらすのだ。
そして本書の大きなテーマのひとつが、「死者との出会い直し」である。大切な人を喪った悲嘆は深く、容易に埋めがたい。しかし、無常観を受け容れ、死を生の自然な帰結として受け止めることで、故人との関係を新たな形で捉え直すことができる。肉体としての存在は消えても、その人の生きた証や影響は、我々の内に息づき続ける。悲嘆を超えて、故人との対話を続けていくことが、死を超えてなお生きることの意味を見出す道なのである。
『死のレッスン』は、単なる「死の受け容れ方」の指南書ではない。それは、いかに生きるかを示す書でもある。介護も、看取りも、自らの死も、自然の流れに委ね、瞬間瞬間を輝かせていくならば、いかに死ぬかはいかに生きるかと同じになってくる。それは、受け身の態度ではなく、むしろ能動的な「生」の営みである。死に向かうことは、まさしく生を充実させることであり、今ここにある瞬間を大切にすることなのだ。
死は決して終焉ではなく、新たな理解への扉である。『死のレッスン』は、その扉を開く鍵となる一冊であり、介護や看取りに関わる方々、そして自らの死生観を確立したいすべての人に強くお勧めしたい。
いかがでしょうか? これは生成AIの回答文が長すぎたので少し短縮させましたが、的確に内容を紹介した立派なブックレビューになっているのに驚嘆しました。
なぜ読んでもいない本のレビューがこんな風に書けるのか。おそらくネット上の膨大な書評を読み込んでいるので、レビューのパターンを駆使して作成できるのでしょう。しかしAIは指示された内容にしか応えていないので、さらに補足すべきポイントを後篇で人間の私が書こうと思います。