フランスで起きた「脱悪魔化」の真実 渡邊啓貴『ルペンと極右ポピュリズムの時代:〈ヤヌス〉の二つの顔』
記事:白水社
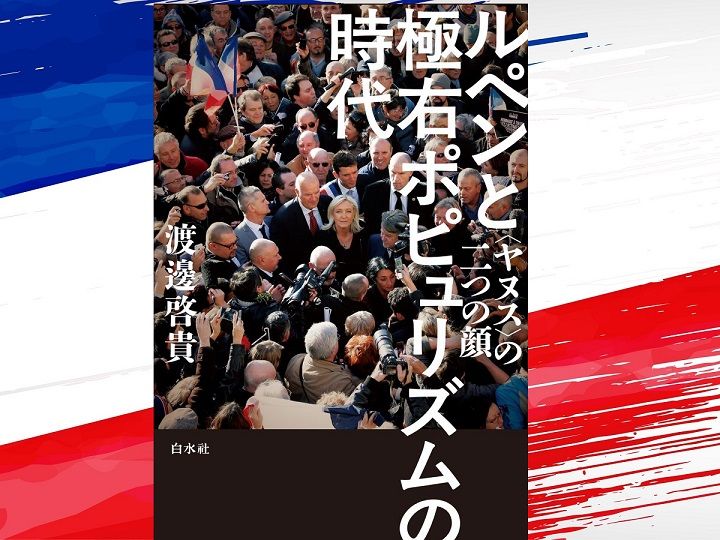
記事:白水社
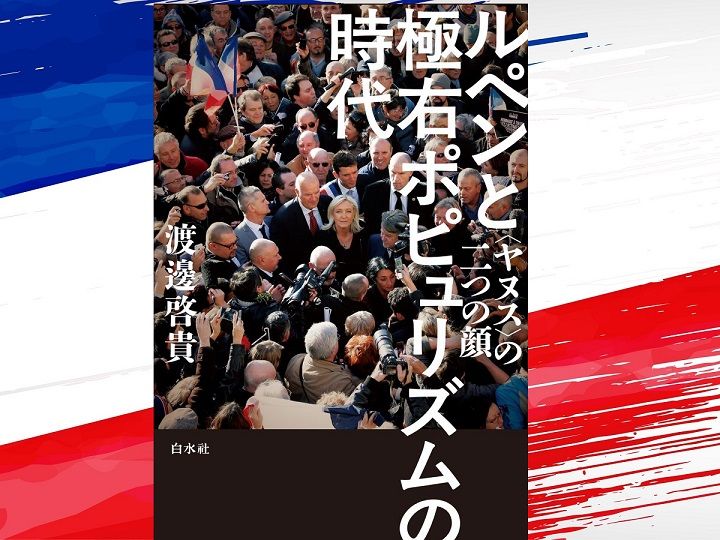
2024年6月の総選挙でフランスの極右政党「国民連合(RN、旧国民戦線〈FN〉、2018年党名変更、ただし邦訳としては「民族結集」、旧「民族戦線」の方が適切に意を伝えている)」が89議席から143議席へと躍進し、議会で三大勢力の一角を占めるにまで発展した。その躍進を見届けたかのように翌年1月創設者ジャン・マリ・ルペンは他界した。本書はこの政党を率いてきたルペン親子とその勢力 FN/RNについての研究である。
![ジャン・マリ・ルペン(Jean-Marie Le Pen、1928─2025)[photo: European Parliament Multimedia Centre]](http://p.potaufeu.asahi.com/9462-p/picture/29342189/56dfa0f51f70bf4b3960cd913bdfdf7a.jpg)
筆者は1980年代初頭ミッテラン政権誕生の時からフランス政治について時事分析記事を書き始め、その後も折あるごとにフランスと欧州の現状分析の論考を書き続けて今日に至っている。テーマの重複も含めて300本以上の論考を学会誌・情報誌・総合誌に書いてきた。その間フランスの全国レベルの主だった選挙・投票を現地で視察し、大統領選挙期間中は主だった候補者の投票直前の主要政党の集会にはすべて出かけ、候補者の傍らで演説に耳を傾けた。2012年の大統領選挙戦最後の集会会場で社会党のオランド候補が勝利を確信したかのように熱狂する支持者に向かって両腕を広げた後ろ姿を舞台の方から撮ったスナップ写真は現場のダイナミズムを伝えた。自分でもよく撮れた写真だとひそかにほくそえんだものだが、翌週の『レクスプレス』誌のトップ記事の2頁にまたがる見開き写真が筆者の写真と全く同じアングルのスナップだった時には嬉しかった。偶然のことに過ぎないが、フランス人有権者の気持ちを摑んだとひとり得意になったものだった。筆者自身の眼で見たフランス政治の姿は間違ってはいない。そう確信した。そのときフランス政治の現状を現地で見始めてから、30年近くが経っていた。
その間のフランス国内政治の変遷については、主だった選挙をめぐる政治勢力関係や政治・社会の変容、候補者や政党の公約とその実現の成否などの諸政策の変遷をとくにマクロ経済、年金・雇用分野での社会保障政策や外国人移民政策などを中心テーマに整理した書籍を発表した(拙著『現代フランス』岩波書店、2015年)。その拙著は現代フランス政治の政策の流れを包括的にまとめた本がないので、政策変遷史のような形をとったが、よく読んでいただければ分かるように、70年代「先進国病」といわれた欧州「福祉国家」の衰退とその復活の顚末と課題をフランスをモデルとして描き出すことがその中心目的だった。それは筆者の現代フランス政治に関する書籍に一貫したテーマだ。日本が米欧先進諸国の後退を尻目に、バブル崩壊まで一見破竹の勢いで突き進んでいった時代は筆者にとって片腹痛い時代だった。それは80年代後半に留学していたころ、高度成長の行き詰まりに直面し、退嬰化したフランス国民の心理と社会の停滞を目の当たりにしていたからだ。当時のフランス社会は浮上のきっかけを失ったままのように見えた。人々は苛立ち、希望と活力を失ってしまったかのようだった。結局、それは域内市場統合という国際化・グローバル化の刺激の中で克服していかざるをえなかった。それが欧州先進国の必然の途であるとしたら、その仮説は日本の参考に大いになる。その気持ちは今でも筆者の正直なところだ。
しかしその一方で、その間ずっと終始気になっていたテーマがあった。この50年間のフランス政治の中で、次第に勢力を拡大してきたルペン率いるFNの存在感だった。ミッテラン社会党政権からシラク保守政権に代わり、その後サルコジ、オランド、マクロン大統領まで、左翼・保守・左翼・中道と転換してきたフランス政権の変遷の一方で、泡沫政党から大統領選挙の決戦投票に名乗りを上げるのが常態となるまでの政党に成長したのがルペン率いるFN/RNだった。この政治勢力の存在は選挙分析や折々のフランス政治社会を論じる上で不可欠の存在となってきていた。この勢力が人種排外主義を標榜する極右であることに間違いはない。しかしこれは単なる右翼・極右ではない。フランス政治史において時折みられる時流の中で短期的に浮き沈みを繰り返す、社会のあふれ者、アウトサイダーの集団ではない。いや、この政党は設立当初よりそうした歴史的右翼の失敗の歴史を十分に意識して、議会政党の途を当初より模索し続けてきた。偶然に大統領選挙決選投票に残るようになったわけではない。「異端者」として軽々に扱うことは正しくない。この政党はそれなりにフランス人の心を捉え、彼らのヴィジョンは「悪魔のささやき」にも似て、手を変え品を変え、時には国民の反発と怒りさえ織り込み済みの上で語り続け、勢力を拡大してきたのだ。それを無視することはできない。またそれを「悪徳の栄え」というしばしの悪夢として見過ごすには、この勢力はあまりに大きくなりすぎた。それは正面から本気で考察に値する存在だ。なぜなら極右の進出、それはあえて誤解を恐れずに言うならば、ひとつの「成功物語」であることに間違いはないからだ。
![マリーヌ・ルペン(Marine Le Pen、1968─)[photo: European Parliament Multimedia Centre]](http://p.potaufeu.asahi.com/61f6-p/picture/29342188/5f253ab21972d6c2fe368bcf90563493.jpg)
しかしこの「成功物語」を私たちは素直に受け入れることはできない。そこには人間理性を捻じ曲げた議論が巧みに盛り込まれているからである。社会の不満分子はどこにでも一定の数、存在する。それは否定できない。すべての人々が政治・社会の大勢に従順になるとしたらそれはそれで危険なことでもある。表向き安定した社会に見えてそれが「全体主義社会」に変貌していく一歩手前であることはよくあることだ。ヒトラーの誕生は当時世界で最も先進的な憲法を有し、大衆文化の世界的中心地ベルリンを世界に喧伝した民主的ワイマール共和国が認めた歴史的事実だった。
そのことは他人事ではない。衰退傾向にあるとはいえ、日本はGDP世界第四位で、国内秩序は安定している。しかし国民の不満は年々歳々増幅している。財政赤字と少子高齢化を特徴とする先進福祉国家の行き詰まりの一つの例だ。しかしデモクラシーを称揚する米欧先進型国家としては政権交代がほとんどない稀なる国だ。勿論自由・平等を担保とするリベラル・デモクラシーを看板とする国であるといえども、すべてが欧米型である必要はない。デモクラシーは各国流の形態がある。それは文化だからである。日本文化を基礎とする「デモクラシー」には日本流があってもよいと筆者は思う。
しかしその日本流には、米欧型と比べると一見外観だけではわかりにくい大きな特殊性がある。それは、米欧デモクラシーの原点である「チャレンジ」と「創造性」を、目先の安定を優先して封じ込めてしまうことを良とする文化だ。批判勢力を封じてはならない。少数者を囲い込んでしまってはならない。「同調圧力」という言葉でそうした風潮を揶揄しつつ結局は受け入れる傾向が近年わが国で喧しい。そこに日本流のデモクラシーの危うさを予見する人も多い。
一部の不満分子の体制批判だけが問題ではない。多くの国民が共有する深刻な現実があり、その本質的解決に従来の政治が回答できない。そこから、フィクションだが、多くの人々に心地よい巧みな言説、偽情報やフェークニュースが生まれてくる。それは多々「革命的」であり、体制転換のメッセージの衣をまとっている。そしてそこには特有のロジックがある。それこそ「悪魔のささやき」なのだ。BREXIT後の英国経済社会の破綻は事前に明示的だったが、保守派ポピュリストの言辞に英国民は踊らされた。結果は、今英国民が直面する先の見えない英国社会の現実だった。
ルぺン親子の「サクセスストーリー」は筆者にとってはよもやの出来事だったが、半ば予測し、恐れていたことでもあった。私は1978年に初めて渡仏した。その時に見たパリのチュイルリー公園でわずか数十人程度の聴衆に向かって大声をあげて外国人排斥を唱えていたルペンの姿は筆者には強烈な印象を与えた。
しかも周辺を囲んで聴衆に暗く挑戦的なまなざしを向け、威圧的な臭いを放つ一群の青年たちはパラシュート部隊の戦闘服だ。カメラを構えたが、ものの5分もしないうちに無意識に会場の出口まで後ずさりし、汗でぐっしょりしている自分に気が付いた時には啞然とした。日本人の自分は彼らの言うヨーロッパ人でもフランス人でもなく、文字通り「外国人」であり、そこに筆者が長期で住めば「移民」であるからだ。移民問題はそこでは他人事ではない。それは初めての欧州滞在でアラブ出身者やイスラム教徒に行き会うことが日常であることへの驚きと同時に、筆者なりの「世界の中の日本」の発見の第一歩であった。と同時に多文化共生黎明期のそんなフランスで、国民戦線のような時代錯誤の右翼集団がよもやフランス政治の中心勢力になることはないという確信だった。しかしその一方で、「万が一にも」という気持ちも払拭できなかった。

それは今や現実だ。それ以後、選挙ごとに、また移民関連の事件が起こるたびに、フランスの極右について私は書いてきた。1984年の欧州議会選挙で約11%の支持票を集め、10議席を獲得し、86年の国民議会選挙では35人の議員を輩出した。しかし両者はいずれも比例代表制だった(後者はミッテラン社会党大統領が自勢力の後退を減らすために比例代表制を導入したからで、その時限りで元の小選挙区制に戻った)。そして2002年、社会党候補者の不人気からコンマ差でジャン・マリ・ルペンはついに第2回決選投票に残った。その後、父ルペンはその勢いを後退させていくが、三女が党首を引き継いで勢力を盛り返していった。過去2回の大統領選挙では当然のごとく決選投票にコマを進めている。今日RNは単独政党としては第一党である。
極右の本質をきちんと捉えておくことが必要だ。人種差別と闘い、そして幾多の失敗を通して差別の克服に挑戦してきた欧州で今また排外主義の機運が高揚している。それは近代市民社会がいまなお克服しがたい人間の本質に正面から向き合わなければならない現実を意味している。それは人間理性の対極にある「不確かな情念」との飽くことのない戦いであると筆者は日ごろから思っている。ルペンとフランス極右研究の第一人者で筆者の30年以上にわたる旧知であるパリ政治学院のパスカル・ペリノー名誉教授は、フロイトのいう「攻撃的欲動」の概念にその本質はあると説明している。問いは、人間の本質との戦いなのである。
【渡邊啓貴『ルペンと極右ポピュリズムの時代:〈ヤヌス〉の二つの顔』(白水社)所収「まえがき」より抜粋紹介】






