花と軍靴のはざまで――『カーネーション革命』が描くポルトガルの民主化
記事:明石書店
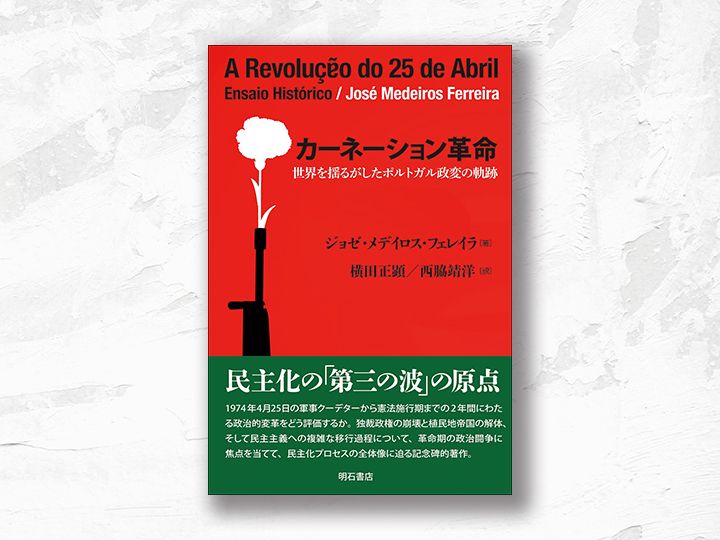
記事:明石書店
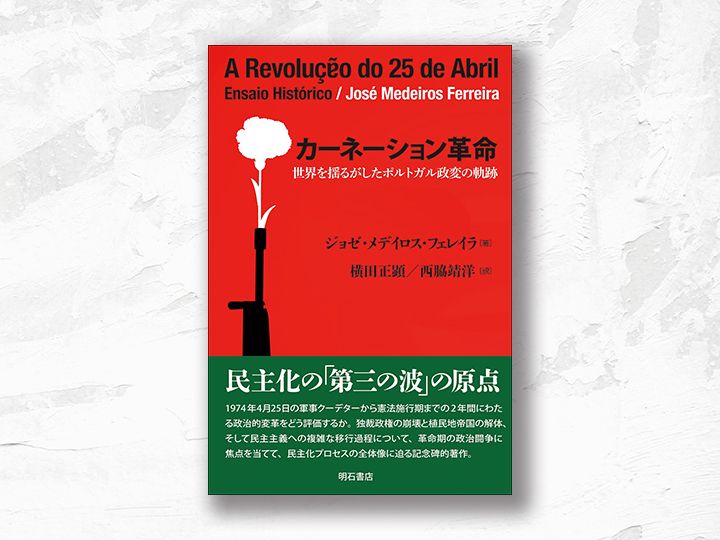
1974年4月25日、ポルトガルの首都リスボンで、半世紀にわたる独裁的統治の終焉と、13年に及ぶ植民地戦争の終結を同時に告げる政変が勃発した。この政変は、国軍運動(MFA, Movimento das Forças Armadas)を名乗る、中下級将校を中心とする軍事組織の無血クーデターにより始まった。この日、反乱に参加した将兵たちは銃口や軍服のポケットに赤いカーネーションを挿し、市民の喝采の中で自由の到来を共に喜んだ。のちに「カーネーション革命」と呼ばれるこの出来事は、暴力によらぬ平和的変革の象徴として、国際社会に驚きと希望をもって迎えられた。2024年以降、その50周年を祝って、ポルトガル政府の主導のもとにさまざまな記念事業が展開されている。
しかし、この出来事が現代日本において顧みられることはほとんどなく、2024年4月25日にこれを取り上げた主要メディアは皆無だった。筆者の見るところ、その背景には、ポルトガルという国に対する歴史的イメージの固定化がある。日本におけるポルトガルの印象は、多くの場合、16世紀の南蛮貿易にまで遡る「古き異国」としてのものにとどまり、現代ヨーロッパ政治の中でこの国が果たしてきた役割に光が当たることはほとんどない。かつて世界有数の海洋帝国として君臨したこの国は、今や国際政治の舞台で「小国」の地位に甘んじている。そのような「不可視性」が、ポルトガルの民主化の経験に対する日本側の無関心を助長しているのかも知れない。だからこそ、本書が提示する知見には、学ぶべき多くの示唆がある。
「カーネーション革命」という呼称が詩的で感傷的な響きを持つことは間違いない。だが、その背景と過程は政治的・社会的にきわめて複雑であった。実際、ポルトガルの人々はクーデターから1週間もたたないうちに混沌の渦に巻き込まれ、新たな政治秩序を模索して約2年にわたる彷徨を余儀なくされることになる。ジョゼ・メデイロス・フェレイラは、この革命を美化された物語としてではなく、体制移行の現実的な過程として丹念に描き出している。
カーネーション革命は、歴史の転換点として、少なくとも3つの国際的意義を担っていた。第1に、この革命は、スペインのフランコ体制と並んで西ヨーロッパにおける右翼権威主義体制の一角をなしていた「新国家(Estado Novo)」を崩壊させ、ポルトガルで両大戦間期以来続いてきた長期独裁の流れに終止符を打った。第2に、それはアフリカ領の独立をかけた解放戦争を終結させ、15世紀初頭のセウタ攻略以来、海洋帝国としての地位を築いてきたポルトガルの植民地支配の最終的崩壊を導いた。第3に、この革命は、サミュエル・P・ハンティントンのいう民主化の「第3の波」の起点として、世界各地における体制移行に深い影響を及ぼした。
「第3の波」とは、1970年代半ばから1990年代にかけて世界各地で起こった民主化の連鎖的な広がりを指す比較政治学上の概念であり、19世紀から両大戦間期にかけての「第1の波」、第2次大戦後の「第2の波」に続く、3度目の地球規模の民主主義の潮流を意味する。ハンティントンは、MFAのクーデターをその先陣を切る出来事として位置づけており、著書『第3の波』の冒頭で、カーネーション革命の経緯について紙幅を割いている。このように、カーネーション革命はポルトガル国内の改革にとどまらず、国際秩序の変動にも貢献した画期的な出来事であった。
もっとも、カーネーション革命前年の1973年には、南米チリの首都サンティアゴで起きた軍事クーデターによってアジェンデ政権が崩壊し、ピノチェトの軍事独裁が成立したばかりであった。これに対してMFAの決起によって始まったカーネーション革命は、独裁体制の一掃を実現したものの、その先に多元的議会制民主主義が築かれるかどうかは、少なくとも政変勃発の当初において予測不能であった。さらに、1974年5月以降、状況は急速に進展して、社会革命としての様相を帯びるようになる。そのような中でポルトガルがたどった体制移行の過程は、海図も羅針盤もないまま嵐の中を航行するような、不確実性に満ちた困難きわまる試みだった。
だからこそ、この2年間にわたる激動の時期は、世界史に残る稀有な政治的実験の記録として特筆に値するのである。
本書が示す中心的な視座は、革命を主導した主体が、半ば無名の中下級将校を中心とする軍由来の組織(MFA)であったという点に置かれている。メデイロス・フェレイラは、革命を政党や市民運動ではなく、軍内部から生じた自己改革の運動と捉える。すなわち、それは、植民地戦争で疲弊して混乱した軍が、軍制秩序の立て直しを初発の動機として、戦略的思考と政治的計算に基づきながら、多元的議会制民主主義の確立を志向する試みであった。だから、メデイロス・フェレイラは、MFAを単なる軍事組織の一部門ではなく、正規軍の一部が政治的役割を担うように変質した存在、すなわち軍の「政治的変異体」であると位置づけている。
メデイロス・フェレイラが強調するのは、革命がもたらした最も重要な成果が「制度的な体制移行の実現」であるという点である。カエタノ首相の辞意を受諾したのがアントニオ・デ・スピノラ将軍(移行期の初代大統領に就任する保守派軍人)であったことにより、MFAによるクーデターの果実はスピノラに「簒奪」されてしまった。しかし、スピノラが抱いていた保守的権威主義の路線や、旧植民地をポルトガル連邦に再編しようとする構想は、1974年9月の「声なき多数派」デモの失敗、さらには1975年3月のスピノラ自身が関与したクーデター未遂事件によって葬り去られた。
革命の急進化の過程では、ソ連型社会主義に移行するための共産党の計画化構想や、本土作戦司令部(COPCON)司令官オテロ・サライヴァ・デ・カルヴァリョ大佐から提起された「人民権力」構想が、MFAの進路に大きな影響を及ぼすことになる。1974年7月に発足した、ヴァスコ・ゴンサルヴェス将軍を首班とする第2次~第5次臨時政府は、共産党との関係を強化していった。しかし、MFA本体は、共産党とその系列の労働組合頂上組織インテルシンディカルが主張した労働組合運動の単一化の要求に積極的に応じることはなかった。その共産党と、1975年4月25日の制憲議会選挙で比較第1党となった社会党との間に熾烈な権力闘争が発生した。それは、同年夏にかけての革命派と反革命派の鋭い対立とも共鳴し合いながら、ポルトガル社会を内戦前夜の状況にまで追い詰めていった。
エルネスト・メロ・アントゥネス(当時中佐)を中心とするMFA穏健派は、こうした無秩序を回避するために権力集中を図りつつ、民主派諸政党との連携を深め、最終的に文民指導のもとでの民主体制を志向する道を歩んだ。共産党以外の政党は、カーネーション革命の前後に結成された未熟な存在であり、MFAとの関係を通じて政治的実力と存在感を増していった。スピノラ失脚後に大統領に就任したフランシスコ・ダ・コスタ・ゴメス参謀総長の調整的役割は、メデイロス・フェレイラによって高く評価されている。総じて彼の筆致は、ポルトガルの政治が最終的に多元的議会制民主主義へと橋渡しされたことを、MFAの戦略的判断の成果と見なし、ポルトガルの民主化に向けた重要な分岐点であったとする視点に基づいている。
本書においてメデイロス・フェレイラは、革命のすべてが理想どおりに達成されたわけではないことを率直に認めている。そもそも市民社会に起源を有する運動や組織が脆弱であったのは、半世紀にわたって政党活動の禁止やコーポラティズムによる国家的な利益統制が続けられてきたことの副作用であった。体制移行の主導権を軍が握ったことは、その論理的帰結である。労働者自主管理、土地・住宅の占拠、農地改革といった自然発生的な社会変革の動きの多くは、制度化に至ることなく終わり、あるいは民主的憲法のもとで巻き戻されていった。メデイロス・フェレイラは、当時のポルトガル政治の核心が、階級間の闘争ではなく、制度間のせめぎ合いであったと喝破している。しかし、それは決して社会変革への希求が敗北したことを意味するのではなく、可能な限り安定した政治秩序を築くための現実的な成果であり、未来へと続く「未完の革命」の一部なのであった。
メデイロス・フェレイラの解釈に異を唱える形で、1976年に民主的憲法が採択された後、EC加盟を視野に入れた新体制の整備の過程で革命の成果が徐々に清算されていったことを重く見る人々もいる。ポルトガルの欧州回帰と民主政治の相乗効果を寿ぐ見方に対して、逆に社会革命の失速を「失われた革命」あるいは「反革命」として否定的に評価する論調もここから生まれている。一方で、革命が一時的に急進化したからこそ、MFAや諸政党が単独ではなし得なかった民主化が実現したのだという指摘もある。また、MFAが全体として急進化の波に飲まれそうになったことの反作用として、諸政党とMFA穏健派との提携が生まれ、そのことが多元的議会制民主主義への着地を可能にしたとする見解も存在する。
本書の叙述は、1975年11月末の人民権力派のクーデターの鎮圧で実質的に終わっているが、MFAの影響は、民主的憲法が公布・発効されたあとも残存した。軍が揺籃期の民主政治の後見役として位置づけた革命評議会が廃止され、文民の国防大臣職が設けられたのは1982年であった。また、上記クーデターの鎮圧に功のあったラマリョ・エアネス(当時中佐)は、コスタ・ゴメスの後に大統領に就任した軍人大統領である。彼に代わって社会党の指導者マリオ・ソアレスが約半世紀ぶりに文民大統領に就任したのは、ようやく1986年のことであった。つまり、権威主義から民主主義への文字通りの体制移行が完結したのは本書の叙述の範囲外の出来事であり、政軍関係はこの段階では克服されるべき問題となっていた。
これらの多様な視点は、本書に対する批判としても提起されてきたが、それ自体がカーネーション革命に対する多面的な読解を促し、革命の意義と限界を問い直す契機となっている。カーネーション革命が「第3の波」の起点であったように、本書がカーネーション革命をめぐる生産的な議論の出発点としてポルトガル語圏の人々のあいだで長く読み継がれてきたことも、確かな事実である。
革命から半世紀を経た今日においても「4月25日」が「自由の日」であることに変わりはない。市民による記念行進、MFAのクーデター開始の合図に使われた革命歌「グランドラ・ヴィラ・モレーナ」の合唱、学校教育での継承など、多くの場面でこの革命はポルトガル社会の生きた記憶の中に織り込まれている。しかし同時に、その記憶は一様ではなくなりつつある。近年では、急進右翼政党「シェガ(CHEGA)」(ポルトガル語で「もうたくさん」の意)が急速に支持を伸ばし、現行の体制への批判的言説を強めている。
このことは、カーネーション革命の経験が空洞化し、人々の日常生活の中に埋没する一方、革命を知らない世代の反逆が表面化しつつあることを意味するのだろうか。必ずしもそうとは言えない。「4月の革命」の多様な側面が現代史研究を通じて客観的に明らかにされ、それらに対する評価が精緻に分岐していく中で、革命の意義がむしろ新たな地平において問い直されていることの表れなのである。
本書『カーネーション革命』は、この出来事を風化しつつある過去の逸話として閉じるのではなく、今なお私たちにさまざまな問いを投げかける「生きた経験」として描いている。花が銃口に差し込まれたあの日、軍靴の下に流血はなく、その平和の選択が、制度としての自由を可能にした。メデイロス・フェレイラの筆致は、理想と現実、熱狂と冷静、運動と制度のあいだを往復しながら、カーネーション革命を「未完」でありながらも希望を生み出すプロセスとして提示している。
本書のもう一つの大きな特色は、著者が単なる観察者ではなく、革命とその後の体制構築に実際に関与した「歴史の内部者」である点にある。スイス亡命からの帰国後、彼は体制移行期の政策決定に携わり、社会党系の政治家としても重要な役割を果たした。本書の主張の根幹的部分は、現在のポルトガル社会党の革命観とほぼ一致しており、社会党政権のもとで閣議決定された革命50周年記念事業実行委員会の基本思想に明らかに影響を与えている。しかし、それにもかかわらず、メデイロス・フェレイラは、自らの潜在的な政治的敵対者の言動にも公平な評価を下し、学術的距離感を保ちながら構造を見極める冷静な視座をもって叙述を進めている。それが本書に独特の説得力と緊張感を与えている。
加えて特筆すべきは、メデイロス・フェレイラの分析が理念や情熱に流されることなく、制度の成立条件と権力構造の変遷に焦点を当てている点である。彼は「物語」や「記憶」ではなく、政治秩序の持続性と正統性に主眼を置き、革命という非連続的な出来事をいかに制度的連続性へとつなげるかという課題に正面から取り組んでいる。その意味において本書は、ポルトガル現代政治の成立を理解するための実証的かつ知的な案内書であると言えるだろう。
暴力を用いずに軍が体制変革を実現し、市民と制度が緊張と協働を経て民主主義を築いた経験は、日本社会において「民主主義とは何か」「民主的制度はいかにして生まれるのか」という根本的な問いを投げかけてくる。また、現在も革命の記憶と向き合い続けるポルトガルの人々の姿は、過去の出来事をいかに語り継ぐかという問いにおいても、貴重な示唆を与えてくれる。
革命は終わっていない。それは今もなお、ポルトガルの政治と社会を照らし続ける灯であり続けている。しかし、そのカーネーション革命から50年を経た今日、世界各地で民主主義の後退や劣化、そして権威主義の広がりに警鐘が鳴らされている。民主主義を生み出し、持続させること――気の遠くなる営みを前にして、誰もが立ち尽くす。それでも「希望は欺かない」(spes non confundit ― ローマ書5章5節)と信じて、人は前へと進むことができるだろうか。1974年4月25日とそれに続く出来事は、希望への扉を開く鍵として、過去と未来を紡いできた。こうしてポルトガルの物語は、未来を考えるための手がかりとなる。本書を読む意義は、今を生きる私たちの手の中に、静かに差し出されている。