〈戦後80年〉米国は占領下の沖縄でどのように言論を統制したか
記事:明石書店
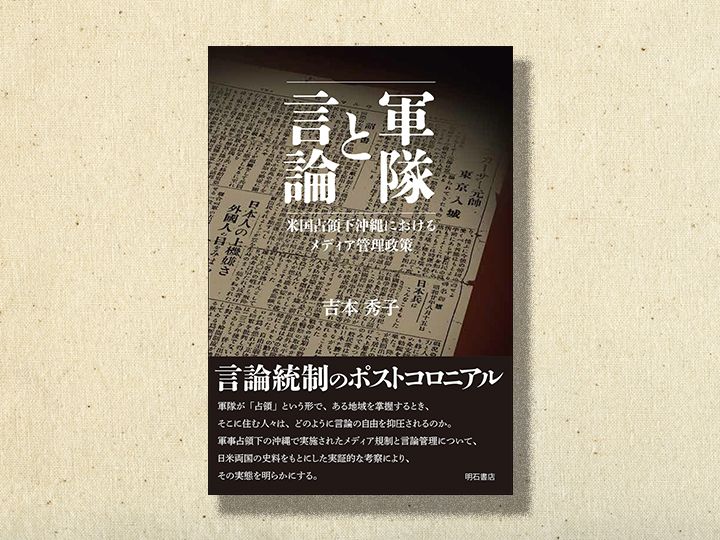
記事:明石書店
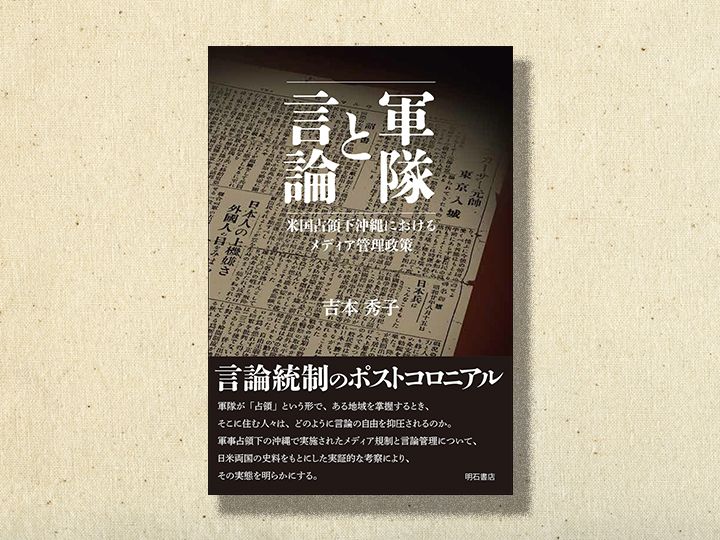
第二次世界大戦の終結から今年で80年です。大戦最後の地上戦となった沖縄戦からも、80年の時間が流れました。戦争を実体験として語れる人も少なくなり、あの戦争をどのように語り継いでいくか、が課題になっています。一方、今も沖縄には米軍基地があり、米兵の犯罪が、周辺の住民と様々な軋轢を引き起こしている現状があります。沖縄だけでなく、本土でも米兵の犯罪が日本の裁判所で裁かれないなど、この国は本当に独立国なのか、という疑念を抱かせるような事態も起こっています。その意味では、今もなお、戦後がどこまでも続いていると言えるでしょう。
そもそも沖縄の米軍基地は、今から80年前の1945年4月1日、沖縄本島に上陸した米軍が、沖縄戦を戦いながら、急ピッチで建設したものでした。なぜ戦闘と同時進行だったのかと言えば、米国は、沖縄の基地を対日戦争の拠点として使う計画だったからです。その頃、米国にとって、日本は容易に降伏しそうにない国に見えました。なぜかと言えば、国民が一丸となって天皇に忠誠を誓う、いわゆる皇国主義が社会全体に浸透していたからです。それは、行政・メディア・教育が一体となった、文字どおり、国家総動員の戦争でした。沖縄戦に至るまでの太平洋の島々で、米軍は日本軍の激しい抵抗にあい、本土決戦は厳しいものになるだろう、と予想していました。そして、米軍は、沖縄の人々も日本の皇国主義思想の影響下にあるとみていたので、沖縄の住民が、米軍が行う作戦の邪魔をするかもしれないと考え、軍人ではない民間人を収容所に入れて管理したのです。
1945年8月15日、日本本土の人々は昭和天皇の肉声によるラジオ・メッセージで、日本がポツダム宣言を受諾し、無条件降伏したことを知りました。戦後の日本では、毎年8月15日の「終戦記念日」が近づくと、テレビなどが「さきの大戦」に関する特集を組み、そのなかで繰り返し使われたのが、天皇が自ら国民に敗戦を告げる「玉音放送」の音声でした。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び……」という一節と独特の言い回しが印象的でした。ところが、同じ日、米軍が設置した民間人収容所にいた沖縄本島の人々は、ラジオから流れる天皇の声ではなく、米軍支援によるガリ版刷りのビラ『ウルマ新報』で、日本の敗戦を知りました。沖縄にはNHK沖縄放送局があり、地方新聞社がありました。しかし、沖縄戦で放送局も新聞社も破壊されてしまいました。そのため、少なくとも沖縄本島は「マス・メディア不在」の状態に陥っていたのです。そのなかで、日本が負けたことを沖縄の住民に伝えるために発行されたのが『ウルマ新報』です。
現在、私たちは新聞・ラジオ・テレビ・インターネットなどの多様なメディアを通して、「今、世界で何か起きているか」を毎日のように知ることができます。メディアは、今日が何月何日であるか、これからの天気がどうなるか、など様々な情報を提供してくれます。だから、多くの人は、「もしもメディアがなかったら……」などという状況を考えたこともないのではないでしょうか。東日本大震災では、行政の機能が一時的にマヒしたり、新聞社の社屋が被災したりする状況がありました。それでも、数日のうちに何とか通常の機能を取り戻し、行政とメディアは被災状況を住民に伝える使命を果たしています。しかし、激しい地上戦となった沖縄では、数ヶ月の間、行政とメディアが不在となる状況が続いたのでした。
実は、米軍上陸後、実弾が地上を飛び交うなかで、当時の沖縄の新聞社の人々は、首里城の下にあった地下壕に活字と印刷機を持ち込んで、5月下旬まで新聞発行を続けていました。しかし、読者に新聞を届けるルートは途絶え、地下壕の編集部は解散になります。行政も同じように地下壕に避難しましたが、その機能は失われていきました。そのようななかで、戦火に追われる人々は、毎日、生き延びることだけに必死で、今日が何月何日であったかなど、意識しなくなっていったことでしょう。
メディアがなければ、戦況についての情報も得られません。日本軍は勝っているのか、負けているのか。米軍は、どこまで迫ってきているのか。逃げ惑う人々には何もわからない。これこそが、地上戦の凄まじさを物語っています。英語の「ジャーナリズム」には、「日々を記録する」という意味があります。新聞などのメディアには、日常の出来事を「日付つき」で記録するという社会的役割があるのです。日付を伴うかたちで歴史を記録することは、現代メディアの重要な機能です。メディアが失われた世界では、個人の記憶のなかで日付が曖昧になってしまう、と言われています。人は、メディアで伝えられるニュースの日付と、自分自身の個人の記憶を無意識のうちに重ね合わせて、「あの日、あの時、私はこのような体験をした」と自分の過去を振り返るのです。
メディア研究者でもあった元・沖縄県知事の大田昌秀さん(故人)は、このように、「メディア不在」を経験した沖縄の復興が、本土の復興に比べて、大変困難なものであったと考えていました。彼は、次のように書きました。「日本の降伏が『玉音放送』というラジオによってみごとに収束されたという事実は(中略)、本土においてはなお放送が健在だったことを物語っている」。新聞は、日本が無条件降伏したことを住民に知らせる目的で再建されました。しかし、放送の空白期間は、これより長く続きました。自分たちのメディアを持たないことが、地域社会の復興に与える影響の大きさを、メディア研究者としての大田昌秀さんは身をもって実感していたように思われるのです。
戦争といえば、戦車や砲弾を用いた戦闘行為を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、戦争はそれだけでなく、戦場において情報発信の主権がどこにあるか、という側面も重要です。沖縄における地上戦は、このような「情報主権」を沖縄の人々から奪い去ったと言えるでしょう。もちろん日本軍も米軍も情報の重要性をよく理解していました。だから、米軍は沖縄戦を戦いながら、基地を建設しましたが、この建設作業には、通信基盤の整備も含まれていました。さらに、米軍が設置した民間人収容所では、沖縄の人々が日本軍と連絡をとることを警戒して、ラジオなどの通信機の所持が禁止されていました。
加えて、沖縄は1972年までの27年間、米国の施政権下にありました。米軍幹部は、沖縄の人々が日本に復帰したいと思っていることを十分に認識していたようです。でも、だからこそ、復帰運動を表面化させないために、住民を監視し、言論を管理しようとしたのです。沖縄戦で勝ち取った基地を自由に使うために、基地周辺の住民に対する沖縄管理政策を実施しました。言論の自由を標榜しているはずの国が、なぜ、人々の言論を統制しなければならなかったのでしょうか。それは、米国の軍隊が、独立を回復した日本という外国の地で、軍事的な自由を獲得するためでした。
本書は、米国の沖縄占領に関する史料に基づきながら、外国の軍隊が占領という形で、ある地域を掌握するとき、そこに住む人々は、どのように言論の自由を抑圧されるのか、を考えていきます。