「多文化共生」の行きづまりを打破するために――塩原良和『共生の思考法』
記事:明石書店
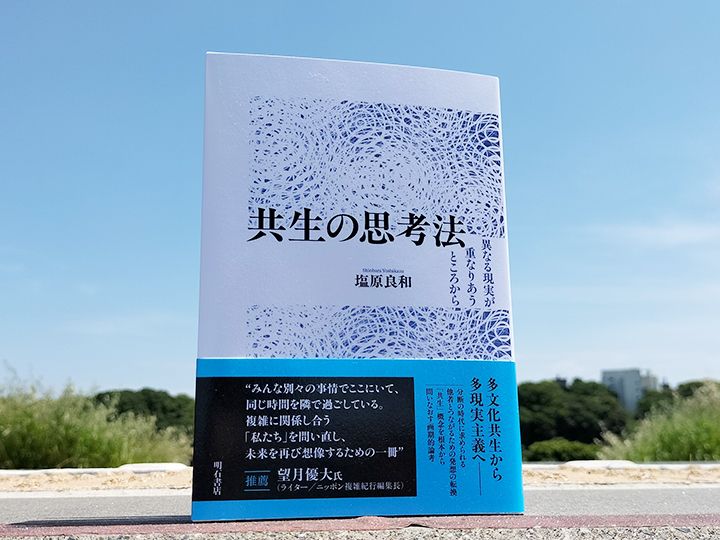
記事:明石書店
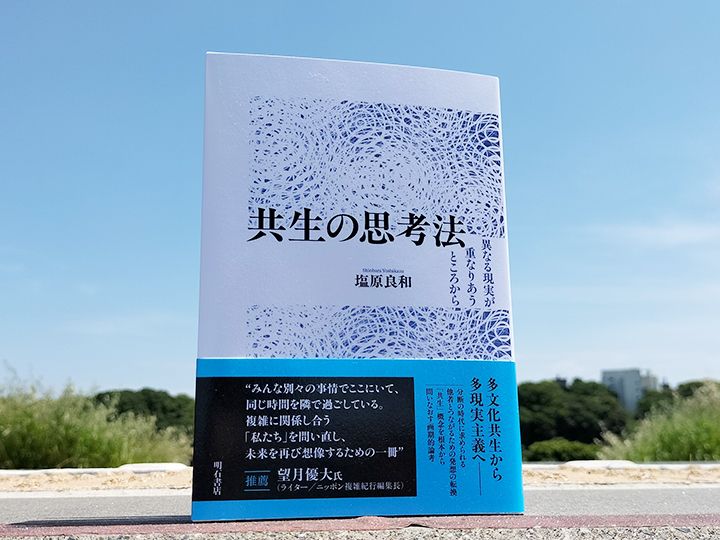
私が大学院で社会学を学びはじめた1990年代半ば、日本では外国人住民の人口が増加し、「多文化共生」を推進する必要性が研究者や支援者のあいだで広く認識されはじめていた(吉富 2008)。それから30年ほど経過した2024年現在、日本社会における事実上の移民としての外国人住民に関する実証的研究の成果は確かに蓄積してきた。では、「多文化共生の理論」はどうだろうか。大学院で私が学んだ規範概念や分析的フレームワークから、何らかの大きな刷新があったのだろうか。もちろん、30年前の理論をそのまま使うこと自体が悪いわけではない。しかしこの間、日本や世界のあり方や社会が直面している課題への認識が変わっているのであれば、多文化共生の理論もまた刷新しないわけにはいかないのではないか。本書は、日本における多文化共生をめぐる理論的視座につきまとう停滞感を払拭するための蟻の一穴を開けてみたいという、やや大それた動機から書かれている。
とはいえ、同業の研究者からの評価ばかり気にして本書を書いたわけでもない。これまで上梓してきた『共に生きる』(塩原 2012b)、『分断と対話の社会学』(塩原 2017b)と同じように、本書は私が慶應義塾大学法学部政治学科などで担当した講義(主に2018~2024年度)の内容をもとに、大学学部生を主な読者と想定して書かれている。現代世界の変動という大きな視座のなかで多文化主義/多文化共生をめぐる諸概念を再考することで、読者が現代社会における共生の現状とオルタナティブを考えるうえで有益な発想の転換、すなわち「共生の思考法」を提示することを目的としている。わかりやすい文章を心掛けつつも、単に既存の研究や理論を紹介する入門書を超えた、他の研究者の引用にも耐える論を世に問うことを目指したが、それに成功しているかどうかは読者の判断に委ねるほかはない。
第1章で述べるように、日本における多文化共生を分析する理論的フレームワークは、私が「リベラルな福祉多文化主義」と総括したものであり続けてきた。もっとも、日本の「多文化共生」を、英語圏における「多文化主義(multiculturalism)」の一類型とみなすことには異論もある(Shiobara 2020)。しかし本書でも検討されるように、「統合」「インターカルチュラリズム」(第2章参照)といった他の輸入された概念を適用して多文化共生を論じたとしても、それは大筋ではリベラルな福祉多文化主義の枠内に留まるものでしかない。まさにそれこそが、多文化共生の理論的考察に閉塞感をもたらしてきたのだ。本書の前半ではこの多文化共生の理論的限界を批判的に考察していく。第1章と第2章では、現代日本における多文化共生の政策や言説を批判的視座から分析し、論点を導きだす。それはマジョリティ国民としての「日本人」とエスニック・マイノリティとしての「外国人」を二項対立的に構築し、前者の優位性を隠蔽してきた同化主義としての多文化共生のあり方に他ならない。続く第3・4章では、この二項対立の前提となる「日本人」というカテゴリーの社会的構築のあり方について分析する。それをもとに、第5章で同化主義としての多文化共生の不可能性を検証し、その帰結として生じる、多文化共生のもつ排外主義としての側面を第6・7章で明らかにする。本書前半での考察をあらかじめ総括するならば、人々のあいだに社会化された所与の「価値観」が存在し、それによって維持されているマジョリティ中心の社会秩序がすでにあり、それをマイノリティが「共有」することで社会的「調和」が保たれる、という「symbiosisとしての共生」のイメージが暗黙の前提になっていることこそが、多文化共生を規範的・分析的・実践的に「生き/行きづまらせている」のである。
…中略…
そして本書の後半では、「symbiosisとしての共生」モデルに代わるオルタナティブな共生のための「発想の転換」が模索される。第8・9章ではまず「移動(mobility)」という概念に注目する。そして「定住」しているマジョリティの人々にとっての他者であるはずの「難民」「移民」が、実はマジョリティの人々自身の現実と重複し、つながっていることを論証する。これらの章で強調される発想の転換は、共生とは私たちがいまいる場所に留まって誰かを受け入れ、統合・同化させることではないということだ。そうではなく、共生とは私たち自身が、他者との境界線を越えてその先に進んでいく実践なのである。これを本書では、「共生の越境論的転回」と名づけている。
それに対して第10章以降で強調される発想の転換は、共生とはいまはまだ存在しない理想の状態ではなく、すでに私たちが(非―人間を含むさまざまな他者とのつながりのなかで)それを生きており、これからも生きていかざるを得ない「現にここに存在している」プロセスなのだということである。これを本書では「共生の存在論的転回」と呼んでいる。「内なる他者」の存在への気づきによって日本人/外国人の二分法的発想が無効化されうること、私たちがいますでに「他者の現実」を生きていることを認識したうえで、オルタナティブな共生の構想を存在論的に探求していく。そこでは「人間どうしの共生」のみを論じ、「人間と非―人間を含めたモノ・コトとの共生」というもうひとつのイシューを等閑視しがちであった従来の社会学的な共生観にも異議が申し立てられる。私たちが生きているこの「人新世」の時代では、従来「自然との共生」として語られてきた人間以外の生き物/モノ・コトと人間との関係性が危機に瀕しており、それを根本的に再考しなければ人間どうしの共生の前提条件も崩壊してしまう。多様な人々や物事が共生できる世界をどう構想し、それに向けて私たち自身をどのように変えていくのか。終章では、そのためのつながりを活性化する、広い意味での「政治」のあり方を模索する。
※本文中の強調の傍点は太字に置き換えました。漢数字の一部をアラビア数字に変更しています。
