子供、個人情報、身体は所有できるのか? 『人はなぜ物を欲しがるのか』が揺さぶる「所有」の概念
記事:白揚社
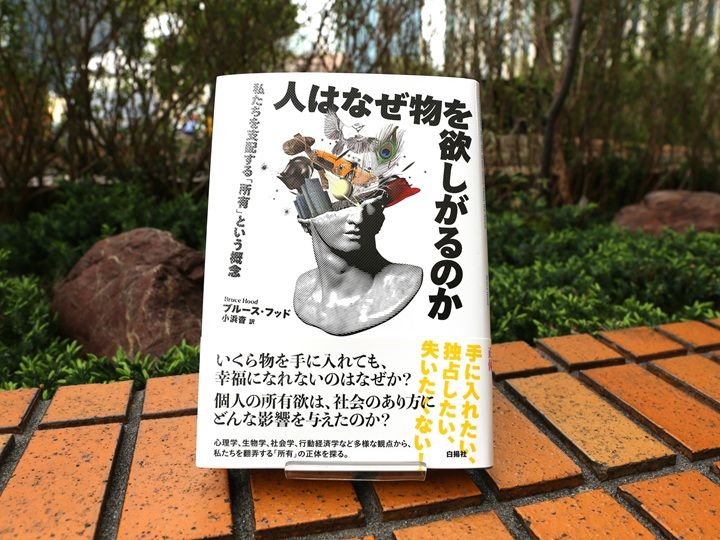
記事:白揚社
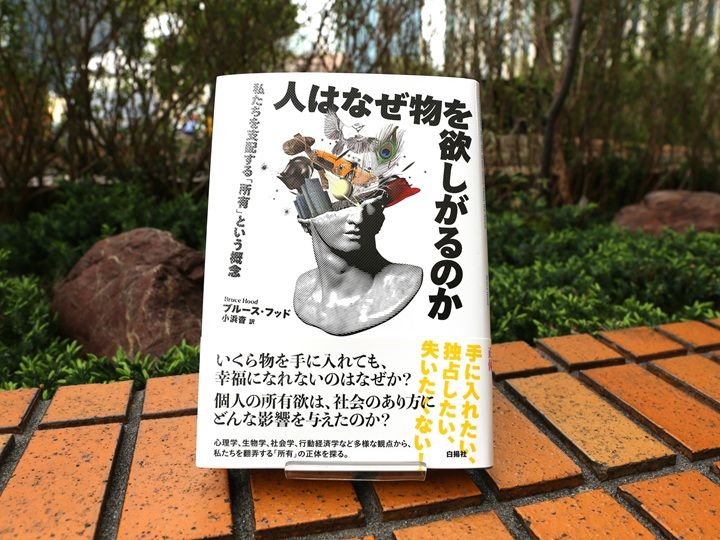
ポケモンショップに徹夜で大行列する人たちがテレビニュースでたびたび取り上げられている。希少な〝レアカード〟には1枚20万円もの値が付くという。果ては、カードを求めての強盗事件まで起きている。そこまでして手に入れようとする、その欲望の凄まじさには驚くばかりだが、人々の所有への欲望は、さまざまな形で現れる。
部屋中にアイドルタレントのグッズを飾る女性、高級腕時計のコレクションを自慢する富裕層、本棚に入りきらないほどのマンガ本を集めるオタク男性……所有欲が現れるのは、こうしたわかりやすい〝物〟のコレクションだけではない。発達心理学者の著者は冒頭部から驚くべき事例を提示して「所有」の本質に迫る。
競売で手に入れた燻製用のグリルの中に人間の足が入っていた。この足は元々のグリルの持主の、事故で切断された足だったのだが、果たして所有の権利を有するのは足の持主なのか、それともグリルを買った人なのか? 答えはぜひ本書を読んでいただきたいが、この後も、配偶者や子供、個人情報、遺体、知的財産などが所有物となりうるか否かを次々と検討していく。驚きながら読み進めているうちに、私はいとも簡単に著者の術中にはまってしまった。ごく当たり前の行為だと思っていた「所有」の概念が変わり、ページをめくる指が止まらなくなっていた。
社会制度の成り立ちを所有という観点から考える章は、特に説得力を感じながら読んだ。世界中で起きている紛争や政情不安ももとをただせば「所有」をめぐる争いで、たとえば、土地をめぐって、資源をめぐって、権利をめぐって人々は争っている。社会を安定的に維持するためには、人の所有欲を守ったり適度に制限したりする制度が必要になってくる。法やルールは道徳心の延長として生まれたと思い込んでいた私にとっては、まったく新たな見解だった。
こうした〝目から鱗〟な考察が本書では次から次へと展開される。富に任せていくら欲しいものを手に入れても幸せになれないのはなぜか、隣の芝生が青く見えてしまうのはなぜかなどのテーマが、生物学的、行動経済学的、心理学的、社会学的に考察されていく。
それなのにとっつきにくい内容になっていないのは、各所に「所有」に関わる興味深い話題が散りばめられているからだろう。例を挙げれば、「イギリスでは2016年だけで10万件を超える離婚があったが、1857年に離婚法が制定されるまでのイギリス全史でもわずか324件しか離婚がなかった」「南米に住む吸血コウモリは腹を空かせた仲間に自分が吸った血を分け与える」「ドナルド・トランプがレストランで出会ったハリウッド俳優にプレゼントしたダイヤのカフスボタンは偽物だった」等々の雑学が次々と挿入される。さらに、平等で格差のない社会は実現できるのか論じたかと思えば、バンクシーの作品は落書きかアートかを考察し、イスラエルとパレスチナの紛争の原因について見解を述べたりもする。まるで「所有」をテーマにした面白いトークショーを聴いているような気持になるので、決して退屈することはないはずだ。
著者は「所有」からは幸福は生まれないと言う。人間がよりよく生きるためには「所有」という「悪魔」を祓う必要があると訴えるが、それがいかに難しいことかは、昨今の中東情勢を見ていれば明らかだ。未来の人類に突き付けられた課題なのだろう。
人間の三大欲望といえば、食欲・性欲・睡眠欲だというのが定番だが、本書を読み終わった今の私には、三大欲望の上に君臨するのは所有欲かもしれないとさえ思ってしまうほどだ。人間の根源的欲望について考察しながら、話のネタになる雑学を学び、社会問題まで考えさせられてしまう見事な一冊なので、ぜひ手元に所有して、何度も読み返してほしい。
はじめに
第1章 本当に所有していますか
第2章 動物は占有するが、所有するのは人間だけ
第3章 所有の起源
第4章 それが公平というものだ
第5章 所有と富と幸福
第6章 私のものとは私である
第7章 手放すということ
おわりに