池澤夏樹「双頭の船」書評 桁外れの喪失に 言葉与える格闘
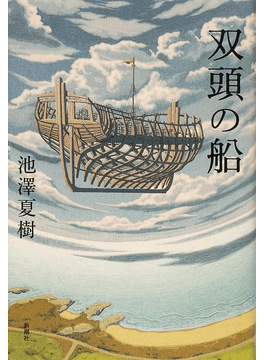
ISBN: 9784103753087
発売⽇:
サイズ: 20cm/259p
双頭の船 [著]池澤夏樹
「絆」――何か言った気になれる便利な言葉ではあるが、ひとつだけ、はっきりさせよう。
「絆」の要件とは、一人一人、ばらばらであることだ。
同じであることではない。たとえば酸素分子があって、隣も酸素分子なら、どこまで行っても酸素。だが、水素分子が隣り合わせると、水という奇跡的な第三のものが生まれる可能性がある。
ばらばらほど、融合するものはない。簡単なことだ、が、盲点である。この冷徹なまでの明晰(めいせき)さから物語は出発する。「船」ほど、それを端的に体現するものはないから。船は乗組員がそれぞれのことをして初めて動く。逆に乗組員が「一枚岩」だったりしたら沈む。
「3・11」直後の被災地沿岸部。小さなフェリー船、しまなみ8は、独自のボランティア活動に乗り出す。やがてさくら丸と名乗るその船は、独自の価値と規範を創(つく)り、独立した共同体のようになり、食物をつくり家族をつくり、歌い踊り祭りをし、死者の弔いをする。やがて船は、意外な姿を読者のうちに結ぶだろう。
もとは狭い港内で転回せずに発着できる、舳先(へさき)と艫(とも)の区別のない双頭の船。それが自らに課した最初のミッションは、日本各地で放置された自転車を回収、船内で整備して、津波の被災地に届けること。そのために呼ばれた知洋がメインの語り部であるのは、当然のことに思える。整備とは、ばらばらにして、ひとつにすることだからだ。それは、摂理をもたらす行為である。だから、別のすこぶる魅力的なキャラクター、熊を本来いる場所に帰したりオオカミに掟(おきて)を教えたりする男、ベアマンとも、違うようで似ていて、どちらにも居場所がある。「それぞれが個性と力を発揮すれば、一人一人がユニークな存在で必ず居場所がある」。よく言われるこのことは、本当なのだ。ただ、楽ではないというだけだ。これをあたかも個人の当然の権利のように喧伝(けんでん)したのは「戦後」の罪ではなかろうか。
「戦後」の罪のもう一つは、大戦の膨大な死に言葉を与えていないことだろう。被災地の「復興」が、進まないどころか忘れられ、国内棄民をつくりつつあるのは、桁外れの喪失に言葉を与える力が社会にないからではないか。池澤夏樹は、これに言葉を与えようと格闘している。寓意(ぐうい)に満ちた語りは神話的で、現実的ではないと言う人もあろう。が、そのようにしか語れない重層性もあるのだ。
「船は橋のようなものかもしれない」と、私はふと思った。橋に、どちら向き、もない。きちんと過去と折り合うことと、未来を夢見ることとは、等価である。人もまた、双頭の船なのだ。
◇
新潮社・1575円/いけざわ・なつき 45年生まれ。作家。88年に「スティル・ライフ」で芥川賞。93年、『マシアス・ギリの失脚』で谷崎潤一郎賞、2000年、『花を運ぶ妹』で毎日出版文化賞、01年、『すばらしい新世界』で芸術選奨文部科学大臣賞。11年に朝日賞。












