SNSで、口コミで、静かな反響を呼び続けるロングセラー ――宮地尚子『傷を愛せるか 増補新版』より
記事:筑摩書房
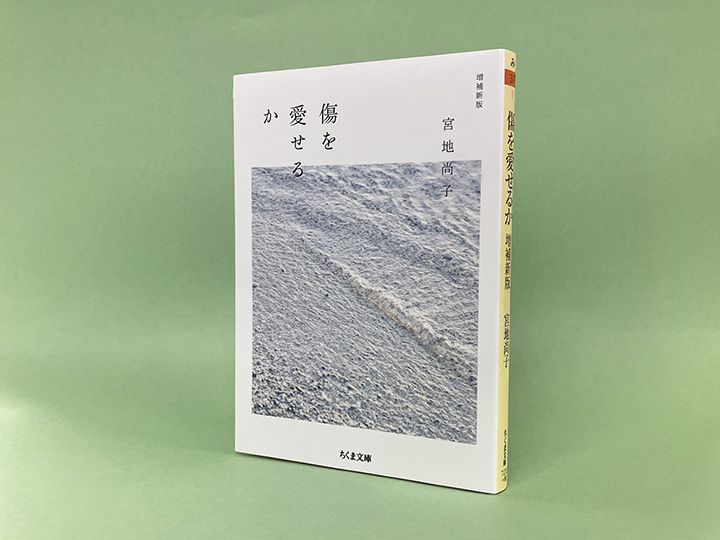
記事:筑摩書房
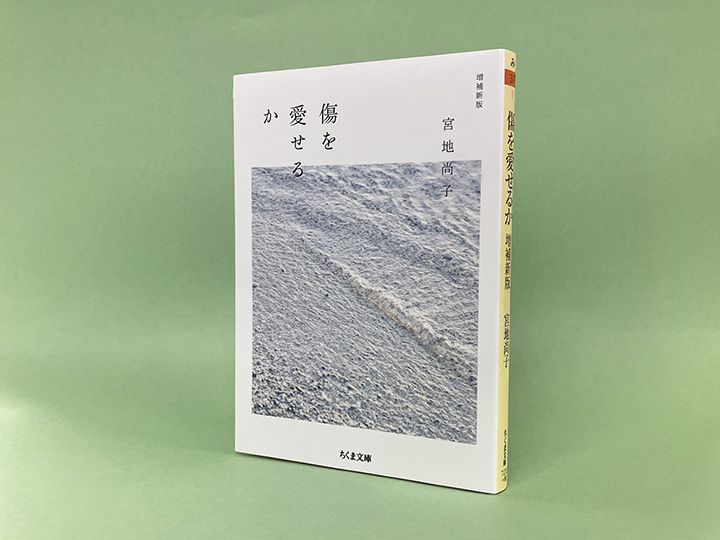
こんなふうにあなたが飛びだし、遠ざかってゆくとき、わたしがあなたを見届けてあげる必要が、まだありはしないでしょうか?
——リュス・イリガライ『基本的情念』
娘がまだとても幼いころ、外出先で階段から転げ落ちたことがあった。少し離れたところにいたわたしは、落ちていく姿をただ見つめていた。ただ黙って、目を凝らしていた。静かに。動くことなく。はたからは冷たい母親だと思われたかもしれないと、あとで思った。母親だとふつう、パニックになって叫んだり、あせって駆け寄ったりしそうだからだ。
なぜパニックにもならず、駆け寄ることもなく、ただ見つめていたのか。
たぶんわたしはそのとき、医師としての自分になっていたのだろう。どのように落ちていったかをきちんと見ておくことが、その後どのように対処すればいいのかを考えるのに、いちばん役立つからだ。
なにが起きているのかを、冷静に観察することは、診療行為の基本である。感情に突き動かされず、よけいなことをせず、経過を見届ける能力を身につけることは、医師として不可欠なものだろう。
けれども、それはあとから取ってつけた理由なのかもしれない。もしくは、順序が逆なのかもしれない。そう思い直す。起きていることを、ただ見つめる癖があったから、わたしは医師という職業に就き、いまのような仕事をしているのかもしれないと。
なにもできなくても、見ていなければならない。目を凝らして、一部始終を見届けなければいけない。そういう命題が、自分に課されているような気がずっとしていた。その命題が、どこから来たのかはわからない。いつからかも覚えていない。だれかにいわれたわけではないと思う。
幼いころの体験が作用しているのかもしれない。ここには書き記さないが、いくつか思い当たる記憶がある。家族の中でいちばんの年少者として、じゅうぶんに愛され、守られてきたとは思うが、同時に、家族内外の災難や諍(いさか)い、悲喜こもごもを、いちばん無力な存在のまま、はらはらしながら目撃しつづけていたような気もする。
わたしに限らず、子どもというのは、自分のまわりに起きることを、ただ見つづけるしかない。大人たちの諍うさまを、ほかの子どもが理不尽にあつかわれるさまを、自分を守ってくれるはずの大人が怯えたり、あたふたするさまを、大切なだれかが恐ろしい目に遭ったり傷つくさまを、ただ息をつめて見ているしかない。諍いをやめさせたくても、まちがいを正したくても、自分にはその力はない。だれかを守りたくても、守る力はない。かといって、立ち去る力も行く場所もなく、ただそこにいつづけるしかない。だから目を凝らして見ているしかない。ふすまの陰から、車の後部座席から、教室の隅のほうから。
大人になって、医師になって、専門的な知識と技術を身につければ、もう、ただ見つづけるだけでなく、目の前の状況になんらかの変化を与えることができる。諍いを止め、まちがいを正し、人の命や心を守り、安心感を与え、傷つきを癒やすことができる。……そのはずだったのだが、現実には、子どものころと同じような経験ばかりをくりかえしているような気がする。
拱手傍観(きょうしゅぼうかん)という言葉がある。手をこまねいたまま、そばで観ていることだ。肯定的な意味で使われることは少ない。けれども、手をこまねいたまま観ているしかないときは多い。手を差し伸べようがないとき、差し伸べても相手に手が届かないとき、届いても引き上げる力が足りないとき。どれだけ医療が発展しても、治らない病気はいくらでもある。傷ついた心を癒やす特効薬はないし、回復が促されるよう周囲の環境を整えるにも、時間と精神的エネルギーがおそろしくかかる。目の前で状況が悪化しつつあっても、本人や家族がいったん「底つき」をするまで、待つしかないこともある。
結局、大人になっても、医師になっても、自分が変えられることなどごくわずかでしかないことを、思い知らされつづける。子どものときとちがうのは、無力感に罪悪感が上乗せされるということだろうか。手をこまねいていたほうがましなのに、わざわざ危険な領域にまで手を伸ばしてしまうことがあるのは、なにもしなかったという罪悪感から少しでも逃れるためかもしれない。よけいなことをせず、ただ見守りつづけることもまた、むずかしい。そして苦しい。
少し話は変わるが、最近、親しい女友だちが最愛のパートナーを病気で喪った。彼とも友人であり、治療方針のことで相談を受けたりもしていたので、その死はもちろんショックだった。生命力に満ち、長いあいだ病いと共生してきた人なので、訃報(ふほう)は信じがたかった。ただ、あまりに仲のいいカップルだったから、遺される彼女のことが最も心配になった。つきっきりの看病で、ようやく光が見えてきた矢先だった。彼がいなくなることなど、彼女にはこれっぽっちも考えられなかったはずだ。
仮通夜に駆けつけ、お葬式にも出席したが、彼女にどう接すればいいのか、わたしにはわからなかった。どんな慰めをいっても、手を握っても、ハグしても、なんの力にもなれないと思った。すべてが薄っぺらくて、自分が下手な芝居を演じているような気さえした。
そばにいても、彼の代わりにはだれもなれない。そのことは、痛すぎるほど明白で、動かしようのない、どうしようもない事実である。
お葬式の日は、蟬時雨(せみしぐれ)の降り注ぐ、よく晴れた暑い日だった。喪主を務める彼女は、みんなの前で終始おだやかな表情をたたえていた。参列者へのあいさつも過不足のない美しいものだった。
式のあと、冷房の効いた斎場で火葬がおこなわれ、参列者が骨を拾う。骨壺に彼の骨が納められていくのを、彼女が見つめる。最後の一カ月間、入院生活を余儀なくされていた彼の身体。そこに残された病院からの異物が骨壺に混入しないよう、目を凝らす。その彼女の姿を、わたしは見つめる。
そのとき、なにかが腑(ふ)に落ちた。見ているだけでいい。目撃者、もしくは立会人になるだけでいい、と。
「なにもできなくても、見ていなければいけない」という命題が、「なにもできなくても、見ているだけでいい。なにもできなくても、そこにいるだけでいい」というメッセージに、変わった。
ちゃんと見ているよ、なにもできないけど、しっかりと彼女が喪主の役割を果たす姿を目撃し、いまこの時が存在したことの証人となるよ。そしてこれからも彼女が彼女らしく生きていくのを、見つめているよ。喪失は簡単には埋まらないだろうけれど、それでもいいよ。急がないで。ずっと見ているから。見ているしかできないけど。……そう思った。
そう思わせてくれたのが、亡くなった彼のもっていた生命力からくるのかどうかはわからない。でも彼も、どこかから見つめているにちがいない。
目撃する。目を凝らす。見つめる。見据える。見通す。見極める。見届ける。「見守る」ほどの力や度量は、いつまでももてないだろうが、それでいいのだ。
英語では、目撃することも証人も、「ウィットネス」という。目撃すること。証人になること。自分が直接ひどい目に遭ったわけではないから、その恐怖や緊張は、本人にも周囲にも気づかれないままのことが多いが、強い負荷を心身にかけるはずだ。子どものころのわたしも、どれほど怖かっただろうと、ようやくそのことに思いがいたる。けれども同時に、子どもが自分で感じるほど、子どもは無力ではないのかもしれない、ということにも気づく。起きたことを目に焼きつける子どもがいることで、救われる人間もかならずいるはずだから。

Ⅰ 内なる海、内なる空
なにもできなくても
〇(エン)=縁なるもの
モレノの教会
水の中
内なる海
泡盛の瓶
だれかが自分のために祈ってくれるということ
予言・約束・夢
Ⅱ クロスする感性――米国滞在記+α 二〇〇七―二〇〇八
開くこと、閉じること
競争と幸せ
ブルーオーシャンと寒村の海
冬の受難と楽しみ
宿命論と因果論
ホスピタリティと感情労働
右も左もわからない人たち
弱さを抱えたままの強さ
女らしさと男らしさ
動物と人間
見えるものと見えないもの
捨てるものと残すもの
ソウル・ファミリー、魂の家族
人生の軌跡
Ⅲ 記憶の淵から
父と蛇
母が人質になったこと
母を見送る
溺れそうな気持ち
本当の非日常の話
張りつく薄い寂しさ
Ⅳ 傷のある風景
傷を愛せるか
あとがき
文庫版あとがき
解説 切実な告白と祈り 天童荒太
初出一覧
エピグラフ・出典