「あの頃」の苦しみに、もう一度触れる――小川たまかさん書評『このクソみたいな社会で“イカれる”賢い女たち』
記事:明石書店
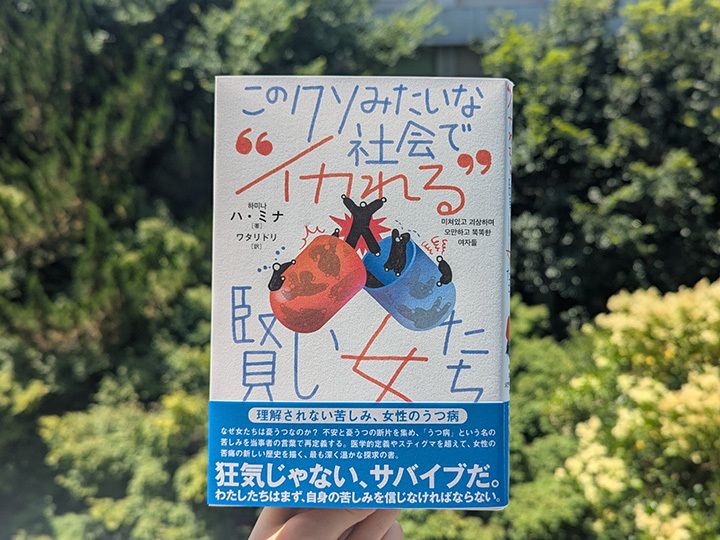
記事:明石書店
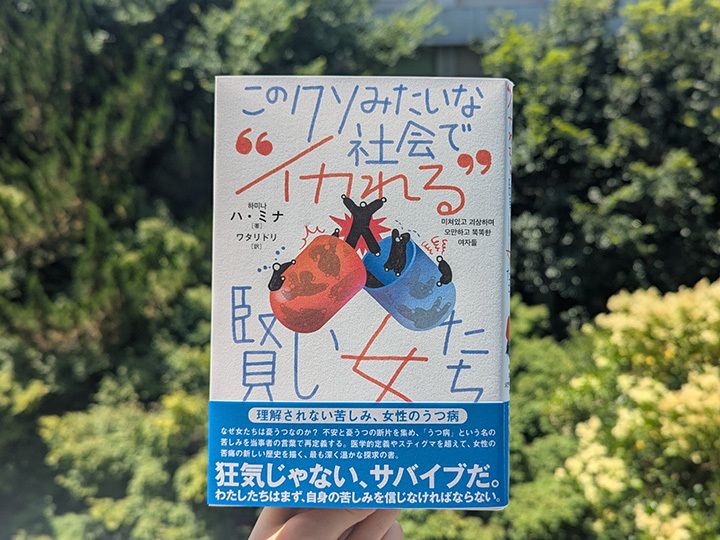
正直に言えば、開くのに勇気のいる一冊だった。
私は性暴力や性差別を主に取材するライターであり、被害後の長い時間をうつなどの症状に苦しんで過ごした人たちを多く知っている。だからこそレビューを頼まれたと思うのだが、この本の著者であるハ・ミナや彼女がインタビューするうつの女性たちが20〜30代だと知って、いたたまれない気持ちになった。
私は現在40代だが、20代の頃よりもずっと心穏やかに過ごしている。女は若いうちはイージーモードなどといまだに思っている人がいるけれども、そんな単純な事実はない。社会がどれだけ若い女性の自己主張が嫌いかに気づいていないうちでも壁は歴然としてそこにあるし、気づいたら気づいたで社会から切り離されたような感覚になる。
40代になって数十年前の生きづらさが過去になりつつある今(そして完全に過去になりきっているわけでもない今)、その真っ只中にいる彼女たちの言葉を一つずつ辿っていく作業に情けないけれど足がすくんだ。いくつものページで自分のかけらを発見すると予見できたからだ。彼女たちの怒りは自分の怒りのようで、ニューゼネレーションが今も同じように苦しんでいる現実を見せられるとは、これはやっぱり何かの罰ですかと怯えた。
ハ・ミナはまず第I部で、精神医学は男性主体であると指摘する。
女性だけでなく男性にもやはり性ホルモンがあり、また特定のライフステージを経験するにもかかわらず、テストステロンは男性の精神疾患を診断する際の重要な基準とはされていない。(略)うつも、男性の『正常』な身体が原因なのではなく、かれらを苦しめる外的要因、つまり社会文化的条件が原因とされるのである。逆に女性のうつを語る際には、女性の『非正常』な身体の中に原因があるとみなされる。(P20)
そして、西洋の男性を主体に研究された「うつ病」の基準で、社会文化的条件の異なる韓国女性を診断できるものなのかと疑問を呈する。
診断室で起こる被害の軽視や無理解、薬の効用と副作用、あるいは日本でも製薬会社のマーケティングによって広められたように思われる「うつ病」の定義。文献による調査と女性たちへの聞き取りを交えた上で突きつけられるのは、この分野がどうしようもなく発展途上であるという現実である。もちろん、すべての学問・研究は発展途上であるけれど、ハ・ミナは医学の中のミソジニーを指摘しながら、発展途上の精神学に頼るしかない人々の現実を、まるで未来から振り返るようにして活写する。
第Ⅱ部では、家族や恋人、そして社会が彼女たちにとってどのような影響を及ぼしてきたかが明らかにされる。そうそれ、と言いたくなる文章が並ぶ。
経済的に苦しい状況の中、病気の子どもの面倒をひとりで見る女性が、どうしておかしくならず落ち着いていられるだろうか。(P138)
女性たちがあまりにも散り散りになっています。他のつながりがないから男性との一対一の恋愛でそれを埋めようとするんだと思います。(P169)
地方に住む女性たちであるほど、より家父長的で性差別的な社会に直面している。(P191)
会社にいるためには平気なふりをしなきゃいけないし、こういうハラスメントに対しておもしろおかしく切り返さなきゃいけないんです。(P193)
ハ・ミナが出会った女性たちは「誰もうつをまったくの個人の問題と見てはいなかった」(P203)という。むしろ自分のせいだと思えたらいいでしょう、とさえ語るのだという。けれど世論はうつを個人の問題と見なし、あまつさえ努力や耐久が足りないのだと言ったりする。人(社会)のせいにするなという叱咤の前で、彼女たちはもはや沈黙するしかない。
韓国と日本は状況が似ている部分が多くある。違う点の一つは、韓国ではデモや社会運動が活発なことだろう。ただ日本でもたとえば「保育園落ちた日本死ね」のように、SNSがあったから可視化された女性の鬱屈がある。孤立した女性をつなぐツールであるという指摘は日本にも当てはまる。
第Ⅲ部ではまず自殺について触れられている。統計によれば韓国では1日に36人が自殺し、リベンジポルノやミソジニーによる攻撃を受けて命を断ったアイドルもいた。彼女たちの死は当然、同年代の女性に強い影響を与えるし、それよりも前に子どもの頃からの希死念慮につきまとわれている人もいる。
続く章は「ケア」と「回復」であり、深刻なうつに苦しむ女性とその恋人の様子や他人へのケア、同じ苦しみを持った集団の中での回復について綴られている。安易な希望には頼るまいとしつつも、回復に向かう道筋を示そうとしている。
第I章から第Ⅲ章までを読み終えると、ページが進むごとに著者の筆致が柔らかくなっていく印象を持つ。うつを患うと集中力が続かなくなり本を読み進められなくなる一方で、ものを書くことが自分の回復につながっているように思うと、ハ・ミナは何度か書いている。実際、この本を書くことで彼女はひとつかふたつ、心の荷をおろしたのではないか。
ものを書くというのは、他人に(もしくは自分に対して)何かを説明することだ。対人関係の中で、長い話は嫌がられるし、心ゆくまで説明させてもらえることはなかなかない。それがうつ病患者であったらなおさらだし、まだ社会の中で理解されづらい概念であれば最後まで聞いてもらえることの方が少ない。表現をする行為は、少なくとも自分自身に対しては説明をし尽くすことができる。だから彼女はペンを取らずにはいられなかったのではないか。
第Ⅱ章で、なぜこの本で20〜30代の女性の苦しみに着目したのかについて、ハ・ミナ自身がその苦しみの目撃者だと思うからだと書かれている。
わたしが望むのは、『20〜30代の女性の苦しみを見てくれ』というよりは(もちろんそれもあるが)『20〜30代の女性の目線に立って世界を見てほしい』ということだ。(P204)
私が本書を怖れたのはまさに、もう20〜30代の目線に戻りたくないと思ったからだろう。かつて待機児童問題は、渦中にいる子育て世代は忙しすぎて課題に取り組めないし、子どもが育った後は何があったのか忘れるから(あるいは次の課題にぶち当たるから)、問題が据え置かれてきたと言われた。若い女性と社会の深刻な齟齬や、若い女性の病理の矮小化も同じで、当事者であるうちは声を上げることができない人が多く、いったんそこを抜けたら「忘れよう」「忘れたい」という意識が働くのだと思う。
だからこそ、嵐の真っ只中から本書を綴った著者の行動は途方もなくエネルギーのいることであり、道なきところに道をつくるアクションであっただろう。
いくら説明しようとしても理解を得られないために自分を曲げざるを得ない目に遭った人たち。そんな目に遭ったけれど、まだそれに気づいていない人たち。かつてそんな目に遭った人たち。まずはそういった人が、怖れずに過去を振り返ることができるようになれば。そんな未来を考えた読後感だった。