「怒り」と「からかい」が社会を壊すとき──トランプ政権に見る政治と感情の危うい関係
記事:晶文社
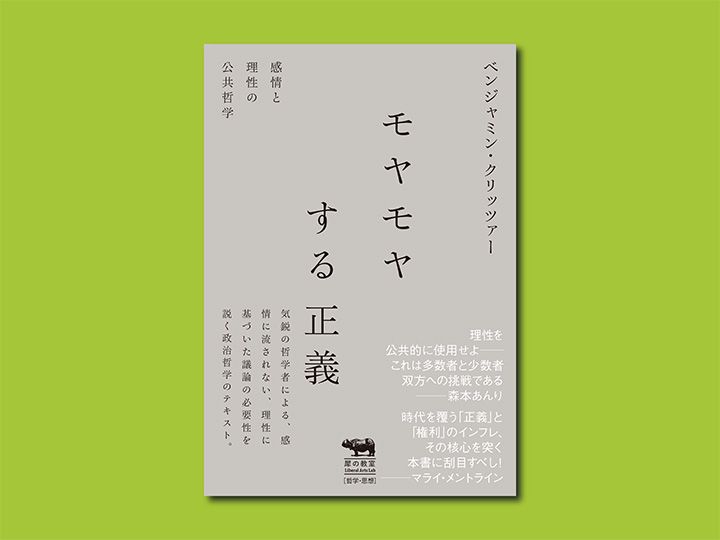
記事:晶文社
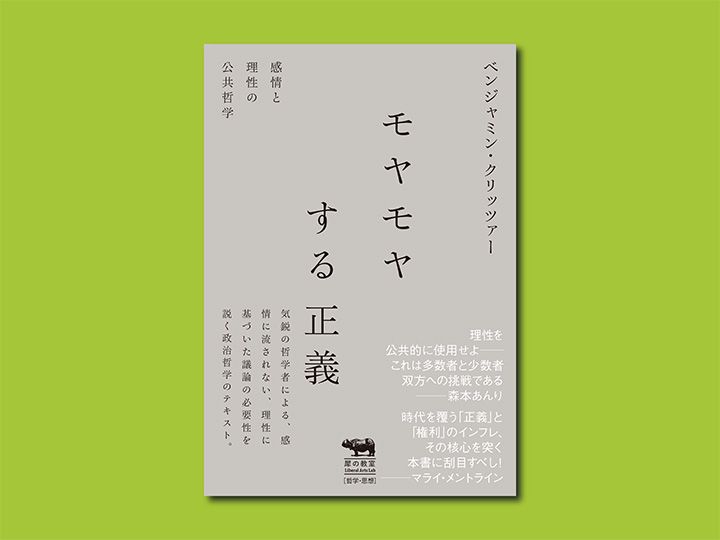
政治には感情が付き物だ。そして昨年のアメリカ大統領選挙の結果や、その後のアメリカで起こっている事態は、政治において「怒り」が持つ力を生々しく示している。
ドナルド・トランプ現大統領は以前からも虚偽や陰謀論を振りまいて支持者の怒りを煽り続けて、2021年1月には合衆国議会議事堂襲撃事件を引き起こした。同年、現副大統領のJ・D・ヴァンスは全国保守主義会議で「大学こそ敵である」と題したスピーチをしているが 、学問に携わる人々に対してトランプや共和党の支持者たちが抱き続けていた怒りは、現在になって研究助成金の削減や教育省の解体といった政策に結実している。
行き過ぎた怒りが本人の身を滅ぼすことは明白だ。議事堂襲撃犯のうち200人以上が裁判で有罪となり、今年1月にトランプが恩赦を与えるまで収監されるなどの罰を受けていた 。また、医療や気候変動対策などに関する研究費までもが削減されている事態は、トランプ支持者を含めた多数のアメリカ人たちに(そして残念ながら世界中の人たちにも)遠からず多大な不利益を生じさせるであろう。
トランプを取り巻く事態においては、怒りと並んで「ユーモア」や「笑い」も目立っている。
アメリカは以前から政治的な風刺が活発に行われてきた国だ。現在も、トランプやヴァンス、マスクらを題材にした風刺画が毎日のように描かれ、現地の新聞や雑誌に掲載されたりSNSで拡散されたりしている。今年で50周年を迎えたアメリカのコメディ番組『サタデー・ナイト・ライブ』では、トランプらに扮したコメディアンたちが出演する政治コントが毎週のように放送されている。
一方、2月、トランプは自身が立ち上げた会社が運営するSNS「トゥルース・ソーシャル」に、パレスチナ・ガザ地区がビーチリゾートに改造されてトランプ自身の姿を象った巨大な黄金像が建立されている様子を描いた人工知能生成動画を投稿した。後日、この動画は映像作家らが風刺目的で作成してインスタグラムに投稿し、数時間後に削除したもののトランプに無断転載されたという経緯が明らかになった 。
トランプやその参謀をつとめる実業家のイーロン・マスクの特徴のひとつが、露悪的で悪趣味なユーモアを好むことだ。マスクのXアカウントにはリベラルや民主党支持者、「ウォーク」を揶揄するネットミーム(いわゆる「ネタ画像」)がたびたび投稿されている。トランプも「黄金のガザ像」が自身に対する批判的な風刺や揶揄であることにおそらく気付かないまま、おもしろがって転載したのだろう。こんな状況では、風刺やユーモアといったもの自体の意義にも疑いの目を向けたくなる。
昨年9月に刊行された拙著『モヤモヤする正義 感情と理性の公共哲学』(晶文社)では、政治や民主主義にとって「怒り」と「笑い」という感情が持つ意味や、それらの感情と「理性」との関係について、一章を割いて論じている。
なぜ、私たちは政治的な領域においては怒りと笑いの双方を警戒すべきなのか。以下、「トーン・ポリシング」という概念や「からかいの政治」に関する議論を紹介しながら論じていこう。
さて、一般的に、物事を主張したり論じたりする際には「感情的」になることは避けるべきだとされている。とくに政治的な要求を訴える際には、自分がなぜその要求をしているのかを説明し、また相手はなぜその要求を受け入れるべきなのか、理由や証拠を提示しながら論理的に説得することが理想だとされている。
この考え方の背景にあるのは、原則として民主主義の社会では誰もが対等の存在と見なされる、という前提だ。民主主義では誰もが等しく自分の意見や訴えが発信可能であるべきだ。ただし、同時に、その意見や訴えを聞く他の人たちも自分と対等な存在である。自分が意見を言ったら相手は質問や反対ができること、相手は自分の訴えに疑問や批判を呈するのが可能であること、それらの状況があって初めて、民主的な議論と政治が成り立つ。
とくに政治的な要求を発する際には、自分たちと異なる立場の人たちとの間では利害が対立しており、自分の要求が通じた場合には異なる立場の人たちには多かれ少なかれ不利益が生じる、という場合が多い。そのような場合にも、たとえば「現在の社会状況や実施されている政策の下では自分たちの方に多大な不利益が生じているのであり、平等や公正のためにもこれらの状況や政策は是正されるべきだ」などと、理念や理由を提示しながら議論を行い、相手に納得してもらうのを目指すべきだ。
逆に、自分が要求をされる立場になった場合には「自分がその要求を聞き入れ、不利益を受け入れなければならない理由はなにか」と問いかけてよい。重要なのは、問いかけに対して相手が理由を適切に提示したなら、その理由にきちんと向き合い、相手の要求や訴えから目を逸らさないことだ。同様に、自分が要求を行う際には相手の問いかけを無視せず、誠実に理由を論じる。それこそが、対等で民主主義的な社会における議論であり、政治的な営みである。
言うまでもなく、上記の主張はかなり理想主義的なものだ。実際の政治において「議論」や「理由」がどれだけの力を持っているかは心許ない。権力を持つ側の人々は、自分に相反する人々を説得するまでもなく、相手に対して不利益をもたらし自分に利益を与える政策を易々と実行してしまえる。既得権益の影響は強く、水面下での根回しや権謀術数などが行われることにより、公開性のある選挙や議論が実施されるまでもなく重要な政治的決定がなされる事態は多々発生している。いざ議論が開かれたとしても思考や認知を操作するレトリックや陰謀論の力は甚大であり、また何としても自分たちの側を肯定して相手の側を否定しようとするバイアスや感情も影響するため、理性的で論理的な主張がどこまで意味を持つかは疑わしい。
それでも、異なる立場にいる人々が互いに相手を対等な存在と見なして、共通して備わっている理性に訴えながら合意や妥協の成立を目指していくという民主主義的な議論の理念を手放すべきではない。たとえ建て前に過ぎないとしても、実施される政策を正当化し、また自分たちの生きる社会を私たちが肯定するうえで、この理念は不可欠だ。そして、現時点で不当な不利益を被っており、政策や社会の状況を変えることを求める人々にとってこそ、この理念は力を発する。
上記のような「意見や訴えを主張したり要求をしたりする際には、冷静で論理的な方法で行うべきだ」という主張を批判する考え方も存在する。つまり、訴えや要求をしている人の「口調(トーン)」を云々すること自体が、不利益を被っている人々を抑圧して黙らせて現状の不当な構造を維持させる効果をもたらす「トーン・ポリシング」であり、この行為は批判すべきである……という考え方だ。
トーン・ポリシングを批判する考え方において重要なのは、ある主張が「理性的」に見えるか「感情的」に見えるかということ自体が、その主張を発信する人の属性と、背景にある社会の構造や文化によって左右されるという指摘だ。
この問題はとくに性別が関わる場面において顕著である。つまり、アメリカにも日本にも「男性とは理性的な存在で、女性とは感情的な存在である」という偏見やステレオタイプが根強く存在しているために、同じ主張であっても女性が発信した場合にのみ「感情的」とのレッテルが貼られやすく、女性の意見が無視されたり訴えが否定されたりしてしまいがちだ。「政治的な要求は論理的に行うべきだ」という規範を採用するだけでも、女性が政治的な要求を行う際には、そのスタート時点で男性よりも高いハードルを課せられる。また、同様のハードルは人種的・性的マイノリティの人々にも課せられている。
そして、フェミニズムやマイノリティの権利運動に関わる人々の一部は、単にトーン・ポリシングを批判するだけでなく、政治において「怒り」をはじめとした感情を発露すること自体を肯定する議論も行うようになった。そもそもマジョリティとマイノリティとの間で不均衡が存在する状況では、理性を重視する発想はそれだけでマジョリティを有利にする。マイノリティが不利益を押し付けられている状況を打開するためには、自分たちの怒りを堂々と肯定し、社会に向かって表明しなければならない……。
私は、女性やマイノリティの人々が上記のような発想にたどり着いた経緯を不十分ながらも理解できているつもりだし、彼女らに共感を抱く面もある。
だが、やはり、怒りを肯定する議論は危なっかしい。なにはともあれ議事堂を襲撃したトランプ支持者たちも怒りに駆られて行動したのであり、彼らの主観では、自分たちこそが不公正な選挙によって意見や主張が黙殺され不利益を押し付けられた被害者であったのだろう。
さらに悩ましいのが、第二期トランプ政権は男性のみならず、一部のシスジェンダー女性らがトランスジェンダー女性に対して抱いている「怒り」を利用している点だ。その怒りは、トランスジェンダーをはじめとする性的少数者の人々の存在を否定して弾圧する国家的な差別政策につながり、彼女らや彼らの健康や生命すらもを脅かしている。そして、議事堂を襲撃した男性たちと同じく、シス女性たちもまた、自分たちこそがトランス女性によって不利益を被らされている被害者であるという主観を抱いているのだ。
この問題を是正できるのは、感情ではなく理性である。主観だけでは認識できないマジョリティの有利さやマイノリティの不利益を客観的な論理によって明らかにしながら、互いが共に生きていく社会を実現する方法を議論していくしかない。トーン・ポリシングが女性やマイノリティに対して不当に高いハードルを課すとしても、政治的な主張に対して「理性」のハードルを課すこと自体は正当だ。必要なのは、マジョリティとマイノリティに課せられるハードルの高さを等しくすることである。
上記の「怒り」に関する議論は、訴えや要求を行う側の感情についてのものであった。しかし、トーン・ポリシングに関連して、訴えや要求を「される」側が抱く感情についても議論を行う必要がある。
属性に関わらず、相手が自分のことを批判したり自分に不利益を課すような要求を行なったりする場合には、自分にとって相手は「感情的」に見えてしまいがちである。これは社会構造の問題などを抜きにしても存在する、私たちに根深く備わった心理学的な傾向だ。
人間の心理とは保守的なものであり、自分自身を批判したり自分にとって有利な状況を疑ったりすることは、それだけで感情的ストレスを生じさせる。したがって、理性的に相手の主張を受け止めようとする以前に、相手の主張を取るに足らないものとして扱い無視しようとする「否認」のメカニズムが作動することになる。
社会学者の江原由美子が1981年に発表した論考「からかいの政治学」(『増補 女性解放という思想』(2021年、筑摩書房)に収録)では、1970年代の日本のウーマンリブ運動やアメリカのフェミニズム運動に関して、当時の週刊誌などのメディアは運動家の女性たちの性的な要素をことさらに強調し、また女性たちの主張を誇張して「おそろしいもの」と戯画的に表現していたことを指摘しながら、当時の男性中心主義的なメディアが行なっていた女性運動家に対する揶揄や侮辱など「からかい」のメカニズムが論じられている。
「からかいの政治学」は2020年代になってからも参照され続けている。その背景には、社会運動を行なったり政治的な意見や訴えを発信したりする女性に対する「からかい」は現在でも再生産され続けており、インターネットやSNSを中心にして過去よりもさらに拡散されているという問題が存在する。
一般的に、「怒り」に比べると「笑い」や「ユーモア」には理知的で冷静なイメージがある。だが、揶揄や侮辱を通じて相手の主張を矮小化してその指摘から目を逸らし、社会の状況や自分たちの問題を批判的に考えることを拒否するという点で、「自分たちにはユーモアがある」と思いながら男性たちが行う「からかい」は理性にまるで相反している。さらに、怒りと同様に笑いも集団的な感情の高まりをもたらし、女性をからかう行為に参加した男性たちの思考や認知を歪める傾向があることを、『モヤモヤする正義』では指摘している。
笑いやユーモアには反権威的で革新的なイメージもある。既存の権威や秩序に対抗するためのユーモアは好ましく肯定すべきものだ、という議論は左派やリベラルの人々の間にも見受けられる。だが、イギリスの心理学者マイケル・ビリッグは著書『笑いと嘲り ユーモアのダークサイド』(鈴木聡志訳、新曜社、2011年)でこの風潮に疑問を呈している。
怒りに関して論じた時と同様に、問題となるのは、どのような人々が「権威」の側に位置しておりどのような物事が「秩序」であるか自体が、各人の主観によって委ねられてしまう点である。
ビリッグは「反逆的ユーモア」が保守的な機能を持つことを指摘している。ポリティカル・コレクトネスを笑い物にして「真面目」なリベラルや左派の人々をおちょくるコメディアンは2000年代の時点でも多数いたが、彼らやその観客たちはポリティカル・コレクトネスが「権威」であり自分たちこそが「反逆者」であると、本気で信じていたのだ。同様の傾向はトランプやマスクに、そして彼らの支持者たちに、今でもそっくりそのまま存在している。
本項では昨今のアメリカを題材にしたが、政治と「感情」の結び付きが激しくなり、人々の間の分断や対立が進行する状況は、日本でも同様に起こっている。
この現状でこそ、私たちは「理性」に立ち戻るべきだろう。異なる立場にいる人々の権利を蔑ろにして差別を扇動し、社会を破壊することも辞さない輩に対して怒りを抱くのは良心を持った人間にとって当然のことではあるが、それらの行為を否定して止めさせるためにこそ、彼らに対する批判は第三者にも共有可能な論理に基づかせることが必要だ。
そして、揶揄であろうが風刺であろうが、相手のことを笑い物にしながら相手に対する理解を深めることはできない。相手に対して同情や共感を抱くべきだとは限らないが、相手の主張や行為の背景にある動機や思考、そのさらに背景にある社会的な問題や歴史的な経緯などを理性の光に照らして眺めようとすることは、良い社会を維持したり取り戻したりするためには不可欠なのだ。