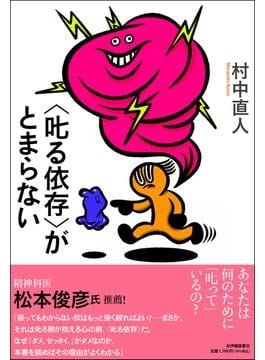
ISBN: 9784314011884
発売⽇: 2022/02/04
サイズ: 19cm/205p
「〈叱る依存〉がとまらない」 [著]村中直人
執拗(しつよう)に叱責(しっせき)を繰り返す上司がいたとする。先輩やコーチ、先生、親でもよい。
私にもいた。小学校の家庭科の先生。下手な裁縫をなじられ、人前で「悪い手本」をやらされた。でも、ときに優しい言葉をかけてくれる。「自分のためを思って」と考えることにしてきたが、あるいはこれだったのか?
脳はだれかを罰することで心地よくなり、充足感が得られる。結果としてだれかを叱れずにいられない状態に陥る。まだ仮説の域は出ていないようだが、一言でいえば、これが本書の根底にある考え方である。
著者が定義する「叱る」とは、言葉によって「ネガティブな感情体験を与えること」であり、その前提条件として、権力のある人がない人におこなう「非対称性」を挙げる。
その言葉は強い調子である必然はなく、丁寧な口調で不安や恐怖を感じさせることはいくらでも可能だ。「権力」の方も、自分で勝手に思い込んでいる場合を含めれば、広範な捉え方ができる。社会問題にもなっている、わずかなことで店員を叱りつける客の存在も本書で説明できそうだ。
それでも「叱らないと伝わらない」「忍耐力が身につく」と思うかもしれない。だが、理不尽な我慢を強いて身につくのは無力感やあきらめの方だ。被害者が加害者からなかなか離れられなくなる「トラウマティックボンディング」という現象にも合点が行った。
「処罰感情の充足」が社会制度に組み込まれるともっとやっかいだ。むろん犯罪の被害者が抱く自然な処罰感情は尊重されるべきだが、本書が事例として挙げるように、社会が厳罰化に傾けば更生や再犯防止という目的を損ないかねない。
正直いえば、私自身、本書で「ほとんど意味がない」とされる「怒ってはだめだが、叱るのは必要」と考えていた一人だ。社会には「叱れる大人」が必要だと思ったこともある。示唆に富む一冊である。
◇
むらなか・なおと 1977年生まれ。臨床心理士・公認心理師。著書に『ニューロダイバーシティの教科書』。












