「古代末期のローマ帝国」書評 衰亡か変容かを超えゆく理念
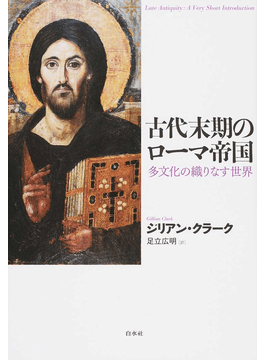
ISBN: 9784560084090
発売⽇: 2015/02/15
サイズ: 20cm/207,15p
古代末期のローマ帝国―多文化の織りなす世界 [著]ジリアン・クラーク
古代末期に関する研究はここ50年で急速に進展した。ギボンが18世紀後半に『ローマ帝国衰亡史』で唱えたローマ帝国は蛮族(ゲルマン民族)の侵入で「衰亡」したという定説に挑戦する一派が現れたからだ。1970年代に台頭した彼らは、ローマは没落したのではなく、新しい社会に「変容」したと主張する。
本書は「古代末期とは、ローマの没落と存続の双方を経験した時代」と位置付けているように、どちらかの説にくみするものではない。また、本書を読むと没落説、変容説どちらが正しいかという問題は些末(さまつ)に思える。歴史家が「過去の諸社会の何を評価するか」で違ってくるからだ。
古代末期の終わりは800年カール大帝の戴冠(たいかん)式とされる。始まりにはいくつかの考え方がある。本書にいう「善にも悪にもなる力としての宗教」を重視するなら、最初のキリスト教徒皇帝、「コンスタンティヌスの治世が始まる4世紀初頭」になるだろう。
キリスト教は、476年西ローマ帝国皇帝の廃位のあと、「共同体のリーダーとしての司教」などを覇者の社会に提供し、「ローマとポスト・ローマ(衰亡説における中世)期の社会を変容させた」。非ローマ人の国でもローマ文化は続いたのだった。
この時代の偉大な哲学者アウグスティヌス(354〜430)が『神の国』を説いたのは「善に作られたが人間の罪によって歪(ゆが)められた世界」すなわちこの世において「人々は自分勝手に支配しようとする」からである。どの時代にも希求されるのは平和と秩序であり、正義である。
古代末期はその与え役をキリスト教が担い「断絶」と混乱を防いだ。アウグスティヌスによれば、誰かが神の国と地上の国のどちらに属しているかは、「何を愛するのか」で決まる。神か欲望なのか。21世紀の現在も同じだ。何を愛するのかによって、変容か断絶なのかが決まるのだ。
◇
足立広明訳、白水社・2484円/Gillian Clark 英国の歴史学研究者。ブリストル大学名誉教授。












