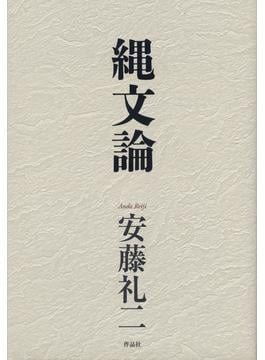
ISBN: 9784861829307
発売⽇: 2022/10/31
サイズ: 20cm/330p
「縄文論」 [著]安藤礼二
「縄文」と聞くと、即座に縄文土器を思い浮かべるかもしれない。だが、本書での縄文はそれとはかなり趣を異にしている。冒頭の連想は、かつて考古学の「研究」資料であった縄文土器を、縄文人による「表現」として鑑賞の対象に据えた芸術家、岡本太郎の「縄文土器論」によるところが大きい。実際、本書でも随所で岡本太郎の名が登場する。だから先の連想もまちがっているわけではない。しかし、こうした連想が、いつしか現代社会の抑圧から逃避するために、縄文を一種のユートピア視する動向を生み出したのも事実だ。本書はそうした縄文の弛緩(しかん)を真っ向から拒み、「縄文」という概念を、もっとはるか「根源」から再発見する。
この根源は、ユートピアであるどころか、「最も貴重な生命が直接やり取りされていた」「言葉の真の意味で、『残酷』な世界」とともにある。同時にそれら「原型的な人々は、定住しながらも根源的な生活様式、狩猟採集を捨てなかった」。だからこの意味での「縄文」は、平穏と安定をなにより求める私たちの生活からかけ離れている。
だが一方で、本書にあるとおり「縄文」は日本列島で一万年以上持続し、他方、しばしば一対で語られる「弥生」は、現在の社会と暮らしの原型を作った「弥生から現在まで」見ても、せいぜい三千年しか経っていない。時間の尺度で言えば、「縄文」は、根源であるがままに私たちの内なる隣人でもあるのだ。「原型的な人間たちが営む根源的な世界、すなわち『芸術』は現在においても生き続けている」。本書での「縄文」とは、なにより「今日の芸術」(岡本太郎)の問題なのだ。
そのために著者は、「『縄文』を時間と空間の限定から解放する」。人類と芸術の「はじまりの場所」へ向けてのこの解放の旅は、「洞窟」「草原」「大海」「南島」などの具体的な「場所」を通じ、フローベールからヘッケル、西田幾多郎から今西錦司、テイヤール・ド・シャルダン、ベルクソンからラフカディオ・ハーン、鈴木大拙、スウェーデンボルグ、フーリエ、そして吉本隆明から折口信夫らの脳髄を縦横に駆け抜け、それらの「類似と照応の詩法」(ボードレール)、「あらゆる感覚の錯乱」(ランボー)を通じ、従来の「縄文」の概念をめくるめく覆していく。
岡本太郎は芸術に進化はないと喝破した。としたら、芸術にも「はじまりの場所」があるに違いない。いまここにいながらにしてそこに還(かえ)ることこそが、本書が冠する「縄文」の別名に違いない。
◇
あんどう・れいじ 1967年生まれ。出版社編集者を経て、文芸評論家、多摩美術大図書館長・教授。2015年に『折口信夫』でサントリー学芸賞と角川財団学芸賞。著書に『大拙』『熊楠 生命と霊性』など。












