「惑う星」書評 宇宙大で問う人間存在の複雑さ
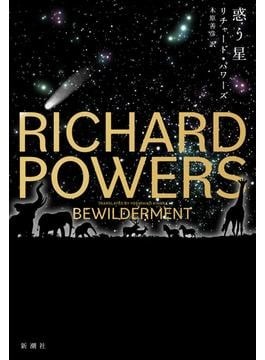
ISBN: 9784105058777
発売⽇: 2022/11/30
サイズ: 20cm/387p
「惑う星」 [著]リチャード・パワーズ
パワーズは分断されたこの世界に「物語の力」という強大な磁力を持ち込もうとしているようだ。『惑う星』を読めば、地球の一時的な間借り人に過ぎない私たちがなぜ些細(ささい)なことで争うのかと疑問を持つ。一方で、人間という存在の複雑さにもあらためて感じ入るのだ。
地球外生物探査の研究者であるシーオは、2年前に妻アリッサを亡くしてからは息子ロビンと2人暮らしだ。9歳のロビンは難しい少年で、並外れた集中力の持ち主ながら、適応障害を抱える。感情制御が下手で同級生にけがを負わせる事件も起こす。向精神薬の投与のかわりに父親が頼ったのは、妻の古い友人。脳神経学者の彼はアリッサの脳波データを使った実験的なトレーニングを提案する。
最愛の母とのシンクロはロビンの情緒を著しく安定させた。「“僕らだ”っていう感じかな」と本人も機嫌がいい。ただそれは知能の平準化を超え、知るはずのない古い記憶を話したり、母が熱心だった動物保護運動に同期して強い傾倒をみせたりもする。父は不気味さを覚えずにはいられない。
父子は以前より架空の惑星について話しこんできた。地球にそっくりだが自転が安定しないドヴァウ、環境変化がなさすぎるスタシス、惑星自体が姿を隠すアイソラ……。それらにも確かに生命体はある。地球外には知的生命体がいないように見える「フェルミのパラドックス」は、人間を絶対視する地球の価値観と同時に、多様性への無理解も浮き彫りにする。本当に人間だけが知的なのか?
物語は、ロビンのカリスマ化や専制的な大統領の学問分野への介入や絶滅危惧種など現代的なトピックを多彩にちりばめ、人間の営為とは何か、読者に考えさせる。それは警告の色を帯び、胸に迫ってくる。
「僕たちすごいところにいるよ。信じられる?」
人類は誤った道から引き返せるだろうか。地球の見方を変える傑作である。
◇
Richard Powers 1957年生まれ。米国の作家。著書に『オーバーストーリー』『エコー・メイカー』など。












