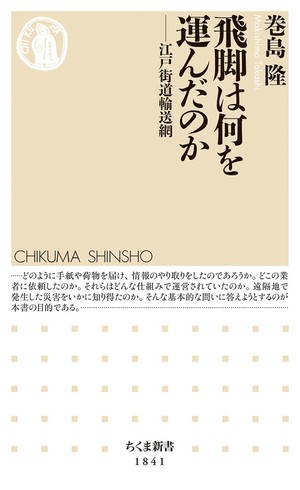
ISBN: 9784480076687
発売⽇: 2025/02/07
サイズ: 17.3×1.9cm/416p
「飛脚は何を運んだのか」 [著]巻島隆
本書は日本の飛脚制度の発達史だが、著者の視点の広さと深さにより、あらゆる分野を網羅した江戸期の社会史になっている。飛脚は平安末期の戦線報告に端を発し、鎌倉期に制度化に向かい、江戸期にはビジネス化していったという。
特に江戸期の飛脚にはその事業形態、経済や物量の動き、通信、さらには災害での輸送物の消失に対する賠償など、現代の企業の芽は全て揃(そろ)っていたことが詳述されている。こうした見方には説得力がある。戦国体制に戻さない知恵でもあったといい、それが国内流通を推進し、メディアの役も兼ねたと指摘する。
江戸期に飛脚を利用した人々は、実に多岐にわたる。幕府、大名家、旗本、商人、村・町名主、文人などだ。著者は曲亭馬琴の日記を分析し、この戯作(げさく)者と大坂の板元などとのやり取りから、飛脚業者(例えば京屋弥兵衛)の拡大と輸送網の広がりを見ていく。京屋の発展史によって経営母体がどう変わったかがわかる。江戸の大名屋敷に出入りするようになり、明治に入ると会社化もした。
飛脚賃はどうだったのだろうか。業者は料金表を明確にしている。江戸から京都・大坂は東海道を使い、荷物一貫目(3.75キログラム)は6匁(もんめ)5分(約1万4千円)。御状(手紙)一通は2分だった。かけそば一杯強分で、江戸から上方まで運んでくれたわけだ。
江戸期には、町飛脚はチリンチリンと鈴をつけて走っていた。その音を聞き、庶民は手紙などの輸送を頼んでいた。庶民も気軽に利用する様は、今の宅配便の原点の風景に通じているのだろう。
とはいえ、飛脚は道中で盗賊に出合うなどの怖さもある。特に金や反物が狙われるが、防備や弁償も具体的で、社会慣習と一体化していた。
本書によって、戦乱なき時代がどのようにヒト・モノの交流を活発にし、制度を確立していくかが理解できる。著者の視点に全面的に共感できる読後感が心地良い。
◇
まきしま・たかし 1966年生まれ。地方紙記者を経て、桐生市史編集委員会専門委員。著書に『江戸の飛脚』『上州の飛脚』など。












