「徳川家康―われ一人腹を切て、万民を助くべし」書評 死後の体制転覆を恐れた理由
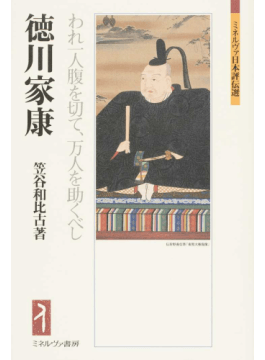
ISBN: 9784623078691
発売⽇: 2017/01/15
サイズ: 20cm/435,13p
徳川家康―われ一人腹を切て、万民を助くべし [著]笠谷和比古
中華帝国や朝鮮王朝のように、儒教が体制を正当化するイデオロギーとして定着していれば、皇帝や国王は「天」から支配の正統性を与えられる。そこでは武力ではなく、儒教的な徳をもつことが「民」を統治するための重要な条件となる。たとえ武力がなくても、支配者が「民」から徳をもっていると思われている限り、王朝の交代は起こらないものとされた。
だが、日本では中国や朝鮮ほど儒教が政治思想として定着しなかった。このため天下を統一しても、支配者は武力を解くことができず、自らが死んだ途端に体制が覆されるのではないかという幻想におびえ続けなければならなかった。
本書を読むと、徳川家康こそはこうした幻想にとらわれた最大の人物ではなかったかという思いに襲われる。
家康は決して、関ケ原合戦に勝って江戸に幕府を開いた時点で幕藩体制と呼ばれる全国的な支配を築き上げたわけではなかった。大坂(現・大阪)には依然として豊臣秀吉の側室、淀殿とその息子の秀頼がおり、幕府成立後も権威を保っていた。家康が西日本に全く徳川系大名を配置しなかったのも、東日本は徳川家と将軍が支配するのに対して、西日本は豊臣家と秀頼が支配する「二重公儀体制」を構想していたからだ。
しかし家康は同時に、自らの死をきっかけとして、この体制のバランスが崩れ、関ケ原合戦の負け組であった大名が秀頼を戴(いただ)いて徳川討伐の軍を起こすのではないかと考えていた。家康が大坂の陣で豊臣家を滅ぼしたのは、それを未然に防ぐためであったのだ。
見事な考察である。長年にわたり近世史を研究してきた著者ならではの魅力的な説と言ってよい。家康は江戸に幕府を開いてから将軍職を息子の秀忠に譲ったが、なお大御所として実権を握っていた。一方、大坂城では秀頼の生母に当たる淀殿が後見として権力をもっていた。つまり二重公儀体制とは、東日本を「父」が、西日本を「母」が支配する体制と言い換えることもできるのではないか。
家康は源頼朝を尊崇し、鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』を愛読していた。そこには頼朝の死後に頼朝の正室で源頼家や実朝の生母だった北条政子が支配者となり、承久の乱に際して北条の軍勢を鼓舞する勇姿(ゆうし)が描かれている。本書の説が正しいとすれば、家康が最も恐れたのは自らの死後、淀殿が北条政子のような存在になることではなかったか。大坂の陣とは、豊臣家を武力で滅ぼすとともに、「母」の権力を封じることで「父」の支配を確立させるための戦いだったように思われてならない。
◇
かさや・かずひこ 49年生まれ。国際日本文化研究センター名誉教授(日本近世史、武家社会論)。著書に『主君「押込」の構造』『近世武家社会の政治構造』『士(サムライ)の思想』など。












