「死の都の風景」書評 収容所での生活 「美」と「郷愁」
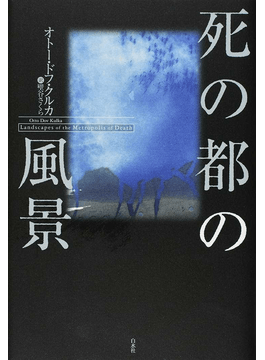
ISBN: 9784560083529
発売⽇: 2014/04/25
サイズ: 20cm/184,9p
死の都の風景——記憶と心象の省察 [著]オトー・ドフ・クルカ
ユダヤ系の歴史学者である著者は、十歳のころ、アウシュビッツの「家族収容区」へ入れられた。長い年月を経て、はじめてその経験を語ったのが本書だ。
「家族収容区」は、赤十字の査察団の目を誤魔化(ごまか)すための施設で、大人と子どもが一緒に暮らし、私服を着ることが許された。歴史の授業も、劇や合唱(「歓喜の歌」!)の練習時間もあった。だが査察が終われば、半年後には全員がガス室に送られる。その運命を、みんな知っていた。著者はたまたまジフテリアに罹(かか)り、病棟に移されたので、ガス室送りを奇跡的に免れた。
アウシュビッツの悲惨で残酷な実状は、これまでにも多くの書物が伝えている。本書も淡々と収容所内での生活を語るのだが、そこには不可思議な「美」と「郷愁」が感じられる。
鉄条網に本当に電気が通っているのか、友だちと試して遊んだ記憶。病棟で死の床にあった青年から、ドストエフスキーの『罪と罰』をもらい、貪(むさぼ)り読んだこと。遺体を燃やす煙が煙突から絶え間なく上るかたわらで、収容された人々はなんとか楽しみを見出(みいだ)そうとしつつ、期限付きの「日常」を送っていた。絶望のなかで、子どもたちに大切なことを伝えようとするひとも、たしかに存在した。
著者は、少年の日にアウシュビッツで見た夏の青い空を、美しい永遠の風景として心に刻み、何度も何度もそこへ還っていく。「すべてを支配する大いなる死が隆盛を極める中で感じる美から、逃れるすべはないのだ」
あふれかえる死と残酷のなかでも、著者の美と文化への感性、思考しつづける強靱(きょうじん)な知性は、決して失われなかった。そこに希望を感じると同時に、収容所を「故郷」として生きざるをえない、著者の壮絶な経験を思って、粛然とした。なぜ、と神や良心の存在について真剣に問わずにはいられない一冊だ。
◇
壁谷さくら訳、白水社・2376円/Otto Dov Kulka 33年生まれ。ヘブライ大学名誉教授(歴史学)。












