小島信夫「ラヴ・レター」書評 この相変わらずの新しさは何だ
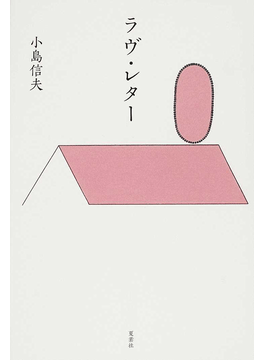
ISBN: 9784904816110
発売⽇:
サイズ: 20cm/269p
ラヴ・レター [著]小島信夫
第三の新人、という言葉をあえてここで使おう。日本文学史における分類としてではない。七十を過ぎ、八十九歳までに書かれた小島信夫の単行本未収録短編を読みながら、この相変わらずの新しさは何だろうと目をみはるような思いにとらわれるからだ。
第一でも第二でもない。むしろ常に分類からはみ出すゆえに、いつまでも新人であらざるを得ない故・小島信夫。
例えば、老作家と自分らしき者を呼びながら始まる小説は、決しておのれを把握しきらない。途中で急に「みたいだった」と突き放す。
また、幾つかの作品はあたかも突然ハシゴを外されるように終わり、読者は慣性の法則みたいなものでつんのめりながら思わずふっと笑うだろう。それは未知のエンディングを知る体験であり、既知の小説形式を捨て去る喜びにも通じている。
私小説や随筆のようでいて、短編群がそう簡単にジャンルにおさまらないのは、筋が要約出来ないような次元で文章が推移するからでもあり、弱ったことにそれがまたするすると楽しく読めてしまう。読めるが、時にいつの間にか何を言っているのかわからなくなる。どこから文意を取れなくなったのか、と我々は何度もその平易な言葉の前で行きつ戻りつする。そして読み切る。これこそ、小説の理想のあり方ではないか。
ある短編で作者は創作についてこう表現する。「小説としてマトマリがよい、ということにはこだわらなくて、気持のよい感じだ、と思えるもの。その中では、思い切った自由ともいえるものが出来るといいね」
いかにもたやすそうに小島信夫は極意を開陳する。だが、実際は物語の遠近法がゆるやかに外れ、主語は分裂する。とぼけた調子でベケットのようなことを行う。
国語を揺るがすもの、それが文学だと我々は永遠の新人から諭され、ふっと笑う。
◇
夏葉社・2310円/こじま・のぶお 1915年生まれ、2006年没。作家。『抱擁家族』『残光』など。












