「地上の飯―皿めぐり航海記」書評 身体的行為としての食の歴史
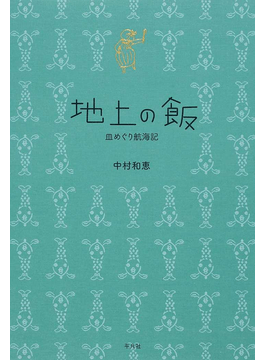
ISBN: 9784582835588
発売⽇:
サイズ: 20cm/189p
地上の飯―皿めぐり航海記 [著]中村和恵
飯を食って文化の違いを論ずる——そんなこと、もう誰もが書いている。海外体験を描くとき、異文化の食にいささかでも衝撃を受けない人はないからだ。辺境の飯、伝統的な飯、そして都市の最先端で生み出される飯。書店のノンフィクションの棚に立てば、よりどりみどりだ。
しかし、この本はそうしたものとは一線を画している。書きようはやわらかいが、噛(か)めばかちんと硬いものに当たるからご注意。読者は「食の異文化」というテーマを超えた問題に直面させられるからだ。飯には文化的な背景が必ずひそむものだが、中村さんが飯を求めてめぐる土地の多くは、かつて植民地だったところや、いまだにヨーロッパの国に領有されているところである。
植民地の宗主国が持ち込んだ文化と土地固有の文化とが混成し、独自の文化が作られる。これを「クレオール文化」と呼ぶ。飯とて、例外ではない。中村さんのフィールドは、カリブの国々やタヒチなどのクレオール文化圏である。ヨーロッパの白人が奴隷を送り込み、先住民の暮らしを圧迫した歴史が飯に刻みつけられている土地ばかりなのだ。
たとえば、干鱈(ほしだら)。北の海でとれる魚が、なぜかカリブ海で常食されていた。日本に来る前カリブにいたラフカディオ・ハーンも食べていたという。生鱈ではなく、干鱈が旧植民地の食料として根付いた背後には奴隷制が関わっていたのだ(詳しくは本書で)。
中村さんは、こうした植民地における支配と被支配の問題を激しく糾弾するのではなく、あくまで飯とその歴史を「食べる」という身体的行為を通じてあぶり出してゆく。
「ゾンカ」という香水のかおりから、消滅したシッキム王国に至る章では、国境が不変ではありえないことを痛感させられた。いろいろな意味で日本の安全神話が崩れた今こそ、読んでほしい本だ。
◇
平凡社・1680円/なかむら・かずえ 66年生まれ。明治大学教授、詩人。著書『降ります』など。












