「知の棘―歴史が書きかえられる時」書評 「歴史はいかに可能か」問う
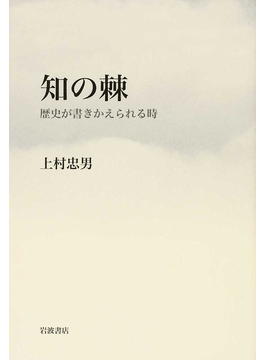
ISBN: 9784000238670
発売⽇:
サイズ: 20cm/196p
知の棘―歴史が書きかえられる時 [著]上村忠男
時代に歴史が満ち満ちていた六〇年代を遠く離れて、高度にシステム化された資本主義社会のいまは「歴史の暮れ方」であると著者は書く。その歴史なき時代に、歴史認識はどんなかたちで可能になるのだろうか。
ベネデット・クローチェに従えば、すべての歴史は現代史であり、現在の生の実践的な欲求や関心に促されてつくられる。三木清も、歴史は現在が端緒になるゆえに、つねに書き換えられる内的必然性をもつという認識に立って、それを叙述するロゴスとしての歴史はたんなる過去の出来事の模写ではなく、叙述者の主体的事実の表出である、とした。歴史の叙述がイデオロギーになる所以(ゆえん)である。
また、かくて歴史は支配者=勝利者の所有物ともなるのだが、たとえばこれに対抗してベンヤミンは、個人が支配者の歴史学から過去を奪い返し、生きたかたちで未来へ開くための能動的な「回想」を唱えた。またさらに、実体論的な国家観に代わって、国家や国民を想像力の構成物として捉えるとき、想像の共同体にリアリティーを与える言語装置としての物語が要請されることになるが、それは国民形成の物語をつくるということではない。むしろ国民の数だけ差異をもち、他者と自己が対峙(たいじ)する言語の本質に従って他者を抑圧する〈原—暴力〉に満ちることもある、生きた声のざわめく空間が生起するのである。
さて、歴史はいわば他者との関係の記述であるが、他者とはそもそも自己が知ることの出来ないものではなかったか。そこから高橋哲哉が「記憶されえぬもの」と呼び、アーレントが「忘却の穴」と呼んだ表象の限界へと、著者の思索は進んでゆく。すなわち自己言及的でしかあり得ない私という主体を、いかにして他者へと開いてゆけるか。現在にけっして還元できず、語り得ない他者との関係によって現在が異化されるような歴史はいかにして可能か。評者は歴史学には不案内ながら、認識主体の限界を内破せんとして、現在の生に身を投じる著者のリオタール的な能動に共感をもった。歴史認識は生そのものである。
評・高村薫(作家)
*
岩波書店・2520円/うえむら・ただお 41年生まれ。学問論・思想史家。『ヴィーコ——学問の起源へ』。












