森於菟「耄碌寸前」書評 老いを照らす乾いたユーモア
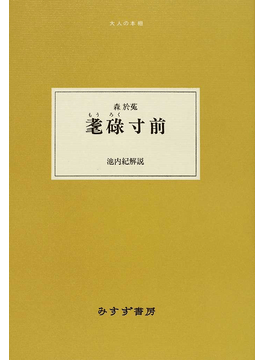
ISBN: 9784622080831
発売⽇:
サイズ: 20cm/184p
耄碌寸前 [著]森於菟
「父の名をはずかしめたくないので、己の能力の限界を知った私は文学よりもむしろ基礎医学の研究生活を選んだ」
収録された二十一の随想、そのうち一編の冒頭である。虚飾を嫌う清潔で抑制のきいた一文に人となりの表出があり、瞠目(どうもく)した。「父の名」は森鴎外。
鴎外は人間味豊かな家庭人だったが、子供たちにとって厳しい教育者でもあった。於菟(おと)、茉莉(まり)、杏奴(あんぬ)、類(るい)。二男二女は学問や芸術への情熱を烈(はげ)しく求められ、あげく劣等意識や絶望感もたっぷり引き出された。さらに、長男於菟の育ちかたは入り組んだ。生母は一年余りで離縁された先妻、登志子。父方に引き取られるが里子に出され、十三歳のとき鴎外一家と同居をはじめる。しかし、父の若い再婚相手と育ての親である祖母との不仲に巻きこまれた。そして冒頭の決意をもって医学を選び、解剖医学の第一人者となる。
於菟はみずから文学者への道を封じたが、昭和十一年、台湾に赴任したころから盛んに随想を書きはじめた。四十代後半、しがらみから解放された南の別天地だったところに屈託をかんじる。しかし、父を描くその文章は、於菟にしか紡ぐことができないものだ。控えめながら事実をゆるがせにせず、家庭不和に懊悩(おうのう)する姿をとらえて文豪の真実に迫る。その筆致は紛れもなく鴎外文学の嫡子(ちゃくし)。
かくして七十二歳のとき書かれた表題作「耄碌寸前」、この老いをめぐる随想の独自の持ち味はどうだろう。「私は自分でも自分が耄碌しかかっていることがよくわかる」「この調子では死ですら越えて夢見そうである」。乾いたユーモアや諧謔(かいぎゃく)が顔をのぞかせるが、韜晦(とうかい)でも恬淡(てんたん)でもない。「寸前」の二文字に精密さを潜ませ、透徹した視線でみずからの老いをすみずみまで照らしだす。そこに浮かぶのは、「愛すべき死体達」と親しく会話を重ねてきた解剖学者のつつましやかな佇(たたず)まい。
森於菟の文章世界は鴎外の遺産だが、いっぽう父を離れて愛されるべき陰影に富む。その稀覯(きこう)な味わいに光を当てて編まれた一冊であることがうれしい。
評・平松洋子(エッセイスト)
*
みすず書房・2730円/もり・おと 1890〜1967。台北帝大医学部長。『父親としての森鴎外』など。












