「労働の思想史」書評 苦役か喜びか 古代からたどる
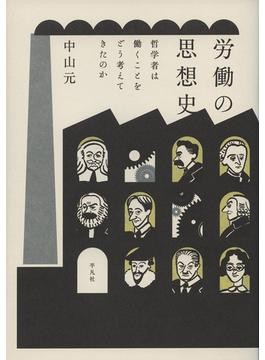
ISBN: 9784582703658
発売⽇: 2023/02/24
サイズ: 19cm/326p
「労働の思想史」 [著]中山元
「やりがい搾取」という言葉をよく聞くようになった。「世の中に役立つ仕事だから」「あなたの成長にプラスになるから」などと言いつつ、安い賃金でこき使うことだ。働くのはカネのためだとみなが割り切っていれば、成立しない行為である。それほど私たちは、働くことに意味や喜びを求めているのだろう。
労働は苦役か、喜びか。昔から宗教家や思想家たちが考え続けてきた。その軌跡を丁寧にたどる本書は、いわば労働観の通史である。古代のユダヤ・キリスト教の世界では、労働は神が人間に課した「罰」だった。しかし中世に修道院ができると意味あいが変わる。院内で聖職者たちが畑仕事に従事し始めたことで、労働は魂の救済という色彩を帯びてくる。
19世紀、資本主義勃興期の過酷な労働に向き合ったのが、思想家・革命家のマルクスだった。労働とその生産物が、労働者にとってよそよそしいものとなっている。彼はこの状態を「疎外」と呼んだが、それは自分の手で何かを作る労働には本来喜びがあるはずだという信念の裏返しだ。マルクスの社会主義思想には、ぎりぎりのところで労働を肯定する発想がある。
著者によれば「近代にいたるまでの労働の歴史は、労働にどのようにして肯定的な意味が与えられるかという歴史でもある」。では現代のサービス業で笑顔や忍耐を切り売りする「感情労働」については、どう考えるべきか。人工知能に働く場が奪われるなら、どう対処すべきか。そこは著者も考えあぐねているように見える。現代人すべてが引き受けるべき問いであろう。
著者は哲学者であり、哲学や社会科学の古典的名著の新訳を次々にものした翻訳家でもある。本書で登場する顔ぶれは、一見労働の話とは縁の薄そうなホッブズやハイデガー、フロイトなども含め、百花繚乱(りょうらん)だ。自分の働き方を見つめ直すヒントが見つかるかもしれない。
◇
なかやま・げん 1949年生まれ。哲学者、翻訳家。著書に『フーコー 生権力と統治性』など。












