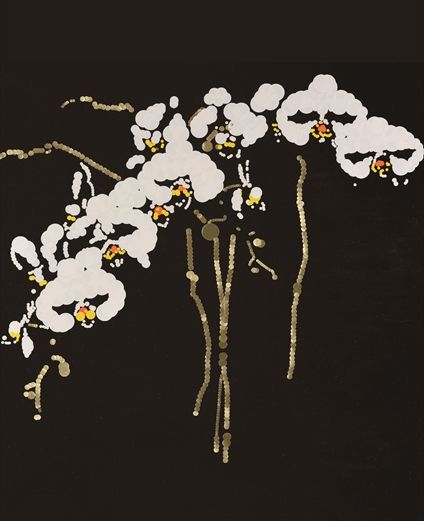
声の大きい者たちの言葉で、この世界は埋め尽くされている。そう思った途端に、私たちの人生は貧しくなる。ならば、ふとした瞬間に漏らす言葉は、あるいは心の中に生まれる想(おも)いには意味がないのか。そうではない。文学は、そうした微(かす)かな声に耳を傾ける。そして私たちに、生き続けることの意味を与えてくれる。
◇
井戸川射子『曇りなく常に良く』(中央公論新社)を読み始めた途端に、鳴り響く五人の女子高校生たちの声の中心に読者は放り込まれる。最初は区別がつかないが、じっくりと聞いているうちに、一人ひとりの苦しみや優しさが見えてくる。たとえばハルアの両親は再婚同士だから、彼女と弟や妹は顔が似ていない。家でも常に気を使い続ける彼女が唯一ホッとするのは、母親と二人で出かけるときだ。だがそんな機会はめったにない。
おそらく発達障害のあるシイシイは、人の表情が読み取れない。友達がドッと笑っても、その理由が理解できない。だからなんでも気がつくハルアが羨(うらや)ましい。だが彼女にそう言われてハルアは落ち込む。一方、家が貧しいウガトワは部活もできず、バイトに明け暮れるしかない。
彼女たちの本当の思いを聞いてくれる人は、自分たち以外、誰もいない。教師は一般論で励ますだけで、親は自分たちの苦しみで精一杯だ。だから彼女たちは互いの辛(つら)さに耳を傾ける。もちろん、そのことで根本的な解決は訪れない。だが、少なくとも今日一日は生きられる。
『こちらあみ子』以来、今村夏子は子どもの心をすくい取るのがうまい。短編「カラーハート」(「群像」五月号)の主人公、小学生の創太が最近、気になっているのは、姉の同級生の麻梨乃だ。プロの漫画家を目指す彼女は、なぜか漫画の表紙のみを描き続けている。そこに記されたタイトルはこうだ。「ふしぎのプリン」「モードショック!」「メモリーラブ」。しかも眼鏡姿の老人は体育館に住む妖精で、人間は天使、ねずみは魔女だ、と麻梨乃は言う。
分からないと思うほど、創太は麻梨乃に惹(ひ)きつけられる。そしてだんだんと彼女をめぐる事実に気づく。創太の姉が、世話をしているふりをして、実は麻梨乃をいじめていること。本当は麻梨乃は速く走れるのに、姉の前では足が遅いふりをしていること。そして麻梨乃の母親はシングルマザーで、大量の酒を飲みながら水商売で頑張っていること。
ある日、麻梨乃は鍵を持たずに出かけて家に入れなくなる。仕方なく公園に独りでいるのを創太と母親らが見つけ、彼女を預かる。だが麻梨乃の母親となかなか連絡がつかない。そうした小さな事件を通じて、創太は自分が理解できる世界の向こうに、様々な問題があることを知る。創太の明るい優しさが、たまらなく貴重に思える。
◇
二〇一七年に若くして亡くなった赤染晶子だが、彼女の魅力は芥川賞受賞作「乙女の密告」だけではない。一枚の布が、作業を通して人の体を包む服になる。その魔法に『初子さん』(palmbooks)の表題作の主人公が出会ったのは子どものころだ。そのまま仕立屋に弟子入りし、やがて彼女は職人として独り立ちする。しかし、好きなことを仕事にしているはずなのに、日々の繰り返しの中で彼女は擦り減っていく。澱(よど)んだ京都の空気のせいか。あるいは、服など金で買えばいい、という世の中の流れのせいか。
彼女にとってまぶしい存在は、パン屋である大家の一人娘、弥生だ。まだ六歳の弥生にはできないことが多い。それでも彼女は気にせず、好奇心のままに走り回っている。やがて弥生は告げる。「初子さん、うちな、自分でお尻ふけるようになってん」。ならば初子さんも変われるかもしれない。
イーユン・リー『水曜生まれの子』(篠森ゆりこ訳、河出書房新社)の表題作における真の主人公は、十五歳で鉄道自殺したマーシーだ。残された母親は言う。なぜ娘は死を選んだのかは分からない。だがマーシーは、母親の心の中で勝手に成長していく。「死者たちが私たちの心や手紙を読んでいないと断言できる人はいない。」と母親が語るのは、今でも常に娘と対話を続けているからだろう。かつてイーユン・リー自身も、息子を自死で亡くした。おそらく親を責める、心無い言葉にも晒(さら)されたことだろう。作者同様、今ここにいない子どもの声を聞き続けることで、本作の語り手である母親は命を繫(つな)ぐ。=朝日新聞2025年4月25日掲載












