保坂和志「地鳴き、小鳥みたいな 試行錯誤に漂う」書評 「私」を表出、息のむ生々しさ
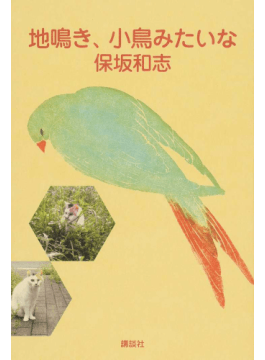
ISBN: 9784062202879
発売⽇: 2016/10/27
サイズ: 20cm/216p
地鳴き、小鳥みたいな 試行錯誤に漂う [著]保坂和志
『地鳴き、小鳥みたいな』は小説で、『試行錯誤に漂う』は随筆。括(くく)りとしてはそうだが、ふたつはともに響き合う。
『地鳴き』に物語はなく、エピソードと随想の合体に近い。「。」で区切るところを「、」を打ってぐねぐねとつづける文体は、初めは奇妙に感じたが、エピソードの衝撃にかき消えた。
最初の一編は若い頃に知り合った先生のこと。あるとき性欲について話していると、突然、先生が進行中の純愛の話をはじめた。「……純愛といってもその先生の話はセックスありだった、セックスのあるないは純愛には関係ない、……」。先生は家族持ちの痩せた「おじいさん」だった。「保坂さんは口が固そうだから言うんですが、」ともらした話を、彼はすぐに同僚にバラし、「浮気!」と盛り上がったが、後にそれを純愛と思うようになる。
表題作は新聞連載した『朝露通信』の話ではじまる。「たびたびあなたに話してきたことだが僕は鎌倉が好きだ、」という書き出しの「あなた」は、読者への呼びかけではなくて、「特定の女性だった、一部の知り合いだけはそれをうすうす感じた、」とつづく。
これらの息をのむような生々しさは、読点が多用されていることに関係あるのだろうか。
文章を読点でつづけると羅列の気配を帯びると『試行錯誤に漂う』にある。物事が意識にのぼるとき、いくつものことが因果関係なく同時にやってくる。文章にそれを書こうとすると直列的にならざるを得ないが、読点を使うと少しだけ並列的になり、意識の働きに近づく。
「私が小説というときの小説は、行為とか手の動きとかにちかい」
原稿用紙に書き、手を動かしながら考える。書きたいことが先にあるのではなく、自分が書いたことに影響されて意識が活性化し、先が見えてくる。
先生の年齢に近づき、作品に描かれる感情や思考や意識には今の「私」が表出している。それを象徴するのは、「私は小説はとにかく作品でなく日々だ」という『試行錯誤…』のあとがきの言葉だ。これを「私にとっては」と言い直すと切実感は後退する。現在の生理がそう言わせているのだ。
どちらの作品からも、聞こえてくるのは「自分はこういう人間だ」という声である。こういう肉体と性格をもって生まれ、それを使ってこういう考えや感じ方を醸成し、書きながらそれを追認していく。だれもに通じるやり方ではないし、読む人も選ぶだろう。けれども、「こういう人間だ」とためらわずに宣言する者がいることで、人の心はどんなに自由になることか。
◇
ほさか・かずし 56年生まれ。「この人の閾」で芥川賞。『季節の記憶』で平林たい子文学賞、谷崎潤一郎賞、『未明の闘争』で野間文芸賞。『カンバセイション・ピース』『カフカ式練習帳』など。












