「人的資本の論理」書評 人の「能力」への見方を再構成
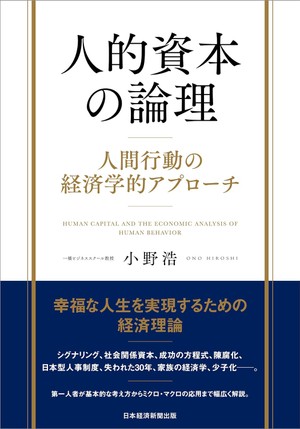
ISBN: 9784296117826
発売⽇: 2024/04/12
サイズ: 21.7×2.5cm/272p
「人的資本の論理」 [著]小野浩
人的資本とは人が持つ生産能力のことを指し、物的資本と同じように投資することで生産能力が伸びると経済学では考える。日本では、ここ数年で「人的資本経営」という言葉が俄(にわ)かに注目を集めるようになったが、人的資本理論自体を日本の読者向けに体系的に説明する本は少なかった。そこで一般読者向けに解説したというのが著者自身による本書の位置づけだが、読後感は「教科書」の趣とは少し異なっている。人的資本理論の進展を肌身で体験した著者の感動が伝わってきて、実に人間臭いのだ。
著者は大学の理工学部で学んだ後に、米国のシカゴ大学で社会学の泰斗であるジェームズ・コールマンとノーベル経済学賞を受賞したゲーリー・ベッカーに師事した。本書には、ベッカーらとの交流のエピソードが随所にちりばめられている。
賃金は労働者側の要因と企業側の要因の両方によって決まるが、労働者側の要因、特に教育年数などの人的資本に関わる要因の影響力が圧倒的に大きい。だが、日本企業では、その企業での勤続年数に比例して賃金が決まる傾向がいまだに強いのに対して、外資系企業では、他の企業での経験も含めたキャリア全体の長さで決まることが多いという。日本企業では、離転職が多いと人的資本を増やせないことになる。
また、人々の間の信頼やネットワークを社会関係資本と言うが、人的資本は社会関係資本を前提にして育まれることを指摘する。日本の労働者は会社内の社会関係資本には恵まれていても、長期雇用によって会社外の社会関係資本は劣化させやすいと言えそうだ。
実証分析を踏まえた豊富な事例から、著者が人的資本理論の含意を突き詰めて考えてきたことがわかる。教科書の効用とは、原理を学ぶことで考えが整理され、普遍的な応用が可能になることだろう。広く教育訓練に携わる人にとって、「能力」に対する見方を再構成してくれる好著だ。
◇
おの・ひろし 一橋ビジネススクール教授。米シカゴ大大学院で博士課程を修了。専門は人材のマネジメントなど。












