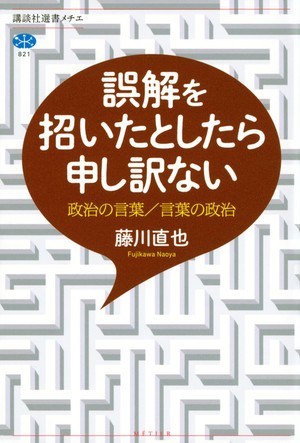
ISBN: 9784065386439
発売⽇: 2025/02/14
サイズ: 13×18.8cm/344p
「誤解を招いたとしたら申し訳ない」 [著]藤川直也
近年では、役に立つことを標榜(ひょうぼう)する哲学の動きがあちこちで起こっている。しかし、申し訳ないが、それらは道楽で哲学をやっている私のような人間にはもうひとつ食指が動かないものだった。ところがどうだ。本書は濃密に哲学的で私の興味を掻(か)き立てながら、しかも役に立つ方向にぐっと身を乗り出しているじゃないか。けっこう驚いた。
とりわけ昨今の政治家の発言に腹を立てたことはないですか? あたしは、もう、なんというか、あのね、言葉を不誠実に使う人っていうのが許せないのね。それでしれっと「私の真意とは異なり誤解を招いたことは大変残念。遺憾に思う」って。本書はそんな実際の具体例をふんだんに取り上げて論じている。
読者としては性急に処方箋(せん)を求めたくなるところだが、そう簡単にはいかない。本書には二つの側面がある。一つは高度に理論的な側面。二十世紀の半ばに、言葉を使うということは社会的な実践であるとして言語行為論という道が拓(ひら)かれ、後に会話における暗黙のルールをもとに会話を分析する理論が提唱された。このあたりまでは教科書的な事柄なのだが、本書を読むとそこからさらに議論が前進していることが分かる。
でも、哲学的関心がさほど強くない人は、本書の実践的側面に目がいくだろう。「そんなつもりはなかった」と逃げようとする者をつかまえるにはどうすればいいのか。
誤解の余地のない言葉遣いだけを認めて、逃げ道を塞げばいい? いや、言外の意味を仄(ほの)めかしたり、少し曖昧(あいまい)なままにしておいたりすることで、日常会話は生き生きと豊かなものになっている。みんなが裁判官や科学者のように喋(しゃべ)れというのはありえない注文だ。では、「そんなつもりはなかった」という発言が適切な場合と不適切な場合を区別する基準は何か。
実情はきわめて複雑で、一言でまとめるなら「ケース・バイ・ケース」としか言いようがない。なーんだ、と言うなかれ。そこに至るまでにこと細かな議論が尽くされている。一筋縄ではいかないこの言語現象を記述し、分析する理論的道具立てを用意することは、実践的にも決定的に重要なことなのだ。
さらに藤川さんは、言語は社会のインフラであり、変革しうるものだとの認識から、言語行為を修正ないし新たに作り出す言語行為工学なるプロジェクトを構想する。私は感嘆の声を上げつつも、でもなあ、哲学と工学を結びつけるのは、どうも私の趣味じゃない。敬意をこめて、新しい哲学の船出を見送りつつ、エールを送りたい。
◇
ふじかわ・なおや 東京大准教授(言語哲学)。著書に『名前に何の意味があるのか 固有名の哲学』。共訳書に『バッド・ランゲージ 悪い言葉の哲学入門』『存在しないものに向かって 志向性の論理と形而上学』。












