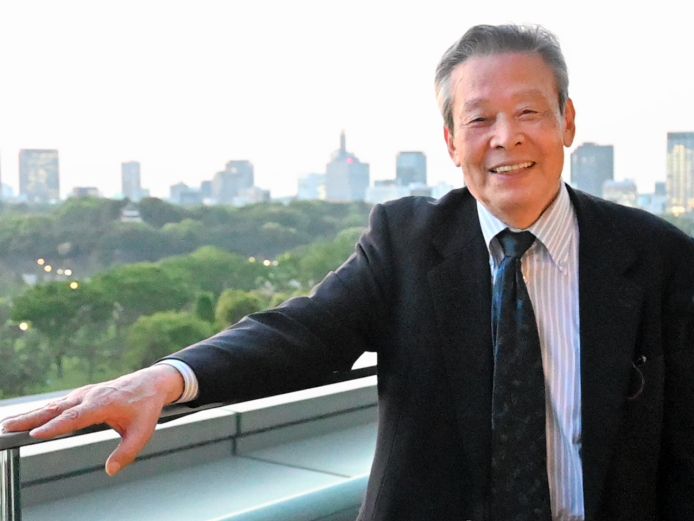
ノンフィクションの大家が、藤沢周平の作品と人をたどった。後藤正治さんが78歳にして初めて刊行した文芸批評の一作。その手応えは、「文品(ぶんぴん)」(中央公論新社)という歯切れ良い書名に映っている。
藤沢作品を経年的に取り上げ、副題は「藤沢周平への旅」。修業時代の秀作「木地師宗吉」や世話物の連作「橋ものがたり」、集大成的な作品「蟬(せみ)しぐれ」……。随所に藤沢の人生模様が織り込まれているのは、半世紀ほど人とその人生を書いてきた後藤さんらしい。
藤沢は1927年生まれ。中学校教員になったが、結核の影響でその道を断念。授かってまもない長女をのこし、最初の妻は早世してしまう。業界紙記者として地道に働き続け、「暗殺の年輪」で直木賞を受けたのは40代半ば。遅咲きと言われた。
「藤沢作品が心に染みるようになったのは、僕自身が中年の坂に差し掛かった頃でした」
読み返しても飽きないのは藤沢の人間観や世界観への共感、と明かす。こんな文章が今作に引用されている。〈失敗の痛みを心に抱くことなく生き得る人は少ない。人はその痛みに気づかないふりをして生きるのである〉
後藤さんの歩みにも曲折があった。学生運動が高揚した69年、デモ隊に加わり、逮捕された苦い記憶。京大卒業後も腰が定まらず、ノンフィクション作品を書くことにようやく光を見いだした。心臓移植など医療をテーマにする中、生命の機微が見えもして、藤沢作品の愛読者になってゆく。
藤沢作品の魅力は、抑制の効いた文体と「文章の吸引力」と後藤さんは語る。天与の才が小説への不屈の取り組みで磨かれていったのだ。
「風景や光の陰り、一見何でもない描写に心象をとけこませ、伝える。語って説かず。書くべきことを知っていた人です」。後藤さんはふと、藤沢作品の忘れられない一文を口ずさむことがある。
97年に他界した藤沢だが、今も根強い人気を保つ。そこに世相の影響もあると後藤さんには見える。「SNSの影響もあり、言ったもん勝ち、というような現象が目立ちませんか。それだけに静謐(せいひつ)な藤沢作品がむしろ新鮮だ、という面もあるのではないでしょうか」
活字、デジタルと媒体を問わず、良き言葉を求める感受性は人々に備わっていると後藤さんは信じている。
藤沢は多くの変わり者を物語に描いたが、品性を欠く者を主人公に据えなかった。書名を文章の品格を表す「文品」と決めたのは、そんな作風への敬意からという。
月刊誌「中央公論」の連載をまとめた。後藤さんには100歳を超えた母と難病を患う妻がいて、取材に出歩くこともままならなくなっていた。ならば、とこの文芸批評に挑戦したが、「二人介護」の日々、浮かんでは消える追憶や愛惜の念があり、たどり直す藤沢作品に随分いやされもした。
そうして受けとめた藤沢の文章が、読み手に潤いを感じさせる。それに呼応する後藤さんの筆もさえ、しみじみとした余韻が残る。小説とノンフィクション。名手ふたりの共演である。(木元健二)=朝日新聞2025年6月18日掲載












