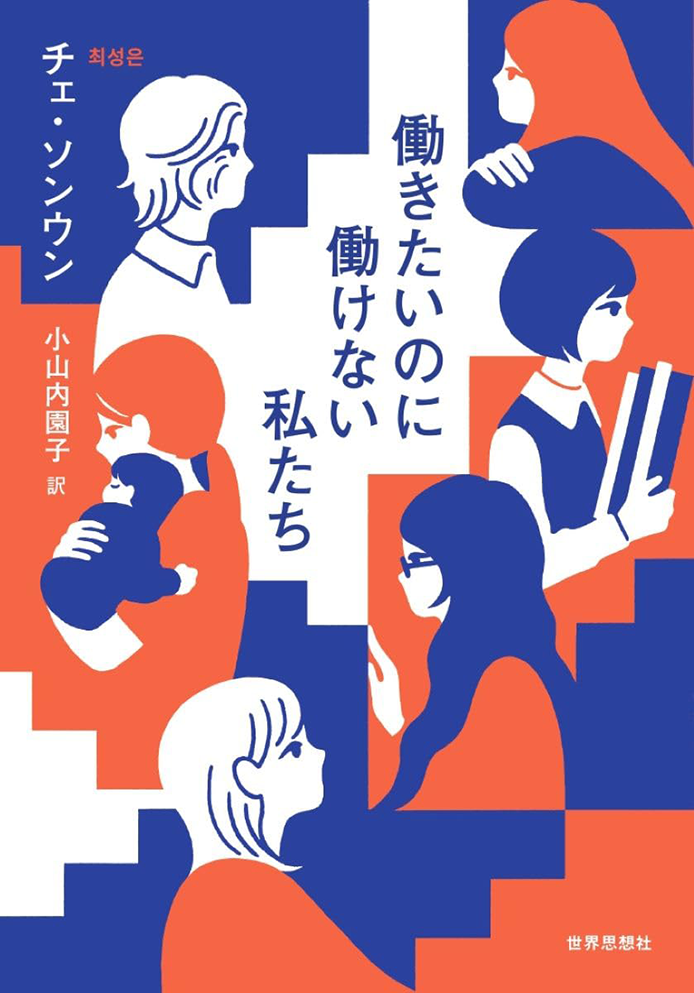
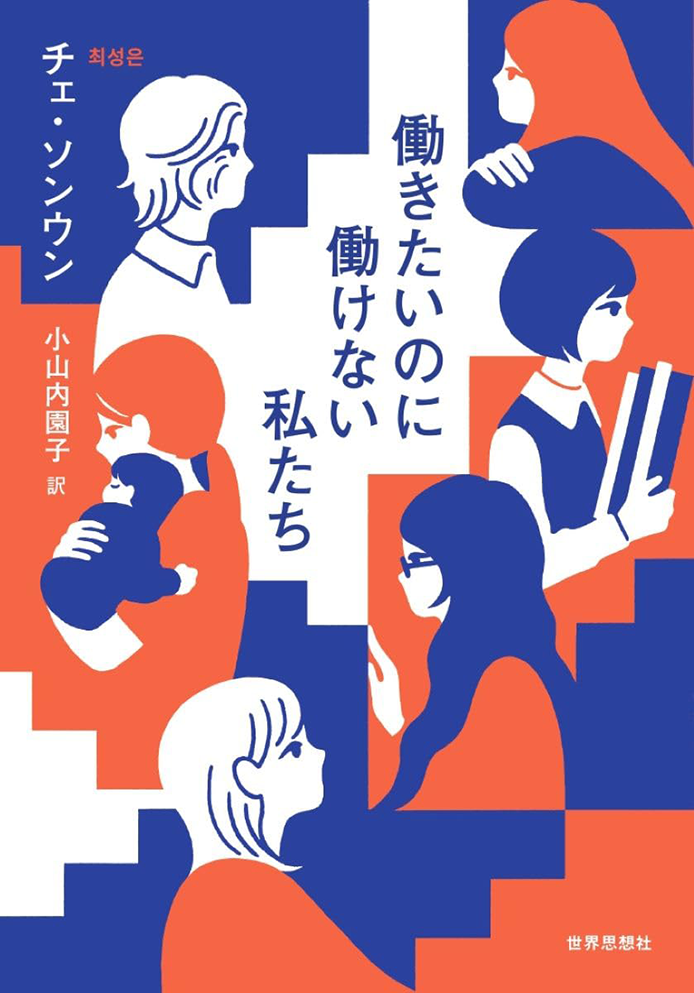
価値観の混乱の中で生きている
――本書はご自身の研究論文が基になっているそうですが、“女性特有の働きづらさ”について研究しようと思った経緯は?
行政学の研究者である私は、実はフェミニズムやジェンダーの問題を深く勉強したことはありません。このテーマを研究したのも、私自身が結婚して子育てをしながら働いている女性だから、ではなかったんです。当時、私は韓国の福祉政策と労働市場を研究する大学の研究センターに勤めていたのですが、そこでは「なぜ韓国は小さな福祉国家なのか」というテーマに沿って、スウェーデンやアメリカと韓国を比較する研究が行われていました。
私も「韓国の労働市場における正規・非正規雇用の格差などの慢性的な問題は、なぜ今のような形になったのか」という研究をしていたのですが、その過程で「なぜ韓国の女性たちは労働市場の周縁にとどまっているのか」「なぜ一生懸命勉強した高学歴の女性たちは、労働市場から一度退場すると戻ってくるのが難しいのか」という疑問を抱いたんです。それが私の博士論文の一部になり、この本の元になりました。
ともすると私がフェミニズムやジェンダーの視点から出発したのではなく、“福祉国家”という大きなテーマの中から私が抱いた疑問の答えを見つけていくという手法を取っていたからこそ、多くの方が「女性特有の働きづらさについて、客観的かつ論理的な根拠を得ることができた」と喜んでくださったのではないかと思います。

――研究論文を一般書として出版することになったきっかけは?
雑誌に掲載された論文が出版社の方の目に留まり、オファーを頂いたんです。元の論文に私自身の経験談を書き加えるという構成にしたのは、編集者のアイデアです。私は研究者なので、個人的な経験を文章にすることには不慣れだったのですが、当時は私も子育ての真っ最中でしたし、ちょうど非正規雇用から正規雇用になったばかりだったので、論文の内容がブレない範囲で、そういった経験を各パートの導入として書くことにしたんです。
――ご自身の経験談に続いて、その裏付けとなる論文のエビデンスが登場するので、非常に説得力がありました。
私はこういった研究を通して、労働市場における構造的な性差別の問題を男女関係なく話し合えるようにしたかったんです。公の場で議論したり、交渉したりするためには、客観的かつ論理的な根拠が必要です。ただ残念ながら、こういった問題で議論すると、女性が男性に対して意見を述べる際に、自分自身がつらい思いをしていることから、自身の経験からくる考えを述べて相手を説得しようとしたり、「どうしてそんなことが分からないの」と感情に訴えてしまったりするケースがあります。
私は研究を通して過去を論理的に考察し、その過去によって形づくられた現在の状況を分析した上で、私たちが今後どうするべきなのか、問いかけたかったんです。それが今、私たちが直面している差別を解消し、より良い世の中を作るために、私にできることだと考えていました。
――プロローグでは本書の内容ともリンクする小説『82年生まれ、キム・ジヨン』についても触れていらっしゃいました。
私は81年生まれで、4人きょうだいの3番目なのですが、キム・ジヨンと同じく弟が末っ子長男です。だからキム・ジヨンの人生には非常に共感しました。私が幼少期に祖父母から一番よく言われたのが「息子が生まれるための3番目の娘」だったんです。男児選好思想の中で、私のように自分の存在価値が“目的のための手段”であると言われて育った人間や、性差別が当たり前の中で育った女性たちにとって、ジェンダー平等という概念は後から学習して身につけたものです。頭では「これは不平等だ」と認識できていても、心の中では「自分のせいではないか」と思ってしまったり、従来の固定観念に引っ張られて「ちゃんと家事育児をやらないと」と思ったりしてしまう。そういう混乱の中で生きているのだと思います。私自身もいまだにそうなんです。だから、この本がそんな方々の力になればと思いますし、個人ではなく国や社会の側が制度や環境を変えていってほしいという思いも込めています。

私たちも自分の幸せを追求するべき
――博士課程を終えて現在の職に就いた後、娘さんの“小1の壁”で苦労したというエピソードは、他人事とは思えませんでした。
娘は少し早くに生まれたので、小柄だったんです。そんな子が朝の登校時に緊張から体が震えてしまうようになって。あの時は自分が働くことがまるでぜいたくのように感じてしまいました。結局、私は自分の出勤時間を遅らせて登校に付き添ったり、子どもが少し落ち着いてからはベビーシッターを利用したりして何とか乗り切ったのですが、シッター代がかさんで、一生懸命働いてもお金は全く貯まりませんでした。放課後の学童保育も私の退勤時間とは合わず、シッターさんにお願いせざるを得なくて。私のようなケースが増えたので、最近では韓国でも学童保育がかなり拡充されたのですが、夏休みなどは利用者のニーズを調査した上で開設されるかどうかが決まるので、全ての学校で運営されているとは言えない状況です。
――日本でも「保育園の時よりも小学校に上がってからのほうが大変」と言う親が増えています。
今、娘は中2なのですが、つい最近も「私も学校から帰ってきたら、お母さんに『おかえり』って言ってもらいたい」という話をされました。実は私も両親が共働きで、“家にお母さんがいる友達”がうらやましかったので、その気持ちがすごくよく分かったんです。だから、やっぱり葛藤しますし、娘には本当に申し訳なく思いました。こういうふうに罪悪感を覚えることが続くと、仕事を辞めざるを得ず、キャリアが途絶える女性が増えるのも当然だと思います。

そうなると別の問題も出てきます。私が大学で講義をした時に、学生たちに「将来、結婚したり、子どもを持ったりしたい?」と聞くと、男子は「育てられるなら3人でも育てたい」と言うのですが、女子は「結婚したくない」「結婚したとしても子どもは持ちたくない」と言うんです。なぜかと聞くと「母みたいにはなりたくない」と。「母も名門大学を出ているのに、私のためにずっと家にいるなんてもったいない。母には感謝しているし、母のおかげで名門大学に入れたけれど、母のように生きるのは嫌」と言うんですよ。
実際、韓国では母親が仕事を辞める理由として“わが子を受験戦争で生き残らせるため”という側面も大きいんです。母親がわが子の学習マネージャーにならなければ、韓国の入試制度の中で名門大学に行くのは難しいんです。
――そう考えると、わが子の前で母親たちはどうするべきなのか、悩んでしまいます。
難しいですよね。ただ、おそらく娘たちが大人になる頃には、私たちが今感じているような罪悪感や葛藤はかなり緩和されると思うんです。というのも、私たちの世代までは「女なら家事や育児をするべき」といった固定観念が無意識のうちに注入されていましたが、世代が入れ変わることで、これまで当然のように思われていたことがなくなっていくからです。例えば、私の夫は比較的家事をするほうですが、料理だけは絶対やろうとしなくて。でも最近の若い父親たちは食事だけでなく離乳食まで作れたりしますし、育児に対しても積極的です。そういった世代交代に伴う意識の変化には私も期待していますし、前向きに考えています。
また、私が仕事と子育ての両立で葛藤している時期に、先輩ママや母からよくこう言われたんです。「今は大変だと思うけど、この時期が過ぎれば、あなたが自分の仕事をしながら幸せでいることが、娘にもいい影響を与えるはず。だから、あまり自分を責めずに自分の仕事を精いっぱい頑張って」と。特に働く母親というのは毎日が反省の連続で、何もかも中途半端になったり、自分の至らなさを痛感したりして、自分を責めてしまいがちです。正直、自分の幸せなんて考えられない人も多いと思います。でも、これは私が自分自身に言い聞かせていることなのですが、私たちも自分の幸せを追求するべきなんだと思います。そうすれば、その幸せが子どもたちにもちゃんと伝わると思うので。

日韓の「ガラスの天井」解消の一助に
――本を読んでいると、韓国の女性たちが感じていることが日本の女性たちとあまりにも似ていて驚きました。
韓国と日本はなぜこんなにも似ているのか。イギリスの時事週刊誌「エコノミスト」が毎年、国際女性デーを記念して発表する“ガラスの天井指数”(女性の労働参加率、男女間の賃金格差、女性役員の割合などの指標を基に算出された指数)で、韓国は29カ国中、長らく最下位で2025年には28位だったのですが、日本も27位なんです。私たちがこんなにも共感できてしまうのには、ガラスの天井がこれほどまでに厚く、社会のリーダー層に女性が少ないという共通点があるからなんです。
――同指数の1位で“女性が働きやすい国”として知られるスウェーデンでも、小さな子どもがいる女性はパートタイム労働を好むものの、パート労働者であっても大半が正規雇用で、“同一労働-同一賃金”の原則があるため、時間当たりではフルタイム労働者と同レベルの給与が保証されているという記述には驚きました。
ただ、それを実現するためには、単に給与体系だけを変えればいいのではなく、労働市場全体のシステムを変えなければいけません。また、私たちが外国の制度をそのまま導入したからといって、その国と同じようにうまくいくわけではないんです。韓国や日本の状況に合わせてアレンジしながら段階的に取り入れていく必要があるのですが、そのためにはガラスの天井を解消して政治の意思決定に女性が関与し、今の制度や社会構造に変化を起こせるようにしていく必要があります。それには私たちが力を合わせて、積極的に声を上げていくことが大事なんです。そういう意味で、この本がガラスの天井を少しでも解消していく一助となればうれしいです。












