「令嬢たちのロシア革命」書評 次代の女性の社会的役割牽引
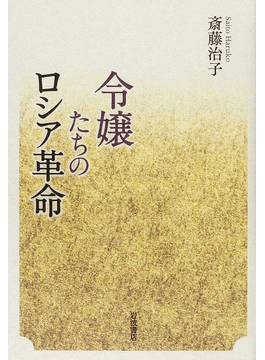
ISBN: 9784000256582
発売⽇:
サイズ: 20cm/314,7p
令嬢たちのロシア革命 [著]斎藤治子
本書を読み進むうちにある感情が熟成されてくる。ロシア革命に至る道筋に顔を出す五人の女性が生き生きと描写され、まるで評伝のような手法が用いられている。著者自身、「歴史学の枠すれすれ、あるいは枠を越えてしまったかもしれない」と書いているが、一般読者にはこの手法こそむしろ著者の意図が正確に伝わるように思える。
五人の女性(生年は1869年から84年まで)は、ロシア社会を含めヨーロッパ社会を代表する知性と行動力をもっているのだが、貴族やオペラ歌手、文官などの家庭で独自の基礎教育を受けた共通点をもっている。その知的環境を知らされると、彼女たちはロシア革命によって自らの信念(女性の自立や社会主義による男女差別の是正など)が果たされたわけではないが、少なくとも20世紀の女性の社会的役割の牽引(けんいん)者になったことは疑い得ない。
五人の一人、イネッサ・アルマンドはレーニンを師と仰ぎつつ、しだいに愛情を寄せるようになるが、家庭を捨て、革命家として自立を目指す中に垣間見える実像を著者は好意的に描く。革命が成ったあとの1920年秋に46歳で病没するが、死直前の日記を引用しつつ、「レーニンと革命と(前夫との)子どもたち、この三つがイネッサの中では一つに溶け合っており、彼女の生きる力であった」と書く。レーニンの悲しみの記述も十分にうなずける。
ロシア革命はドイツから戻ったレーニンが、いわゆる「四月テーゼ」を示し、これが契機となり十月革命が実る。民衆にこのテーゼを知らしめる役を果たしたコロンターイとスターソワという二人の女性の役割は大きいと著者は指摘する。その人生にも、革命理論と実践の研ぎ澄まされた融合がある。最終章で五人の女性が、革命後どのような人生を辿(たど)ったかが描かれる。各様の姿にロシア革命の悲劇も宿っていて考え込む。
評・保阪正康(ノンフィクション作家)
*
岩波書店・3990円/さいとう・はるこ 36年生まれ。元帝京大教授。ロシア現代史、国際関係史。












