「ヒトラーの秘密図書館」書評 愛読書からナチス哲学を分析
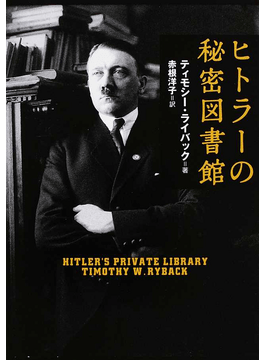
ISBN: 9784163721200
発売⽇:
サイズ: 20cm/373p
ヒトラーの秘密図書館 [著]ティモシー・ライバック
W・S・チャーチルは、『第二次世界大戦』の中で、あえて一章を設けてヒトラーに言及している。彼の『我が闘争』は、「人間は闘う動物である。ゆえに闘う者の独立社会である国家は戦闘単位である」と説いたにすぎないと冷笑する。本書の著者によると、一九二五年に出版されたこの書は、ギュンターの『ドイツ民族の人種的類型学』や自動車王フォードの著した反ユダヤ主義の『国際ユダヤ人』などの影響を受けているが、ヒトラーは体系だった学校教育を受けていないがゆえに基礎的知識に欠けていたというのだ。
「貧弱な知的内容」「文法上のひどい誤り」「語彙(ごい)と構文の間違いだらけ」、まさに欠陥本なのだと具体的に説く。
本書はヒトラーの蔵書のうちアメリカ議会図書館に所蔵されている千二百冊分を軸にしながら、ヒトラーはどのような書物で学んだのか、そこにはどういう書きこみがあるのかを彼の政治権力獲得、そして総統になっての流れに沿いながら解説した書である。ベンヤミンの「蔵書を見ればその所有者の多くのことが分かる」を土台に据えての分析は確かに新しいヒトラー論である。
ヒトラーが読書家だったのは事実で、総統になって日々忙しいときにも夜を徹して書を繙(ひもと)いていたらしい。本書は愛読書の中から十冊を選び、それらの書とかかわりをもつ反ユダヤ主義、人種優位論、オカルト、それに軍事書などを通して、いわゆるナチス哲学をつくりあげていったプロセスを明かすのだ。
その読書法もユニークで、先に目次や索引を読み、自らの観念に合致する語などを見いだしてその部分をすぐに知識にしていき、さっそく演説に利用して国民を鼓舞していたらしい。グラントの『偉大な人種の消滅』にもっとも魅(ひ)かれていたと著者は言い、「そのゆがんだ歴史観」を示す箇所(かしょ)も本書で引用されている。正直に言えば、「ヒトラー」は二十世紀の反文明、反ヒューマニズムが生んだ人工的産物とも思えてくる。書を読む姿勢を説いていると思えば、今に通じる教訓も含まれている。
評・保阪正康(ノンフィクション作家)
*
赤根洋子訳、文芸春秋・1995円/Timothy W. Ryback 歴史研究家。『自由・平等・ロック』など。












