「人類冬眠計画」書評 救急医療や宇宙進出への応用も
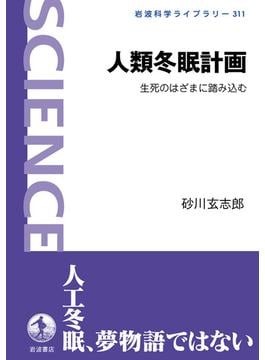
ISBN: 9784000297110
発売⽇: 2022/04/16
サイズ: 19cm/112,3p
「人類冬眠計画」 [著]砂川玄志郎
冬眠は、ひそかに気にはなっていた。
ヒグマは水を飲まず、排尿・排泄(はいせつ)もせずに冬眠の4カ月を乗り切り、体重は3割減っても筋肉は衰えない――昨年本欄で紹介した『アーバン・ベア』という本にこんな驚きの記述があったからだ。入院しただけで体力が落ちる人間とは大違いだ。
哺乳類の体温はおよそ37度に保たれている。人間なら5度上下するだけで生死の境をさまようことになるが、北極には体温が氷点下になっても血液が凍らずに循環するリスがいる。マダガスカルには乾期になると体温が20度台に下がって冬眠に入るサルもいる。
救急医療から人類の宇宙進出まで、その応用範囲や可能性については本書を読んでいただくとして、大昔から知られた現象でありながら、極端な低体温でも生きていける仕組みの詳細はわかっていない。同じ冬眠でも、外界の温度で体温が変わる爬虫(はちゅう)類のような変温動物とは別の機能が備わっているらしい。
冬眠する実験動物が身近に存在しないという研究の制約に風穴を開ける成果が2年前に発表された。著者を含めたチームがマウスを人工的に冬眠状態にすることに成功したのである。
その方法を人間に当てはめるのは難しいとしても、雪山で遭難して奇跡的に助かった人がいることなどを挙げ、潜在的に冬眠能力を持った人がいてもおかしくないという著者の指摘は十分うなずける。
結果よりもむしろ実験を組み立てていく過程が科学者ではない素人にとっては面白い。たとえば、著者はストレスをかけずにマウスの体温と酸素消費量を測る装置の開発に半年を要している。独創的な研究は本来、こうした「手作り感」を伴うものなのだと思う。
わずか100ページ余りのなかに生命工学や生命現象の基礎知識もちりばめられている。壮大なタイトルに引かれて手に取ったが期待を裏切らない。
◇
すながわ・げんしろう 1976年生まれ。理化学研究所生命機能科学研究センター上席研究員。小児科医。












