「チーム・オベリベリ」書評 開拓団を支えた「捨て石」の覚悟
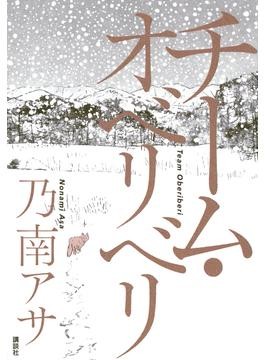
ISBN: 9784065201145
発売⽇: 2020/07/02
サイズ: 20cm/667p
チーム・オベリベリ [著]乃南アサ
明治十六年、英学塾の学友だった依田勉三・鈴木銃太郎・渡辺勝の三人は北海道開拓を決意、「晩成社」を立ち上げて同志を募り、十勝の原野に入植した。
彼らが選んだ地はアイヌの言葉でオベリベリ。今の帯広である。
十五年で三千万坪を切り拓(ひら)く予定だったが、厳しい自然やバッタの害などで開墾は遅々として進まない。女性を含めて三十名いた開拓団も脱落者が相次ぎ、どんどん減っていく。
そんな開拓の最初の七年間を、鈴木の妹であり渡辺の妻である渡辺カネの目から描いたのが本書だ。
カネは横浜の女学校を卒業した、当時の最先端の女性である。それが、夫に従って入植し、粗末な小屋に暮らし、子を産み、畑を耕し、豚を育て、アイヌ民族と交流し、開拓団の子どもに勉強を教える。予想もしていなかった環境に身を置くことになったのである。
開拓の具体的な描写も圧巻だが、新たな環境にどう向き合ったかが読みどころだ。武士や素封家など、かつての自分を捨てられない者もいる。恨み言ばかりの者もいる。そんな中、カネは幻滅や諦めを体験しつつも、妻として母として、武士の娘として、アイヌ民族の隣人として、自分の為すべきことを見つけていく。
彼女を支えたのは教育と信仰だ。自分の芯になるものを持っている人間の、何と強いことだろう。
カネの印象的な言葉がある。「私たちの代が、耐えて、耐えて、この土地の捨て石になるつもりでやっていかなければ、この土地は、そう容易(たやす)くは私たちを受け入れてはくれない」
覚悟とは、こういうことだ。その言葉通り、晩成社は解散する。しかし彼らが広大な原野に記した最初の一鍬(くわ)が、今の帯広の礎になったことは間違いない。
先の見えないコロナ禍の中、未体験の日々に戸惑う今の世が、どこかオベリベリの開拓団に重なって見えた。私たちにカネのような芯はあるだろうか。
◇
のなみ・あさ 1960年生まれ。96年、『凍える牙』で直木賞、2011年『地のはてから』で中央公論文芸賞












