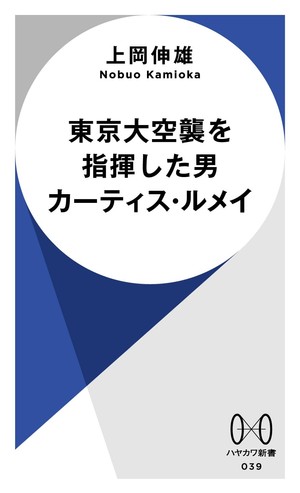
ISBN: 9784153400399
発売⽇: 2025/02/19
サイズ: 10.5×17.3cm/288p
「東京大空襲を指揮した男 カーティス・ルメイ」 [著]上岡伸雄
東京大空襲を指揮したカーティス・ルメイの名前を評者が知ったのは、マルコム・グラッドウェルの『ボマーマフィアと東京大空襲』であった。そこでは、ルメイは、軍事施設や軍事工場だけを爆撃して人道的に敵を無力化することを目指す「精密爆撃」論者と対比されることで、冷酷無慈悲な存在として描かれる。そのルメイの人生と思考回路を、アメリカ文学の研究者が見事に掘り下げたのが本書だ。
本書によれば、実際のルメイは残忍な人物というよりは、組織や命令に忠実で、有能な現実主義者だったという。部下からの信頼も厚かった。だが、現実主義者であるが故に、住宅密集地にも空襲しなければ、やがては日本本土へ侵攻せざるを得なくなり、両国とも犠牲者がもっと増えるはずだと考えていた。そして、それは当時の米国における一般的な見方でもあった。だから、ルメイは戦争の英雄になったのだ。
だが、空襲の「成功」によって自身の考えの妥当性を確信したことで、戦後は次第にタカ派的な傾向を強め、アメリカが核兵器を含む先制攻撃も辞さないことこそが最善だと信じて疑わなくなる。大統領選に副大統領候補として出馬したのも、ベトナム政策に対する自身の考えを世間に訴えるためだった。
東京大空襲で住宅密集地を中心に攻撃したのは、軍事部品の工場が住宅地に点在していたからだと主張される。最近もどこかで聞いたような話だ。大量殺戮(さつりく)の言い訳はいつの時代にもある。
戦後、日本政府は、航空自衛隊の育成に貢献したとしてルメイに叙勲している。その時も、問題になったのは原爆投下の責任者だったかどうかという点だけだったという(ルメイは原爆投下にあまり関わっていない)。日本は、いつの間にか勝者の論理と同化してしまったようだ。戦後八十年を迎える我々は、今、ルメイが体現した「戦争を正当化する論理」の誘惑に抗(あらが)うことができるだろうか。
◇
かみおか・のぶお 1958年生まれ。翻訳家、学習院大教授(アメリカ文学)。フィリップ・ロスらの翻訳を手がける。












