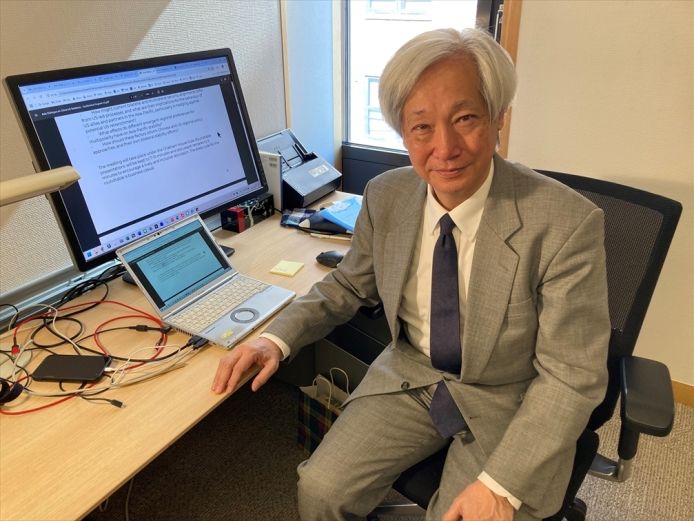
「トランプ2・0」の激動に、地球を何周もする勢いで飛び交うニュースや陰謀論――。国際政治学者の藤原帰一さんは2011年から朝日新聞夕刊に連載コラム「時事小言」を寄せる。ただ、国際情勢と日本の行く末を論じるその藤原さんでさえ、21世紀は「その時々の情勢にふりまわされている」世界だという。少しでも確からしい手がかりをどう求めているのか。碩学(せきがく)の知恵を聞いた。
「自分が状況を捉えているのか、不安を抱えて書いた文章ばかり」
藤原さんは著書「世界の炎上」(朝日新書)のまえがきで苦しい胸の内を明かす。前著「不安定化する世界」(同)に次いで、20年からの連載をまとめた。コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻、イスラエル・パレスチナ紛争など歴史に残る出来事を論じた。
目下、世界最大の関心事はトランプ米大統領の動静だろう。SNSで度々投稿される本人の途方もない発言。藤原さんは「何を考えているのか本当のことは分からない」としつつ、手がかりに、米保守派の政権移行に向けた政策集「プロジェクト2025」の存在を挙げる。100以上の保守系団体が参加し、ワシントンの有力シンクタンク・ヘリテージ財団が23年にまとめたものだ。「トランプ氏自身は関係を否定するが、事実上の選挙公約と見ていいのでは」
マスメディアは今も情報摂取の軸だ。「ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストといった新聞、CNNやBBCなどのテレビ、エコノミストやアトランティックなどの高級誌は、目先の状況の変化に振り回されず、分析が比較的安定している」
だが、現在進行形で展開する世界情勢の分析はやはり困難を伴う。「たとえ現場にいても何が本当で何がうそか分からず、何がニュースかが分からない。うそをうそと承知で主張する政治家や言論人もいる」
軍事研究の大家クラウゼビッツはこれを「戦場の霧」と呼び、限られた情報からいかに確からしい視点を得るかを論じた。では、価値がない議論を見分けるポイントは?
「分からないことについて分かったかのように論じるもの」。ただし、自省の言葉も添える。「自分も一人の書き手として何らかの思い込みが避けられないし、認識や見通しを誤ることもある。どこまではっきり言えるのか。そして、どこから先は言えないのか。確かな分析かどうかは、ほとんどこの一点に尽きる」
人はどうしても、膨大な情報を単純化し、ストーリーをつくりたくなる。ところが、世界情勢の分析は「そもそも推論のもとになるデータセットが安定していない。いくつかの可能性を指摘するのがせいぜい」だという。
「マスメディアの記事や学術研究の知見を総動員し、歴史にも学ぶ。ただし過去の事例をもとにした比喩や比較は単純化に陥る危険もある」
注目するのは、組織や媒体単位ではなく書き手個人。自ら取材・分析し、分からないことを「分からない」と言えるかどうかが見極めのポイントであり、自らもそうした書き手の一人でありたいと語る。
戦争に反対する者は、戦争を引き起こす者に対抗する何らかの力をもって連帯する必要がある。藤原さんは、この「力により平和を保つ」ジレンマを直視するのが、国際政治学の神髄だと語り、こう述べる。「国際政治や戦争の勉強をしてきた自分だからこそ踏み込んで言えることがある。新聞に書く場を与えられているからには、逃げずにギリギリの線で書く」
「20~30代の頃は、時事評論なんかやるもんかと思っていた」
恩師の坂本義和や丸山真男は「権威の殻に閉じこもった空想的な進歩的知識人」というレッテルを貼られがちだった。
「学者は、自分が世間が思うようなことを言っている人ではないと言わなければならない。自分に貼られたラベルとの格闘を今後も続けたい」(大内悟史)=朝日新聞2025年4月30日掲載












