「自画像の思想史」書評 〈自分〉笑い飛ばす俳画、見直す
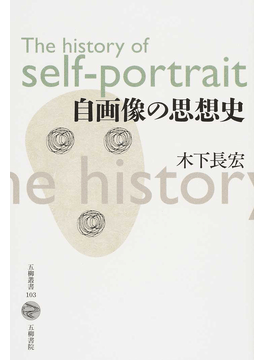
ISBN: 9784901646291
発売⽇:
サイズ: 20cm/597,7p
自画像の思想史 [著]木下長宏
「自画像」というと、絵の具べったりの額入り画が思い浮かぶだろう。展覧会の冒頭に掛けられていたりする。でも、自分自身を描くという本来の意味に従えば、その範囲はもっと広がるはずだ。本書はそうした自画像の歩みを洞窟壁画の時代から説きおこした労作。
中世以前は自画像は描かれなかった。そのためには自分を他者として見つめなければならないが、他者とは神であり、同じ人間をそのようにみなす視点はなかった。近代になり、「人間とは何かを探し求める」ようになってようやく自画像への関心が高まる。
ところが、日本ではこうした道筋をたどっていない。自分をどう解釈して描くかよりも、描かれたものを「お互いにどんなふうに観じ合っているか」が大切にされた。自己を他者との間をとりもつ媒体にする気持ちが強かったのだろう。
なかでも著者が高く評価するのは俳画の系譜である。例にあがる一茶、蕪村、良寛、白隠らの絵を面白いとは思っても、西洋の自画像と同列に考えたことがなかったので、この比較にはハッとさせられた。
日本の肖像画は、大まかに言うと、死後の供養のために描く東アジアの御影(みえい)の系統に、日本の特有の見立ての思想が乗っかって進んできている。親しまれた画題に自己を見立てて入れ替える連想ゲームに似た行為により、江戸末期の俳画は花開いた。著者はそこに、自己を追いつめるのではなく「〈自分〉を笑い飛ばしてみんなと静かに生きている」精神を見いだす。
簡単に自分を写せる自撮り棒が流行(はや)っている現代は、鏡のなかの自己を見つめ描いた時代とは隔世の感がある。他者との境界は曖昧(あいまい)で、自己は萎縮か肥大かのどちらかに走りがちだ。
こんないまだからこそ、明治の欧化の影響下でかき消えた俳画の精神を見直そうと著者は言う。世界との関係のとり方を突きつめずに自己と戯れる、融通無碍(むげ)なあり様こそが逞(たくま)しい。
◇
きのした・ながひろ 39年生まれ。元横浜国立大学教授。『岡倉天心』『ゴッホ〈自画像〉紀行』など。












